医療機関で大きな病気やけがの治療を行うと、医療費がどのくらいかかるのか心配になります。また、病気が増えて複数の診療科に定期的に通うことになると、その費用も積み重なり、さらに心配は増すことでしょう。
しかし、高額療養費制度を利用すれば、医療費の負担が大きくなり過ぎるのを防ぐことができます。では、この制度は、どのような場合に利用でき、医療費はどのくらい戻ってくるのでしょうか? 本記事で解説します。
高額療養費制度とは?
高額療養費とは、どのような制度なのでしょうか?
「高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。」
出典:全国健康保険協会(協会けんぽ) 高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)
上記の定義によれば、この制度を使えば、医療費が一定額(自己負担限度額)を超えると、超えた分があとで戻ってくる、ということが分かります。
では、自己負担限度額とは、一体いくらなのでしょうか? これは、利用者の年齢(70歳未満か70歳以上か)、さらにその方の所得によって変わります。
図1、2は、協会けんぽにおける、70歳未満と70歳以上の被保険者の自己負担限度額を示した表です。
この表を見ると、70歳未満は「所得区分」によって「ア」から「オ」までの5段階に、70歳以上75歳未満は大きく分けて「現役並み所得者」「一般所得者」「低所得者」の3段階に分かれており、その区分に応じて「自己負担限度額」が定められていることが分かります。
このように、医療費の自己負担限度額は年齢や所得がどのくらいあるかによって定められ、これを超えた場合は支払った医療費が戻ってくるという仕組みになっています。
図1:70歳未満の被保険者の自己負担限度額
出典:全国健康保険協会(協会けんぽ) 高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)
図2:70歳以上75歳未満の被保険者の自己負担限度額
出典:全国健康保険協会(協会けんぽ) 高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)
高額療養費制度を理解するうえでのポイント
図1、2を見れば、医療費がいくら戻ってくるかがすぐ分かります、と言いたいところですが、その計算はやや複雑です。ここでは、高額療養費でいくら戻ってくるかを知るに当たり、大切なポイントを挙げておきます。
1. 所得区分の判定タイミングは年2回。
図表1、2にある「所得区分」とは、いつの時点の所得なのでしょうか?
これは誤解が多い点ですが、医療を受けた時点の所得で決まるわけではありません。この所得区分は、毎年1月~7月に受けた医療であれば前々年、8月~12月であれば前年の所得金額で決まります。
例えば、70歳未満の方が8月に医療を受けた場合、所得区分は、「その年8月の給料が30万円だったから『ウ』になる」のではなく、「前年の標準報酬月額(健康保険料や社会保険料を算出するために、給与や賞与、残業代など各種手当の合計額を元に算出した金額)に基づいて決まる」ことになります。
なお、標準報酬月額については、給与や賞与明細を基に調べることも可能ですが、分からない場合は勤務先の給与担当部署や健康保険組合などに確認するとよいでしょう。
2. ひと月分(1日から月末まで)に支払った医療費が、高額療養費の対象となる。
例えば、医療費を「6月10日」「6月15日」「7月2日」の3回払ったとします。それぞれの金額が2万円、3万円、4万円だった場合、高額療養費は6月分を5万円(2万円+3万円)、7月分を4万円として計算します。
したがって、6月の5万円、7月の4万円のうち、それぞれ限度額を超えている部分が払い戻しの対象となります。くれぐれも、6月分と7月分を合算してしまわないように注意しましょう。
3. 70歳未満の場合、高額療養費は「医療機関ごと」「診療科ごと」「入院もしくは外来」に分けて計算する。さらに、それぞれの自己負担額が2万1000円未満の場合は合算できない。
高額療養費は、その月にかかった全ての医療費を単純に合わせて計算するわけではありません。合算の方法にはルールがあり、70歳未満の場合は次の方法に従って計算します。
A 医療機関ごとに分ける
B 同じ医療機関内で医科と歯科に分ける
C さらに、入院と外来に分けて計算
D 外来と「その外来に対する薬局(調剤)」は合算して計算
例えば、同じ月にA病院の内科で2万円、A病院の歯科で3万円、B病院の耳鼻科で3万円支払ったとします。
上記の計算方法に従って計算すると、次のようになります。
●A病院は、内科(2万円)が2万1000円未満のため合算できず、歯科の3万円のみが対象となる。
●B病院は耳鼻科で2万1000円以上のため、かかった費用(3万円)がそのまま合算対象となる。
したがって、対象となる費用はA病院とB病院の合算で3万円+3万円=6万円となり、この金額から自己負担限度額を超えた分が払い戻しの対象となります。
くれぐれも、全ての医療費を単純に合算してしまわないように注意してください。
4. 高額療養費は、同一世帯の家族の分も合算できる。ただし、70歳未満の方については、自己負担額が2万1000円以上の場合のみ対象となる。
高額療養費を計算する際は、原則として家族(被扶養者)の分も合算することができます。ただし、被扶養者の方が70歳未満の場合、自己負担額が2万1000円以上でなければ合算することはできません。
例えば、同じ月の自己負担額が、本人は3万円、妻(被扶養者、48歳)が2万円、父(73歳)が1万円だったとします。この場合、妻は70歳未満かつ2万1000円未満のため、合算することができません。
一方、父も2万1000円未満ですが、こちらは70歳以上であるため、合算することができます。したがって、この例の場合、本人の3万円と父の1万円を合わせた4万円が高額療養費の対象となります。
高額療養費でいくら戻るかはケース・バイ・ケース
それでは、本記事の表題にある「医療費が2万円以上かかると、高額療養費制度によってどのくらい戻ってくるのか」について考えてみます。
これまで解説した注意点を踏まえると、いくら戻ってくるのかは一概には言えないことが分かります。そこで、以下の2つの例で、どのような結果になるかを見てみましょう。
(例1)70歳未満で、所得区分が「エ」の方が、同じ病院、同じ診療科で4万円をひと月の間に自己負担した場合
この場合、自己負担額が2万1000円以上のため、高額療養費の合算については対象となります。しかし、所得区分「エ」の自己負担限度額5万7600円を超えていないため、医療費の戻りはありません。
(例2)3人家族(全員70歳未満)で、ひと月の間に本人(所得区分「エ」)がA病院の内科で2万5000円、B病院の外科で1万5000円、妻がC病院の内科で2万5000円、子がD病院の内科で3万円を自己負担した場合
この場合、3人分を全て合計すると、ひと月で2万5000円+1万5000円+2万5000円+3万円=9万5000円かかっていることになります。
しかし、高額医療費の合算ルールに従うと、本人のB病院分(1万5000円)は合算できないため、対象となる合算額は9万5000円-1万5000円=8万円となります。このとき、医療費の戻りは、8万円-自己負担限度額(5万7600円)=2万2400円です。
医療費が高過ぎて不安な方は、一度相談を。
ここまで見てきたとおり、高額療養費制度によっていくら戻ってくるかは、どの月か、どの医療機関か、どの診療科か、家族の構成は、など状況によってケース・バイ・ケースです。
また、本記事では取り上げませんでしたが、多数該当という、医療機関にかかった回数に応じて限度額が引き下げられる仕組みもあり、これらを踏まえたうえで医療費の戻り額を計算するのはなかなか大変です。
もし、医療費がかかり過ぎていて心配だが、高額療養費の仕組みが複雑でよく理解できない、ということがあれば、お近くの市区町村役場に一度相談してみることをおすすめします。
出典
全国健康保険協会(協会けんぽ) 高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)
全国健康保険協会(協会けんぽ) Q家族も同じ月に病院を受診しました。すべて合算した金額で高額療養費は申請できますか?
執筆者 : 酒井 乙
CFP認定者、米国公認会計士、MBA、米国Institute of Divorce FinancialAnalyst会員。
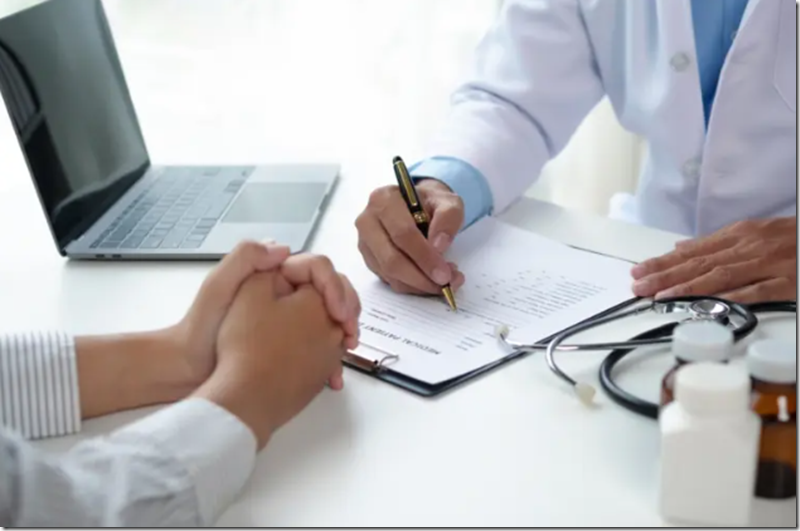




コメント