ピンピンコロリが理想! ただ、年齢が上がると何かと医療にかかる割合が高くなる。それが残念なことに、かえってヨボヨボの入り口になってしまう、ではどうしたらいいかを本書でお伝えする。
従来の「高齢者をヨボヨボにする医療」にNOと言う人のための指南書『 医者にヨボヨボにされない47の心得 医療に賢くかかり、死ぬまで元気に生きる方法 』から抜粋・ 再編集して紹介する。
『もし健診でがんが見つかったらどうする?…治療で寿命を縮めるか、がんと共存する人生か』より続く。
がんを防ぐための新12か条
国立がん研究センターが「がんを防ぐための新12か条」をまとめました。
これは、日本人を対象とした疫学調査や、現時点で妥当な研究方法で明らかとされている証拠をもとにまとめられたもの、とされています。
1 たばこは吸わない
2 他人のたばこの煙を避ける
3 お酒はほどほどに
4 バランスのとれた食生活を
5 塩辛い食品は控えめに
6 野菜や果物は不足にならないように
7 適度に運動
8 適切な体重維持
9 ウイルスや細菌の感染予防と治療
10 定期的ながん検診を
11 身体の異常に気がついたら、すぐに受診を
12 正しいがん情報でがんを知ることから
このなかで気になったのは、たばこについてです。

1の喫煙や、2の受動喫煙は肺がんのリスクを上げるもののひとつです。受動喫煙の害が叫ばれると、2020年4月1日に改正健康増進法が全面施行され、世の中の多くの場所(飲食店、会社などの事務所、娯楽施設、体育施設、宿泊施設など)が原則禁煙になりました。私は喫煙はしませんが、喫煙者が片隅に追いやられているのを見るとなんだか気の毒になります。
肺がんの原因はたばこだけではなかった?
肺がんの原因はたばこだけではないのに、喫煙者だけが非難されるのはフェアではありません。喫煙率は以前の3分の1に下がっているのに、肺がん死はむしろ増えています。
かつて日本人の肺がんは、ほとんどが扁平上皮がんでしたが、喫煙率が下がってから、およそ10〜15年後に扁平上皮がんは減っています。今の扁平上皮がんは3割ほどで、6割くらいが腺がんです。おそらく原因物質として、粒子の大きいものが気管支で引っかかって扁平上皮がんとなり、粒子の小さいものが肺の奥まで運ばれて腺がんを引き起こしていると考えられます。

腺がんの発症要因は、おそらく粒子の小さな大気汚染でしょう。国内の工場からの煤煙などは、以前よりずっときれいになりましたが、中国の経済発展とともに大陸からPM2.5と呼ばれる微粒子が飛んでくるようになりました。自動車の排ガスも問題です。道路工事と警察の過度な規制で発生した渋滞時の排ガスが特に悪い、と私は考えています。また、腺がんの原因にはホルモンも関係していると言われています。
『 医者にヨボヨボにされない47の心得 医療に賢くかかり、死ぬまで元気に生きる方法 』は絶賛発売中!
2年連続新書ノンフィクションベストセラー1位となった『80歳の壁』の著者・和田秀樹医師が、高齢者とその家族に最低限知っておくべき医療とのつきあい方を伝授する初めての本。
団塊世代も全員75歳以上になり、日本は65歳以上が3人に1人の社会です。
残りの人生を楽しんで生きる高齢者が一人でも多くなってほしい、という思いで書かれたのが本書です。
たとえば、年齢が上がると病気になることが多くなります。
とともに年齢を感じるようになったら、「健康願望」「長生き願望」「寝たきりへの恐怖」などから医療にかかる割合が高くなるでしょう。それが残念なことに、ヨボヨボへの入り口になります。
薬ひとつとっても、そうです。健康診断で血圧やコレステロールが基準値を超えているから、そろそろ薬をと医者から言われます。そして、健診を受けるたび飲む薬が増えていき、5種類以上になると転倒などの割合が一気に上がります。
著者が、30年以上にわたる高齢者医療の経験とさまざまなデータから、著者ならではの「心得」を47にまとめました。
そこには、体だけでなく心や脳が生き生き若返る生き方のアドバイスもあります。本書は、高齢者のための新常識なのです。


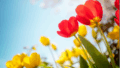

コメント