中国政府が着手した世界最大級のダム建設
中国政府がチベット自治区で世界最大級の巨大ダム建設に着手したとBBCなど各メディアがいっせいに報じた。計画の存在は以前から知られていたものの、実際に工事が進んでいることが衛星画像で確かめられたのだ。
私は、2022年9月5日、ダイヤモンド・オンラインに「『中国の水問題』が危機的状況、世界的な食糧不足や移民増加の可能性も」を寄稿した。
その中では、中国が深刻な水危機に直面している現状と、国内での水資源争奪戦が不動産購入行動に影響を与えている可能性を指摘した。
それから3年たったが、状況はむしろ悪化していると言っていいだろう。
中国は水の豊富な南部から水不足の北部へ水を回す政策を長年進めてきた。その象徴が2006年に完成した三峡ダムである。
だが、この巨大プロジェクトは多くの問題を抱えており、環境破壊、地滑り、下流の洪水被害など、当初から懸念されてきた弊害が繰り返し報告されている。
それにもかかわらず、中国はさらに巨大規模のダム建設計画を推し進めており、今回はさらに国際的な緊張を直接高めるリスクがある。
ダム建設地は中国西南部で水が豊富なチベット高原にある。
この地に建設される新たな巨大ダムは、世界最大規模の水力発電能力を誇る可能性があり、その影響は周辺国にも及ぶ。しかも、インドとの軍事衝突すら引き起こしかねないほどの深刻さである。
巨大ダム建設がもたらす圧倒的な電力量
中国政府は現在、チベット高原のヤルンツァンポ川上流において、史上空前の規模となる水力発電プロジェクトに着手している。
李強首相は今年7月、この計画を「世紀のプロジェクト」と称し、国家の威信をかけた事業であると強調した。
ヤルンツァンポ川はヒマラヤ山脈を東から西へ流れ、その後インド北東部に入るとブラマプトラ川と名を変え、バングラデシュを南下してガンジス川と合流する。
そのため、中国・インド・バングラデシュの3カ国の国民生活や農業や工業を支え、各国の生命線ともいえる河川である。だが、この水系の管理については国際的な包括協定が存在せず、上流を支配する中国が一方的に水流を操作できるいびつな条件下にある。
建設が進んでいる新ダムは、世界で最も深い峡谷とされるヤルンツァンポ大峡谷のU字型の急カーブを迂回する形で、長さ480キロメートル以上、深さ約3キロメートルの地下トンネルを掘削し、水を一気に落差の大きい地点まで導くものだ。
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2025/07/562330.php
ダムは合計5基作られ、発電量は三峡ダムの3倍に達すると試算されている。三峡ダムは約4000万世帯分の電力を供給できる巨大発電施設でもあるが、新ダムは1億世帯以上を賄う潜在能力があるとされる。
2006年に完成した三峡ダムの建設では、約130万人が強制移住させられ、長江に全長644キロメートルの巨大貯水池が誕生している。今回のプロジェクトも膨大な人の移動と環境変化を伴うことは避けられない。
周辺地域には希少生物も多く生息しており、環境団体などがその影響を強く懸念している。
エネルギー自給と環境配慮の矛盾
中国は2023年時点でエネルギー供給の約4分の1を輸入に依存している。米中対立が激化する中、人口の多い中国にとってエネルギー安全保障の確立は急務である。習近平指導部が進める再生可能エネルギーの拡大もその一環だ。
また、中国はデフレに突入しつつある。その原因の1つに供給過剰があり、新ダムはセメントや鉄筋、労働力などの余剰を吸収する役割が期待されている。つまり、デフレ対策も兼ねているわけである。
新ダムは発電した電力を、経済の中心地である広東省、香港、マカオなどへ送電する構想で、総工費は約1.2兆人民元(24兆7500億円)と桁違いの規模だ。
https://www.reuters.com/sustainability/climate-energy/china-embarks-worlds-largest-hydropower-dam-capital-markets-cheer-2025-07-21/
このダム建設は、習指導部の「生態文明」政策(中国版グリーン政策のこと)に沿う形で、表向きは環境に配慮した水力発電計画として進められている。近年、環境保護に力を入れ、再生エネルギーを国家的産業として育成してきた中国としては、この巨大ダムにおける電力事業は「目標のつじつま」を合わせるためにも、どうしても貫徹しなければならなくなっている。
とはいえ、チベット高原は地震多発地帯であり、過去にはマグニチュード8級の大地震も発生している。この巨大ダムが地殻変動に直面した場合、活断層上に造られた三峡ダム並みにリスクが高く、大地震が起これば甚大な被害を引き起こす可能性がある。
さらに、建設現場ではチベット人労働者への過酷な労働強制や土地収用が懸念されている。中国政府は長年にわたりチベット文化や宗教活動を抑圧してきた経緯があり、今回のプロジェクトでも同様の人権問題が国際社会から批判されることは避けられないだろう。
https://www.ft.com/content/49ef27fb-ba46-4ffb-8c36-48eb58d70fc9
しかも、このダムは複数の国にまたがる国際河川に建設されるので、下流域にあたる国々に大きなダメージを与えかねないものだ。それを中国だけの都合で進めていることには、多くの批判が巻き起こりつつある。
下流の周辺国を巻き込むリスク
チベット高原は「アジアの水の塔」とも呼ばれ、インド、バングラデシュ、タイ、ミャンマー、ラオス、ベトナムなど多くの国の主要河川の源流が存在する。ところが、近年、地球温暖化による氷河後退が急速に進み、水量そのものが減少傾向にある。
下流に位置する国々は、中国のダム建設によって水量が不安定化し、堆積(たいせき)物の減少や農業・漁業への打撃が避けられないと主張。近年、異常気象が頻発する中では、ダムの放水判断が難しく、誤れば大規模な洪水を引き起こす恐れがある。
実際、三峡ダムの下流域では度重なる水害が発生し、数百万人が避難を余儀なくされた事例もある。
インド北東部アルナチャルプラデシュ州のペマ・カンドゥ州首相は「中国は信用できない。ダム建設は我々の生活に危機をもたらすだろう。『水爆弾』のように利用する恐れがある」と述べている。
https://www.yomiuri.co.jp/world/20250729-OYT1T50038/
同州首相がこの新ダムを「水爆弾」と呼ぶのは、中国では三峡ダムにおいて「ためて使う」という従来の方法が機能しておらず、ダム建設後にも深刻な水害が起こっているからだろう。
また、中国政府はこの州を「南チベット」と呼び、自国領土と主張している。ダム建設で明らかに影響のあるインドのアルナチャルプラデシュ州に対しても、中国は「自国の周辺の範囲」という理屈で強引に抑え込もうとする可能性がある。そうなればインドも静観できなくなり、中国に対して何らかの報復措置をとりかねない。
現在、インドは対抗策として、同じブラマプトラ川流域に複数の水力発電ダムを建設する計画を進めている。両国が互いに上流域での水流支配を強めれば、洪水や渇水のリスクが相互に高まる「負の連鎖」に陥る可能性がある。
中印国境地帯では、1962年に武力衝突(中印国境紛争)が起きており、2020年にもガルワン渓谷で両軍兵士が殴打戦を繰り広げ、死傷者が出た。
今回のダム建設は、この不安定な国境地域に新たな紛争の火種を持ち込むことになる。もしこのダムがインド側から「中国による戦略的施設」とみなされれば、有事の際に標的となり下流地域には大きな被害が生まれる。
この新ダム建設にまつわる問題は単純な水を巡る争いから起こっているのはない。水源問題、水管理問題、領有問題などの複数の問題が絡み合っており、最終的には国土を干上がらせないための国家の威信を賭けた争いにもなりかねない。
このダム建設が両国の武力衝突に発展し、一気にアジア状勢が不安定化する懸念が存在するのである。
気候変動がもたらす国際紛争への巨大リスク
今回の巨大ダム建設は、単なるインフラ整備にとどまらず、気候変動というグローバルな課題とも密接に関係している。
先述したように、「アジアの水の塔」と呼ばれるほど水に恵まれたチベット高原には、ヒマラヤ山脈に源を持つ河川が多数流れ出している。これらの河川は、インド、バングラデシュ、ミャンマー、ラオス、ベトナムなどの国々にとって、生活用水のほか、農業・工業・漁業などの産業基盤になっている。
ただし、近年は地球温暖化の影響でチベット高原の氷河が急速に融解している。このことが、チベット高原を源流にしている川の水量の変動を激化させている。特に冬季には水不足、夏季には氾濫という極端な季節変動が頻発しており、下流国の水資源管理はますます困難になっている。
中国が建設中のダムは、こうした不安定な水量を制御する目的もあるとされるが、逆に水流の人工的な操作が下流国にとって予測不能なリスクをもたらしうる。
特に、氷河融解による急激な水量増加がダムに蓄積され、それが一気に放出された場合、下流域では壊滅的な洪水が発生する恐れがある。
また、氷河の後退は長期的には水源を枯渇させるものである。巨大ダムを建設すれば一時的には水を制御できるかもしれないが、気候変動が続けば制御不能に陥って、将来的には水資源の持続可能性が失われていく。地域によっては、中国国内における水不足による移住はすでに進行しつつあり、今後は水が手に入らなくなった地域から多数の「水難民」を生む可能性がある。
このように、気候変動と氷河融解は、ダム建設の技術的・地政学的リスクに加えて、環境的・持続可能性の観点からも重大な課題を突きつけている。
国際社会は、越境河川の利用に関して、気候変動の影響を踏まえた新たな枠組みの構築を急ぐべきであり、中国の一方的な開発がもたらすリスクを共有・監視する体制が求められている。
中国からの「水難民」が日本に押し寄せる可能性も
通常、国際河川については「国際水法」が存在しており、上流国は下流国の水利用を著しく損なわない義務を負うのだが、中国はこの枠組みに参加していない。
また、仮にインド政府やバングラデシュ政府が国際司法裁判所に提訴して建設中止が言い渡されたとしても、中国が従うことは期待できないだろう。日本にとっても、この問題によって中印対立が起これば「対岸の火事」ではなくなってしまう。
具体的には3つの問題が考えられる。
1つ目は、日本はまだまだ中国経済に依存している部分があり、中印紛争が起これば日本企業が深刻なトラブルに巻き込まれる可能性があることだ。
現在は中国とのデカップリングが進んでいるものの、両国間の貿易量はまだまだ大きい。特に中国製の日用品の輸入が多い日本側には、深刻な物不足が起こる可能性がある。
2つ目はインドが日本の戦略的パートナーであるための、外交の舵取りの難しさだ。中国はレアメタル磁石など、いくつかの重要資源を握っている。中国経済に依存しながらも、インドへの協力が必要になれば、日本は股割き状態に陥る。
3つ目は、先述したように長期的に中国やインドなどから多数の「水難民」が生まれる可能性があることだ。もし大量の水難民が出て、その一部が海外に避難しようとすれば、いずれも人口大国ゆえに、大きな数になりうる。
特に中国からは日本にも「水難民」が押し寄せる可能性は否めない。そうなれば、ヨーロッパで起こった中東難民問題と類似する治安問題が発生する可能性もある。
中国の巨大ダム建設は、中国政府にとって単なるインフラ事業ではなく、エネルギー安全保障に関わる根本的な問題である。
また、そこには中国が抱える水不足、環境、人権問題が裏に存在しており、巨大ダム建設を優先することで、日本を含む周辺国が多次元の問題に巻き込まれる可能性がある。
チベット高原の水資源をめぐる争いは中印両国の国境紛争と直結している。両国が衝突すれば、アジア全体の安定を揺るがしかねない。
中国が国内の水不足とエネルギー需要を解決するために、国際的な水資源の公正利用原則を無視すれば、その代償は国境を越えて拡大するだろう。中印間の「水の冷戦」が本格化する前に、国際社会が仲裁と監視の枠組みを構築できるかどうかが、今後の最も重要な課題だろう。
(評論家、翻訳家、千代田区議会議員 白川 司)


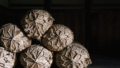
コメント