年金を受給していた人が亡くなったときに受け取れる年金といえば、遺族年金を思い浮かべる人が多いのではないでしょうか?
しかし、遺族年金のほかに未支給年金という年金もあります。遺族年金は要件を満たした人しか発生しませんが、未支給年金は基本的に年金を受給していた人が亡くなった場合、必ず発生します。
本記事ではあまり知られていない未支給年金について紹介・解説します。
年金を受け取っていた人が亡くなったら必ず発生する未支給年金とは?
年金は偶数月の15日(15日が土日祝日の場合はその直前の平日)に前月と前々月の2ヶ月分が支給されます。例えば4月に支給される年金はその年の2月分と3月分に該当します。
仮に年金を受け取っていた人が2月に亡くなった場合、2月分の年金は4月に支給されるので、2月や3月に死亡の手続きをするときは未払い(=未支給)の状態です。
このように年金を受け取っている人が亡くなった場合、必ず未払いの年金が発生します。亡くなった人に代わって遺族などが請求する未払いの年金を未支給年金といいます。ちなみに年金は亡くなった日が2月1日でも、2月分の年金は全額支給されます。
遺族年金と未支給年金の受給要件の違いとは?
年金を受け取っていた人が亡くなった場合、遺族年金が発生するケースがあります。遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。
遺族基礎年金を受給できるのは、亡くなった人に生計を維持されていた「子のある配偶者」か「子」です。子の要件は、亡くなった際に18歳になった年度の3月31日までの間にあること、または20歳未満で障害の状態(障害等級1~2級)にあることなので、高年齢の夫婦のケースでは該当しない場合がほとんどです。
一方で遺族厚生年金を受給できる遺族の範囲は前述のケースに加えて、亡くなった人に生計を維持されていた子のない配偶者、父母、孫、祖父母です。
そのため、すでに老齢厚生年金を受給している高年齢の夫婦の夫が亡くなった場合、夫の保険料納付済期間などが25年以上あるという要件を満たせば、配偶者である妻には遺族厚生年金の受給権が発生します。
未支給年金は遺族厚生年金を受け取れる遺族の範囲に加えて、3親等以内の親族も請求できるので、甥や姪でも生計を同じくしていたら請求することができますし、その他の受給要件はありません。
未支給年金を請求しないと年金のもらい過ぎになる場合も
年金は後払いですので、未支給年金は必ず発生します。さらに未支給年金の請求は受給権者の死亡届も兼ねています。仮に死亡届を提出しなかったり、提出が遅れたりすると、年金の支給が止まらずに過払いとなるケースもあります。
例えば2月に亡くなった場合、死亡の手続きを怠り、4月の年金支給時に2月と3月分の年金が振り込まれた場合、3月分は過払いとなってしまいます。過払い金が発生した場合はあとから返還する必要がありますので、年金を受給していた人が亡くなったら早めの手続きが必要です。
まとめ
年金を受給していた高齢の親が亡くなった場合、遺族年金が発生するか否かにかかわらず、未支給年金は必ず発生します。未支給年金を請求できる遺族は亡くなった人と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、その他の3親等以内の親族です。
未支給年金の請求は死亡手続きも含まれており、手続きを怠ると年金のもらい過ぎにつながる可能性があるので注意が必要です。
出典
日本年金機構 年金を受けている方が亡くなったとき
日本年金機構 遺族年金ガイド令和6年度版
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
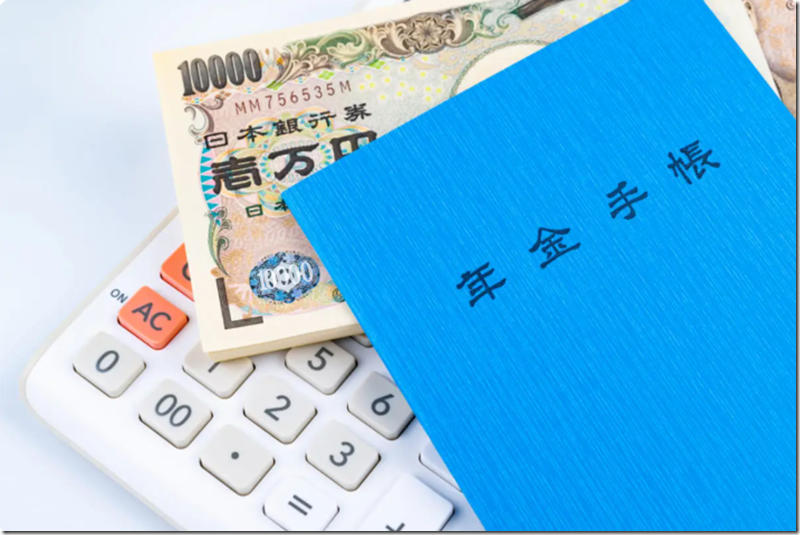


コメント