NISAやiDeCoは長期投資が基本です。運用が長期におよべば加入者の死亡リスクも高まります。加入者が亡くなった場合、NISAとiDeCoでは資産の取り扱いが異なりますので解説します。
NISA の加入者が死亡したら資産はどうなる?
NISA口座(非課税口座)を開設した方が亡くなった場合は、NISA口座で運用していた上場株式・投資信託等はNISA口座から払い出され、相続人は亡くなった方のNISA口座にある上場株式・投資信託等が、相続人の課税口座(一般口座や特定口座)に移管されます。
したがって、相続人が課税口座を持っていない場合は、被相続人がNISA口座を開設していた金融機関に課税口座を開設する必要があります。つまり、NISA口座そのものを相続人は引き継ぐことはできません。
移管するには、相続人は、亡くなったことを知った日以後遅滞なく、「非課税口座開設者死亡届出書」をそのNISA口座が開設されている金融機関に提出しなければなりません。
NISA口座から払い出される際、上場株式・投資信託等はNISA口座(非課税口座)を開設している方が亡くなった日の終値に相当する金額で、相続人が取得したものとして課税口座に移管されます。
例えば、亡くなった方のNISA口座の資産が500万円から700万円に増えていた場合(200万円の含み益)、課税口座に移管されるのは700万円となり、その後800万円になったときは100万円に対して課税されます。
逆に、NISA口座の資産が500万円から300万円に減っていた場合(200万円の含み損)、課税口座に移管されるのは300万円となり、その後500万円になった場合、当初の投資額に戻っただけなのに、課税口座で増えた200万円に課税されます。
つまり、NISA口座(非課税口座)を開設した方が亡くなったときまでの含み益は非課税措置の適用がありますが、損失についてはなかったものと見なされます。
なお、NISA口座(非課税口座)を開設した方が亡くなった日以後、その非課税口座で支払われるべき配当等がある場合には、その配当等には非課税になりません。
相続税の計算にあたっては、NISA口座から移管される資産と、被相続人のその他の資産の合計額が基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超えた場合、相続税が課税されます。
iDeCoの加入者が死亡したら資産はどうなる?
iDeCoの加入者・運用指図者または自動移換者の方が亡くなった場合、iDeCo口座の資産は所定日に投資信託等全資産が売却され、現金化したお金が死亡一時金として遺族の方に支給されます。なお、iDeCoの投資信託は死亡時の時価ではなく、所定日の売却価格が相続税評価額となります。
配偶者(内縁を含む)、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹のうちから、あらかじめ死亡一時金受取人を指定できます。
指定がない場合は、民法の定める相続の順位とは異なり、以下の順位になります。
第1順位:配偶者(死亡の当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)
第2順位:子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹であって、死亡当時に主としてその収入によって生計を維持していた者
第3順位:第2順位の人以外で、死亡した人の収入によって生計を維持していた親族
第4順位:子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹であって、第2順位の人に該当しない人
同順位の人がいる場合は上に記載されている順番通りになります。例えば、第2順位では子が父母に優先します。
死亡一時金を受け取るには、遺族は運営管理機関へ「加入者等死亡届」を、記録関連運営管理機関へは「死亡一時金裁定請求書」を、必要書類を添付して提出する必要があります。亡くなられた方の状況により、請求手続きが異なりますので詳細は亡くなった方がiDeCoの口座を開設していた金融機関に問い合わせましょう。
死亡一時金の請求は、死亡日から5年以内とされ、5年を超えると相続財産の扱いとなり、相続財産の扱いとなった後も請求がない場合は、法務局に供託されます。
死亡一時金は死亡退職金と同じ扱いで「みなし相続財産」として扱われ相続税の対象です。すなわち、受取人の固有財産であり遺産分割する必要がありません。また、相続人には非課税限度額(500万円 × 法定相続人の数 )の適用があります。
「みなし相続財産」として扱われるのは、被相続人の死亡後3年以内であり、3年超5年以内は受取人の一時所得になり5年超は「相続財産」として取り扱われます。
まとめ
NISA口座(非課税口座)を開設した方が亡くなった場合、NISAの資産は課税口座に移管され、相続税の対象となります。iDeCoの資産は相続人が、死亡一時金として受け取ります。死亡一時金の請求時期によっては課税される税金の取り扱いが異なります。
死亡一時金が「みなし相続財産」として相続税が課税される場合、NISAと異なり、相続人には基礎控除の他に非課税限度額(500万円 × 法定相続人の数)の適用もありますので、留意しておきましょう。
出典
金融庁 NISAを知る
国税庁 NISA及びつみたてNISAの手続に関するQ&A
国民年金基金連合会 iDeCo公式サイト
国税庁 No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金
執筆者:新美昌也
ファイナンシャル・プランナー


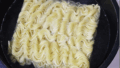
コメント