私は東日本の出身だが、幼い頃からコンビニやスーパーで見かけるボンタンアメが好きだった。祖父が良く買ってくれたボンタンアメ、あの南国の果実を思わせるパッケージ、橙色の包み紙に描かれたボンタンの絵柄は、どこか異国の香りがして、まだ見ぬ南の地への憧れをかき立てた。鹿児島という土地は、私にとってずっと訪れてみたい場所だった。
今回の旅では、鹿児島の食文化に触れることを目的に、天文館の居酒屋で「薩摩ゴールド」という地ビールを注文した。琥珀色の液体は、口に含むとさつまいもの甘みがふわりと広がり、苦味の少ないライトな味わいだった。このビールは、南薩摩特産の「黄金千貫」という品種のさつまいもを原料に、ラガー酵母でじっくり熟成させたものだという。芋焼酎の名門・薩摩酒造が手がけた発泡酒で、芋の風味をビールという形で再解釈した、まさに薩摩の浪漫が詰まった一杯だった。
そもそも「さつまいも」という名称は、薩摩地方から全国に広まったことに由来する。17世紀初頭、琉球王国から薩摩藩に伝わった芋は、前田利右衛門という船乗りによって鹿児島全域に広まり、江戸時代には救荒作物として全国に普及した。その過程で「薩摩から来た芋」として「さつまいも」という名が定着したのだ。
鹿児島が芋の産地として栄えた背景には、桜島の火山灰がある。県の面積の約6割を占めるシラス台地は、火砕流や軽石、火山灰が堆積した土地で、水はけが良く、栄養分が少ない。このような土壌は、米の栽培には不向きだが、さつまいもには理想的な環境だった。芋は肥沃すぎる土では葉ばかりが育ってしまうため、鹿児島の痩せた土地がむしろ芋の甘みを引き出すのだ。
焼酎文化もまた、芋と深く結びついている。鹿児島では古くから芋焼酎が親しまれており、地元の人々の暮らしに根ざした酒として、祝いの席や日常の晩酌に欠かせない存在だ。私は「三岳」という屋久島産の芋焼酎を黒じょかでいただいた。黒じょかとは、薩摩焼の土瓶で、焼酎を直火で温めるための酒器。土の香りと火のぬくもりが焼酎に移り、まろやかで深い味わいになる。三岳は芋の甘みと香ばしさが絶妙で、思わず「本当に美味しい」と声に出してしまった。
焼酎に合わせていただいたのは、黒豚の串揚げ。衣まで黒く、炭を練り込んだその姿は、見た目にも力強さを感じさせた。鹿児島の黒豚は、琉球から持ち込まれたバークシャー種で、さつまいもを与えて育てることで脂の甘みが増す。その肉質はきめ細かく、脂がさっぱりしていて、串揚げにしても重たさを感じさせない。鹿児島の「黒文化」は、黒豚、黒酢、黒糖、黒薩摩など、色に込められた力と誇りの象徴でもある。
酒を飲んだ帰り道、ほろ酔いのまま仙巌園のぢゃんぼ屋に立ち寄った。磯の潮風が頬を撫でる夕暮れ時、焼きたての両棒餅をいただく。香ばしく焼かれた小さな餅に、甘辛い醤油だれと黒糖きなこが絡み、口の中で静かにとろけていく。二本の串が刺さったその姿は、まるで刀を差した武士のようで、名の由来「両棒(ぢゃんぼ)」を思わせた。
この餅の起源は、南北朝時代にまで遡るという。懐良親王が谷山城に滞在した折、城主・谷山隆信が献上した餅に二本の串を刺し、味噌と黒砂糖を煮詰めたたれをかけたのが始まりとされる。江戸時代には「五文餅」と呼ばれ、谷山の名物として薩摩藩主にも献上された。やがて磯の地でも売られるようになり、明治期には「ぢゃんぼ餅」として親しまれるようになった。
旅の締めくくりは、天文館でいただいた「白熊」のかき氷だった。練乳をかけた氷にフルーツや豆類が盛られ、上から見ると白熊の顔のように見える。昭和22年、創業者の久保武氏がイチゴミルクの美味しさに着想を得て、氷に練乳をかけたことが始まりだった。その後、果物や豆を加えて現在の形となり、鹿児島の暑い夏に欠かせないスイーツとして定着した。見た目の可愛らしさと、どこか懐かしい味わいが、旅の終わりにふさわしい一品だった。
鹿児島の食文化は、味覚だけでなく、土地の記憶と人々の暮らしを映し出す鏡のようだった。火山灰に覆われた土地で育つ芋、その芋を酒に変える技術、酒を温める土瓶、豚に与えて旨味を引き出す飼料——すべてが連なり、ひとつの文化を形づくっている。
最後に、コンビニでボンタンアメを買い包み紙を見て思い出した。幼少の頃、祖父がよく買ってくれた懐かしい味。口に含むと、祖父の笑顔や、手を引かれて歩いた商店街の風景がよみがえる。鹿児島の食が、淡く美しい記憶を呼び起こしてくれた。もう戻れないが、この記憶があって良かったと思えた旅だった。異国情緒に憧れていたあの頃の記憶と、今ここで感じる土地の温もりが、静かに重なっていく。





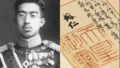
コメント