ニッポンの未来を変える突破口となる可能性を持つ希少金属が小笠原諸島・南鳥島周辺の海に眠っている。電気自動車やIT(情報技術)機器などハイテク製品の素材に広く利用されているレアアースのことだ。少量を加えるだけで素材の性能を大幅に向上させる特性を持つことから「産業のビタミン」とも呼ばれている。
問題は世界のレアアース供給の約7割を中国に依存していることだ。特に高付加価値品に関しては99%近くを中国が加工している。こうした支配的な供給構造が地政学リスクを孕むことは言うまでもない。
最近では米中貿易戦争の激化を受けて、中国政府は7種類のレアアース輸出を制限すると発表した。米国にとってレアアースの供給が滞れば、F35戦闘機や原子力潜水艦など先端兵器の製造が滞ることを意味する。米トランプ政権がウクライナやグリーンランドの権益確保を狙う大きな背景と言ってもよいだろう。
レアアースを巡る地政学的緊張の中で存在感を高めたいのが日本だ。南鳥島周辺の排他的経済水域(EEZ:沿岸国が資源開発や漁業などの権利を専有できる水域)内には、レアアースを豊富に含んだ「レアアース泥」や「マンガンノジュール」(海底に堆積した金属塊)が大量に存在する。世界の需要の数百年分が埋まっているとも言われている。
いよいよ2025年度からは環境に配慮した採掘方法の検証が始まる。開発の実現に前進する成果が出れば、日本は世界のレアアース供給国として第3位に躍進する期待がある。夢の実現時には大きなプロジェクトとなるだけに、活躍が期待される企業への注目度も高まっていきそうだ。
石油資源開発(1662)
■株価(5月1日時点終値)1032円
2015年に「次世代海洋資源調査技術研究組合(J-MARES)」を設立し、政府の戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)に係る調査研究業務を受託したのが同社だ。水深2,000mより浅い位置の海底熱水鉱床の探査に成功するなど、海洋資源開発で得た豊富な実績を持つ。掘削技術や流体制御技術(液体や気体の流れをコントロールする技術)を活用した革新的な採泥システムの開発は、2025年度から始まる環境配慮型の採掘実証に不可欠となろう。
政府系株主の存在により、長期的視点での経営が可能である点も強みだ。国家戦略的な海洋資源開発への継続的な投資が期待できる。さらに財務面では、国内ガス事業が安定的なキャッシュフローを生み出すなど、健全な財務基盤を支える事業構造を持つ。
株価の上値が重い背景には、脱炭素の潮流が中長期的に続くこと、原油・ガス販売量の拡大が短期的に見込めないことなどがある。一方、連結配当性向30%を目安とした株主還元は、長期投資家にとっては大きな魅力だ。レアアース開発が前進することで同社の成長戦略にインパクトが加われば、1倍を大きく下回るPBR(株価純資産倍率)の水準訂正が期待できるだろう。
川崎地質(4673)
■株価(5月1日時点終値)2350円
戦略的な海洋資源開発において中核的な役割が期待されるのが、地質調査のスペシャリストである同社だ。地質調査・解析を主力事業とする建設コンサルタント企業で、特に海底資源調査における豊富な実績と専門技術を有している。
海底探査、港湾・海洋発電設備の建設では、海底地形や底質(海底を構成する表層土)の地質構造を明らかにするデータが不可欠となる。高精度な地質構造の解析技術、3D地質モデリング技術による資源量の評価能力では大きな貢献が期待できそうだ。また、路面陥没を未然に防ぐ地中レーダの探査深度向上にも取り組んでおり、防災関連としても注目できる技術力を持つ。
時価総額は30億円にも満たない同社だが、事業構成比率に占める地質調査業務の割合は高い。特に海洋調査の専門部署を保有し、国土交通省のみならず経済産業省や海上保安庁などの海洋調査業務では多くの実績を持つ。実際に南鳥島でのレアアース開発が前進すれば、収益環境にとっては大きな追い風が吹くことになりそうだ。
古河機械金属(5715)
■株価(5月1日時点終値)2077円
ロックドリル(岩盤掘削)技術と非鉄金属製錬技術は、レアアース泥の採掘から有価金属回収までの一貫プロセス開発における重要な技術となりそうだ。採掘から金属回収までを一貫して行える企業は世界的にも限られており、創業150周年を迎える同社への期待も大きい。

南鳥島周辺の海底には、水深約6,000メートルという極めて過酷な環境下でレアアース泥が存在している。通常の採掘機械では対応できない高水圧と硬い海底地形に対する耐久性が要求される。採泥・揚泥技術(海底の泥を掘削し地上に引き上げる技術)がプロジェクトの核心部分となるだろう。
財務体質の改善も進んでいる。1,600億円以上あった有利子負債を20年以上かけて580億円規模にまで削減し、自己資本比率は50%まで向上した。従来の財務体質強化フェーズに区切りをつけたことで、今後は機械事業を中核に位置づけ、インフラ更新や省人化などに貢献する製品シェアを拡大させる方針だ。資本効率をより高めるコア事業への投資や株主還元強化へ方向転換しており、魅力的な経営指標となりつつある。
三井海洋開発(6269)
■株価(5月1日時点終値)4225円
FPSO(浮体式海洋石油・ガス生産貯蔵積出設備)開発で培った浮体技術と流体処理技術を応用し、2025年度から始まる環境配慮型のレアアース採掘実証試験に向けたシステム設計なども進めている。強みは参入障壁の高い超大水深技術だ。最近では、海底ガスを使ったアンモニア洋上生産の設計承認を日本企業で初めて受けている。先進的な海洋技術をリードできる開発力は、レアアース泥を採取する上でも応用が期待される。
事業環境も良好だ。大深海向け大型FPSOは今後数年は高水準の投資が継続する一方、供給量は制限されているからだ。当面は良好な受注環境が続くことは必至となろう。世界のオフショア開発(海外拠点への開発委託)が活況を続ける中、業績の安定度は一段と高まり、利益率も向上している。
特に営業利益の約6割を占めるO&M(運用・保守)とチャーター事業(主に石油開発会社に対するリース)が好調。中期計画のROE目標を20%という高水準に設定している背景には、キャッシュフロー創出力が大幅に高まったことが大きい。大型投資が予定されていないため、株主還元の拡充余地も高いとみる。
東亜建設工業(1885)
■株価(5月1日時点終値)1370円
港湾・海洋土木に強みを持つ中堅ゼネコン。日本の排他的経済水域(EEZ)内のレアアース採掘実験で実績を持ち、レアアース泥開発コンソーシアムの発起人としても活動をリードしてきた。2024年にはマンガンノジュールを加えた商用化を目指す組織へ発展させている。
同社はレアアース採掘時の海底環境への影響を最小化する工法開発を積極的に推進している。2025年度から始まる環境配慮型の実証試験では、同社が持つ海底工事用の特殊船舶や海底の土砂や堆積物を掘削して取り除く海底浚渫技術を活用した採掘システムが構築される期待がある。
「PBR向上に向けたアクションプラン」を掲げており、更なる増益・株主還元の充実により更なるPBR向上を目指す。主軸となる港湾土木は、国土強靭化政策などで引き続き高水準の政府予算が見込まれ、防衛予算増加にも対応する体制を強化している。予想配当利回りは足元で5%を超えており、配当利回りの高さに着目した投資も有効となるだろう。
レアアース開発は単なる資源確保の問題ではなく、国家の成長戦略と経済安全保障の要となる可能性を秘めている。日本は領海と合わせて世界6位のEEZの面積を確保する離島国家だ。長期目線で大きなリターンをもたらす可能性を持つ資源開発への投資は、持続可能な成長の扉を開いてくれる期待がある。
![]()
宇野沢 茂樹
証券アナリスト
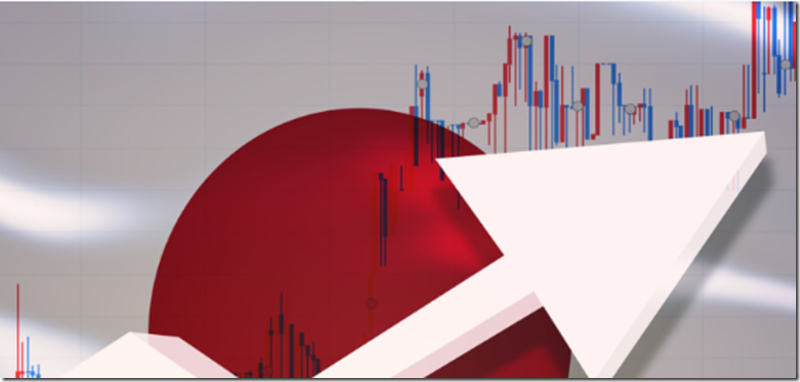




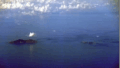
コメント