(画像はイメージです/PIXTA)
「2034年、アメリカの年金制度が破綻する」──そんな衝撃的な予測が2024年5月、アメリカ政府の公式発表により示されました。少子高齢化の影響で年金制度が悲鳴をあげている日本だけでなく、どうやらアメリカでも年金の枯渇が危惧されているようです。カリフォルニア州にオフィスを構える国際税務のプロフェッショナルがアメリカの年金制度の実態を解説します。
2034年、アメリカの年金制度は崩壊するのか
2024年5月、アメリカ政府は、同国の年金制度にあたるSocial Security(社会保障)の信託基金が2034年までに枯渇するとの見通しを発表しました【図表】。
【図表】信託基金の収支推移
背景には、2008年頃から退職を迎えたベビーブーマー世代の増加があります。彼らの大量退職に伴い、年金支出が急増。一方で、日本ほど深刻ではないにせよ、アメリカでも少子化が進行中で、労働人口は減少傾向にあります。さらに平均寿命の延伸により、年金の受給期間が長期化しており、約10年前から支出が収入を上回り始め、基金の赤字が拡大してきました。
2034年=即「破綻」ではない
ウォールストリートジャーナル(WSJ)によれば、「2034年に基金が枯渇=制度の破綻」とは限りません。Social Securityは連邦政府の基幹制度であり、政府そのものが破綻しない限り、制度が完全に消滅することはありません。過去には、Social Securityが黒字であった時期の余剰資金が他の連邦プログラムへ貸し出されていたほど、制度自体には信頼性がありました。
ただし、このまま現在の支給水準を維持すれば、2034年には基金が底をつくため、支給額を最大25%削減する必要があるとの試算もあります。
貯蓄ゼロの高齢者は削減に耐えられるのか
一方で、アメリカの退職者の60%は年金が主な収入源とされており、さらに55~66歳の約半数は老後の貯蓄をまったくしていないとの統計もあります。こうした人々にとって、年金支給額の25%削減は生活の根幹を揺るがす深刻な問題です。
年金が削減されれば、モノの購入を控えることになります。これは全体的な経済活動が停滞させることに繋がり、GDPの鈍化、失業率の上昇、景気後退という悪循環に陥る恐れがあります。これはまさに、現在の日本が直面している状況──24ヵ月連続の実質賃金マイナス、13ヵ月連続の家計消費減、GDPマイナス成長と重なります。
アメリカの年金と財政赤字の関係
現在、Social Securityの支出はアメリカのGDPの約5%に達しており、今後ますます増加が見込まれます。年金問題は個別の問題ではなく、財政赤字と密接に結びついています。
財政赤字を賄うために国債を発行し、発行すればするほど金利が上昇傾向になり、結果として、住宅ローン金利なども上がり、家計をさらに圧迫します。こうしたなか、議会は予算の見直しを迫られ、年金財源の確保のために防衛費や環境対策費などが削減される可能性もあります。赤字国債への慣れがまひ状態にある日本とは対照的に、アメリカではこうした削減が深刻な社会的・政治的課題とみなされます。
日本にとって「教科書」となるか
Social Security制度の大規模な改革が最後に行われたのは1983年で、このときは満額支給開始年齢が65歳から67歳に引き上げられました。今後の対応としては、増税や受給年齢のさらなる引き上げが有力です。バイデン政権下では、富裕層への課税強化が議論され、トランプ氏も含めて「年金支給額の削減には反対」という点では一致しています。
一部では、年金基金の赤字分を他の一般財政予算から補填できるようにする法改正も模索されていますが、議会との合意形成は難航が予想されます。
日本の国会では、年金問題が根本的な議論すら進みません。一方、アメリカでは年金が重大な問題であることは広く認識されているものの、誰も積極的に行動しようとしないというジレンマに陥っています。
残された時間は、年金が底をつく2034年までの10年。しかし、今から行動しなければ間に合わないというのは、アメリカでも日本でも変わりません。
日本政府は、アメリカが今後どのような対応を取るかを注視し、自国の年金制度改革における「教科書」としようとしています。外交・防衛だけでなく、他国の対応を見てからでないと動けないという日本の政策スタイルのままでは、持続可能な制度の確立は難しいのかもしれません。
税理士法人奥村会計事務所 代表
奥村眞吾
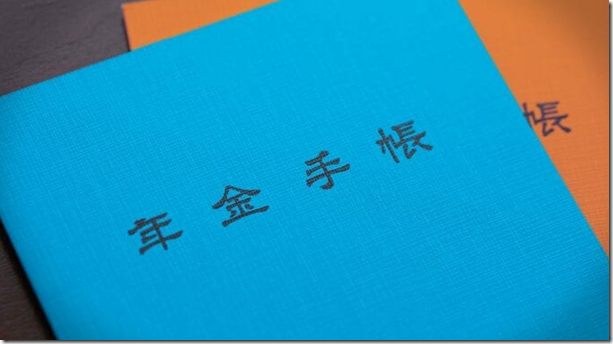

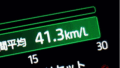

コメント