ウォシュレット(温水洗浄便座)は快適なトイレには欠かせない設備ですが、「自分で取り付けられるのかな?」と不安に思っている方も多いでしょう。
実は、ポイントを押さえればウォシュレットの取り付けはDIYでも可能です。本記事では、初心者の方にもわかりやすいように、取り付け前に確認しておきたい事項や準備する道具、具体的な取り付け手順を丁寧に解説します。
さらに、作業中に注意したい給水管まわりのポイントや、プロの業者に依頼する場合の費用相場・選び方についても紹介します。DIYに挑戦したい方も、業者依頼を検討中の方も、ぜひ最後までご一読ください。
公式サイトを見る
イースマイル に電話相談する0120-091-026
監修者
水道設備業者 トイレ・洗面・キッチン設備主任
伊藤 直樹 (株式会社プログレス)
株式会社プログレス 入社平成24年3月 暮らしの中で必要なレスキューサービスを提供する株式会社プログレスにてトイレ・洗面・キッチン周りの設備主任を担当。水回り業務に8年従事し、累計3000件のトイレ・洗面・キッチン関連のトラブルを解決。多くのお客様に信頼される「トイレ・洗面・キッチン」のスペシャリスト。
ウォシュレットを取り付ける前の確認事項
ウォシュレットをスムーズに取り付けるために、作業開始前にトイレの現状や設置環境を確認しておきましょう。
以下のポイントをチェックすることで、後から「取り付けできない!」といったトラブルを防げます。
ウォシュレットを取り付ける前の確認事項
現在のトイレの状態の確認
まずはお使いのトイレがウォシュレットを取り付け可能なタイプか確認します。
一般的な戸建てやマンションに多い、後方にタンクのある洋式トイレ(組み合わせ便器)であれば基本的に取り付け可能です。
一方、トイレの種類によってはウォシュレット単体の後付けができない場合もあります。
ウォシュレットを後付けできないトイレ
以上のように、ご自宅のトイレがどのタイプか把握し、ウォシュレット後付けが可能かを確認しましょう。
もし「取り付け不可」のタイプに該当する場合、便座だけ交換することはできないため、トイレ本体のリフォームを検討する必要があります。
トイレの形状とウォシュレットの適合
取り付け可能なトイレであっても、便器の形状・サイズがウォシュレット本体と適合するかを確認します。
日本の家庭用洋式便器には大きく分けて大型(エロンゲートサイズ)と標準(レギュラーサイズ)の2種類のサイズがあります。
購入予定または手元のウォシュレットが、ご自宅の便器サイズに合っているか事前にチェックしましょう。
サイズの測り方
便器のサイズは、取り付け穴(便座を固定する穴)中心から便器先端までの長さ(奥行き)で判断します。
一般的に約48cm前後なら「大型」、約46cm以下なら「標準」が目安です。
また、便座取付穴の間隔も製品によって多少異なります(メーカー標準は約14~15cm)が、国内メーカー製であればほとんど問題ありません。
便器の形状
便座の形状には、昔ながらのO型(前丸)とU型(前割れ)という区分もあります。
家庭用の温水洗浄便座はほとんどがリング状に前方が閉じたO型デザインですが、公衆トイレ用など一部にU型も存在します。
ご家庭の便器が特殊な形状(例:楕円形や海外製)でない限り、市販の国内メーカー製ウォシュレットは適合するでしょう。
ただしユニットバス一体型の小型便器や海外製便器の場合、サイズが特殊で合わない可能性があります。この場合も無理に取り付けず、専門業者に相談してください。
適合確認の結果、サイズが合わないウォシュレットを無理に取り付けるとグラつきや隙間が生じて正しく固定できなかったり、使用時に不具合が出る可能性があります。
便器とウォシュレットのサイズは必ず合わせ、適合する製品を選びましょう。
~補足~
ウォシュレット本体(温水洗浄便座)はTOTO、パナソニック、LIXIL(INAX)など各メーカーから様々なモデルが発売されています。基本的な取り付け構造はどのメーカーも共通なので、本記事の手順は幅広い機種に応用できます。機能やサイズは製品によって異なりますが、例えばTOTOの「ウォシュレット」シリーズ、パナソニックの「ビューティ・トワレ」、LIXIL(INAX)の「シャワートイレ」などが代表的です。高機能モデルほど本体サイズが大きい傾向がありますので、お使いの便器に収まるか寸法を確認してから購入しましょう。
配管や電源の確保
ウォシュレットを取り付けるには、水だけでなく電気も必要です。次に、給水配管と電源周りの準備状況を確認します。
トイレの止水栓(給水栓)の位置
ウォシュレット設置には、トイレタンクへ水を供給している止水栓(給水用の水栓)から分岐してウォシュレット本体へも給水する必要があります。
通常、便器近くの壁や床から小さなハンドル式またはマイナス溝付きのネジ式バルブが出ており、これが止水栓です。

位置を確認し、後述する手順で水を止められる状態かチェックしておきましょう。
古い住宅で止水栓が固くて回らない場合や、止水栓自体が無い構造の場合(稀ですが)、DIYでの取り付けは難しくなります。そういった場合は無理をせず業者に相談してください。
電源コンセントの有無
ウォシュレットは電気で温水や便座暖房、脱臭ファンなどを動かすため、トイレ内に電源コンセントが必要です。
通常はアース(接地)付きのコンセントが望ましく、トイレ室内の壁に専用コンセントが設置されています。もしトイレ内にコンセントが無い場合、新たに電源工事を行う必要があります(コンセント増設にはおよそ1万円前後の費用がかかります)。
電源が確保できない状態でのウォシュレット使用はできませんので、事前に対処しましょう。
延長コードの使用は厳禁
トイレ内にコンセントが無いからといって、廊下など別室のコンセントから延長コードを引き込むのは非常に危険です。
湿気の多いトイレで延長コードを使うと、結露や水滴によって感電・漏電や火災の原因になりかねません。
必ずトイレ内に専用コンセントを増設するか、DIYが難しければ電気工事業者に依頼してください。
電源コードの長さ
ウォシュレット本体の電源コードの長さはメーカーによって若干異なります(例:TOTO製は約1m、パナソニック製は約0.95mなど)。
コンセント位置とコード長も確認し、必要であればコードが届く位置に本体を設置するか、コードを固定して足元に余らないように工夫しましょう。
基本的にトイレ左側(便座に座って左手側)にコードが伸びる設計が多いです。
以上の確認事項を踏まえ、トイレの設置環境がウォシュレット取り付けに適しているかを総合的に判断しましょう。
1つでも不安要素がある場合は、無理にDIYを進めず後述の業者依頼も視野に入れてください。準備万端であれば、次はいよいよ取り付けに必要な道具を確認して作業に取りかかりましょう。
取り付けに必要な道具
ウォシュレット取り付けには特殊な工事道具はそれほど多くありませんが、基本的な工具類を事前に揃えておくことが大切です。
以下に必要な道具と、あると便利な道具をリストアップします。
ウォシュレット取り付けに必要な道具
道具が揃ったら、取扱説明書なども手元に置いて、いよいよ取り付け作業を始めます。次章で具体的な手順を一つひとつ見ていきましょう。
ウォシュレット取り付け手順
ここでは、一般的なウォシュレット(温水洗浄便座)をDIYで取り付ける具体的な手順を、順を追って解説します。初めての方でも迷わないように、各ステップでのポイントや注意点もあわせて紹介します。
ウォシュレット取り付け手順
止水栓を閉める
作業を始める前に、まずトイレの給水を止めます。便器横にある止水栓を閉めて、水が出てこない状態にしましょう。
止水栓を閉める作業内容
ポイントとして、 止水栓が古く固着して動かない場合、無理に力をかけると配管を破損する恐れがあります。その際はDIYを中断し、水道業者に相談しましょう。
また止水後はタンクや配管の水が多少こぼれるため、床に雑巾を敷いて作業すると安心です。
便座の取り外し
次に、既存の便座(古い温水洗浄便座や普通便座)を取り外します。新規でウォシュレットを取り付ける場合は、現在付いている便座を外す作業が必要です。
便座取り外し作業内容
取り外しがスムーズにできないときは、無理に力を入れず、ネジやナットが完全に外れているか再確認してください。
サビついて回らない場合は潤滑スプレーを少量吹き付けて数分待つと緩むことがあります。
便座が外れたら、便器の取付穴周りを掃除しておくと良いでしょう(長年の汚れが溜まっていることがあります)。
ベースプレートの設置
ウォシュレット本体を便器に固定するためのベースプレート(取付プレート)を設置します。
ベースプレートはウォシュレット付属の部品で、新しい便座を滑り込ませて固定する土台となるものです。
ベースプレート設置手順
ベースプレートがしっかり取り付けば、後はここに本体をスライドで差し込むだけで固定できるようになります。
分岐金具の設置
続いて分岐金具(分岐水栓)を取り付けます。これは止水栓からウォシュレット用に水を分けるためのT字型の金具で、ウォシュレット本体に付属しています。
既存の給水管を一度外し、この分岐金具を間にかませる形で設置します。
分岐金具の設置手順
ポイントとしては 分岐金具には「上(水タンク側)」「横(ウォシュレットホース側)」など向きの指定がある場合があり、製品によって異なりますが、基本は横方向の分岐口がウォシュレットホース接続用になっています。
向きを確認し、誤って上下逆に取り付けないよう注意してください。
これで止水栓~タンク間に分岐が設けられ、ウォシュレットに水を送る準備ができました。
ウォシュレット本体の設置
いよいよウォシュレット本体を取り付けます。ベースプレートと分岐金具の準備ができていれば、本体はスライド装着とホース接続で完了です。
ウォシュレット取り付け手順
本体取り付け自体は、プレートに差し込むワンタッチ構造になっているため簡単です。ここまでで、水の経路は繋がりましたので、最後に電源を接続して動作確認に移ります。
給水管の接続確認
分岐金具とウォシュレット本体をホースで繋いだら、給水系統の接続は完了です。ここで一度、止水栓を開けて給水し、水漏れがないか確認しましょう。
給水管の接続確認手順
以上で給水管の接続とチェックは終了です。水漏れがないことを必ず確認してから次の電源接続に進みます。
電源コードの接続
ウォシュレット本体と水道の接続が終わったら、最後に電源をつなぎます。安全のため、これまで電源プラグは差さずに作業してきましたが、いよいよ通電して動作確認を行います。
電源コード接続手順
これでウォシュレット本体に電気と水が供給された状態になりました。仕上げにきちんと動作するかテストしてみましょう。
取り付け後の動作確認
最後に、ウォシュレットが正しく動作するか確認します。いきなり人が座って使用する前に、以下のポイントをチェックしましょう。
動作確認手順
以上の確認がすべて問題なければ、ウォシュレットの取り付け作業は完了です。
初めてでも手順通りに進めれば、概ね30分~1時間程度で取り付けられるでしょう。これで快適なウォシュレット生活を始められます。
給水管設置の際の注意点
ウォシュレット取り付けで特に注意したいのが給水管まわりの作業です。水漏れリスクを防ぐため、以下のポイントに気を付けましょう。
給水管まわりの作業の注意点
古いパッキンは交換する
分岐金具を取り付ける際、既存の接続部に入っていた古いゴムパッキンは劣化していることがあります。
必ず新品のパッキン(通常付属)に入れ替えてください。古いパッキンを流用すると後でじわじわ水漏れする原因になります。
ねじ込みはまっすぐ均等に
金具やホースをねじ込むときは斜めに噛んでしまわないように注意します。金属ネジ同士の場合、斜めに力を入れるとネジ山を潰したり締め込みが不十分になります。
手で回せるところまでまっすぐ回し、最後に工具で適度に締め付けましょう。樹脂製ネジの場合は特に丁寧に扱ってください。
締めすぎに注意
水漏れを恐れるあまり、レンチで力任せに締めすぎると、ネジ山を壊したりパッキンをつぶしてしまうことがあります。
「もうこれ以上は動かない」程度で十分です。
一度通水して漏れがあれば、あとから増し締めすればOKですので、初めは程々の力加減にします。
フレキシブル管の活用
もし既存の給水管が真鍮や銅の直管で、分岐金具を取り付けた結果ホースやタンク位置が合わなくなる場合は、フレキシブル管(フレキ管)への交換を検討しましょう。
フレキシブル管とは手で曲げられる蛇腹状の給水管で、長さや形を融通できるためウォシュレット取り付け時に便利です。
例えば、隅付タンク式で止水栓との距離が短い場合など、フレキ管に変えると取り回しが簡単になります。
ウォシュレット購入時に長さ30cm程度のフレキ管が同梱されているケース(パナソニック製など)もあります。必要に応じて活用しましょう。
分岐金具の種類
分岐金具は通常、付属のもので事足りますが、稀に止水栓の型式によっては付属品が合わない場合があります。
日本の一般的な止水栓は「外ネジ式」か「内ネジ式」ですが、極端に古い型や特殊な水栓だと規格が違うこともあります。
その際はメーカーやホームセンターで適合する分岐水栓を取り寄せる必要があります。不安な場合は業者に相談すると確実です。
給水管周りの作業は狭く姿勢もきつい場合があります。焦らず丁寧に行い、「おかしいな?」と思ったら立ち止まって確認する姿勢が大切です。水漏れゼロで安全に使えるよう、細心の注意を払って作業しましょう。
業者を選ぶポイント
ウォシュレットの取り付け作業について解説してきましたが、「自分でやるのはやっぱり不安」「工具もないし失敗したら怖い」という方も多いでしょう。
そんな場合は無理をせずプロの業者に依頼するのも一つの手です。ここでは、業者を選ぶ際のポイントを解説します。
ウォシュレット取り付け業者を選ぶポイント
水道局指定業者
まず注目したいのが「水道局指定工事店」であるかどうかです。水道局指定業者とは、各自治体の水道局から給水装置工事の認可を受けた業者のことを指します。
指定を受けるには国家資格である給水装置工事主任技術者などを有し、一定の基準を満たしている必要があります。簡単に言えば公的なお墨付きがある業者なので、信頼性が高いと言えます。

ウォシュレット取り付けは比較的軽微な工事ですが、水回りの作業である以上、知識と経験のあるプロに任せると安心です。
水道局指定の業者は適切な施工を行い、万一トラブルが起きた際も迅速に対応してくれるでしょう。
また、無資格の便利屋や安請け合いする業者に依頼すると、取り付けミスによる水漏れ事故が起きても補償が受けられない可能性があります。
そうしたリスクを避けるためにも、信頼できる業者選びは重要です。
依頼前に業者のホームページや問い合わせで「水道局指定店か」「資格保有者が施工するか」を確認すると安心材料になります。
かかる費用
業者にウォシュレット取り付けを依頼する場合、費用も気になるポイントです。
一般的な相場として、取り付け作業のみの費用は約7,000~14,000円程度が目安と言われています。また、それ以外にも追加費用が発生するケースも把握しておきましょう。
取り付け作業費以外で掛かる可能性がある費用
依頼前に作業内容を業者と打ち合わせ、見積もりを確認しておきましょう。できれば複数社に問い合わせて料金や対応を比較すると安心です。
あまりに安すぎる場合は作業内容や保証の範囲を、逆に高額な場合は理由(深夜料金や特殊施工の有無など)を確認して納得してから依頼してください。
保証・アフターフォロー
最後に、業者選びで重要なのが施工後の保証やアフターフォローです。
ウォシュレット取り付け自体は短時間で終わりますが、取り付け後に万一不具合や水漏れが発生した場合にどう対応してもらえるかを確認しておきましょう。
信頼できる業者であれば、取り付け作業に対する一定期間の保証を付けてくれることが多いです(例:施工後◯ヶ月以内の水漏れは無償対応など)。
保証内容を書面で渡してくれる業者だとより安心できます。また、施工日からしばらく経ってからでも相談しやすいように、連絡先や受付体制(24時間対応か、土日対応可か等)もチェックポイントです。
さらに、ウォシュレット本体のメーカー保証の手続きについても尋ねてみましょう。通常、温水洗浄便座本体には1年程度のメーカー保証があります。
取り付け業者によっては、保証書の記入やユーザー登録を代行してくれる場合もあります。アフターフォローが手厚い業者だと、故障時のメーカー修理取り次ぎなどもサポートしてくれることがあります。
総じて、「施工して終わり」ではなく取り付け後も親身に対応してくれる業者を選ぶと、長く安心して使い続けることができます。
口コミや評判も参考にしつつ、疑問点は事前に質問してクリアにしておくと良いでしょう。
まとめ
ウォシュレットの取り付け方法について、DIY手順から業者選びのポイントまで詳しく解説してきました。初めてでも手順を追って慎重に作業すれば、ウォシュレットを自分で取り付けることは十分可能です。
事前準備としてトイレの状態確認や必要工具の用意をし、取り付け手順では止水と電源確保に注意しながら進めれば、比較的短時間で設置できるでしょう。
ただし、水回りと電気を扱う作業のため安全最優先で行うことが肝心です。少しでも不安があれば無理をせず、経験豊富なプロの業者に依頼する選択肢もあります。
業者に頼めば確実に取り付けてもらえ、保証やアフターフォローも受けられるので安心感が違います。費用相場や業者選びのポイントも踏まえて、自分に合った方法を選んでください。
快適な温水洗浄便座が使えるようになれば、毎日のトイレ時間がぐっと快適になります。ぜひ本記事を参考に、ウォシュレット取り付けにチャレンジしてみてください。DIYの達成感とともに、快適な暮らしを手に入れましょう!

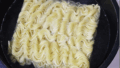

コメント