関税交渉の日米合意は日本の外交的勝利
2025年7月23日、日米間の関税交渉がついに合意に至った。
交渉の焦点は、自動車を中心とする日本製品に対する追加関税であったが、当初アメリカ側が提示していた24%という高率から、最終的には15%へと引き下げられた。これは石破政権にとって外交的な成果であり、日本の製造業にとっても大きな恩恵となる。
この合意の裏には、日本側が提示した巨額の対米投資がある。報道によれば、日本は今後数年間で総額80兆円(約5500億ドル)規模の対米投資を約束した。
対象分野は自動車、半導体、インフラ、金融、エネルギーなど多岐にわたり、トヨタ、ソニー、ソフトバンクなどの大手企業がアメリカ市場での事業拡大に取り組むとされている。
この投資に対して、トランプ大統領はSNS上で「日本が80兆円を投資しても、利益の90%はアメリカが取る」と発言した。この言葉は一見すると挑発的であり、日本側の損失を強調するようにも聞こえる。
だが、実際にはこの発言には国際投資の構造に対する理解が必要であり、それがなければ正確には理解できない。
トヨタが1兆円投資するとカネの流れはどうなる?
理解をわかりやすくするために、仮にトヨタがテキサス州にEV工場を建設するとしよう。
総投資額は1兆円。この資金の使途を分解すると、工場建設費に5000億円、用地取得に2000億円、設備調達に2000億円、残りの1000億円が人件費やインフラ整備に充てられると仮定できる。
まず、工場建設は現地のゼネコンが受注するため、資金はアメリカ企業に流れる。用地取得も同様に、アメリカの土地所有者や州政府に支払われる。設備調達は一部日本企業も関与するが、現地調達が中心となる。人件費は当然ながらアメリカ人労働者に支払われ、法人税もアメリカ政府に納められる。
このように、日本企業が巨額の資金を投じても、その大半はアメリカ経済に還元される構造となっている。これが「利益の90%をアメリカが取る」という意味である。
つまり、この場合であれば「トヨタが得られるリターンとほぼ同じ額をアメリカ側も受け取れる」と解釈できる。
トランプ氏の発言は、投資によって生まれる経済的恩恵の大半がアメリカ側に回るという現実を端的に表現している。
ただし、通常の投資では、リターンの9割を現地が取るというのは簡単ではない。そこで、今回は大きな仕掛けがしてある。
政策金融が“黒子”に徹して日本企業の対米投資を支援
今回の対米投資には、日本政府系金融機関による「政策金融」が活用される。
国際協力銀行(JBIC)、日本貿易保険(NEXI)、産業革新投資機構(JIC)、日本政策金融公庫などが、低利・長期の融資やリスク保証を通じて、日本企業の海外展開を支援する。
これらの金融機関は、民間銀行とは異なり、採算性よりも国策を優先する。利益度外視で資金を供給するため、融資による金利収入や出資による配当といった金融的リターンは期待できない。
結果として、日本の公的資金がアメリカの雇用や設備投資に流れ込み、日本の金融はまるで「黒子」に徹するかのように機能する。
この構造こそが、トランプ氏の「利益の90%」発言の背景にある。日本企業は事業機会を得るが、出資者である政策金融は利益をほぼとらないため、金融的な果実はアメリカ側に集中する。
これは通常の海外投資とは異なる、政策主導型の経済支援である。通常は先進国投資では用いられないが、今回はあえて使うということになる。
政策金融による利益を得るのは主にグローバル展開の大企業
日本側の利益はどこにあるのか
では、日本は一方的に損をしているのか。答えは否である。
今回の交渉によって、日本は自動車関税の引き下げという大きな成果を得た。加えて、円安容認という暗黙の合意もあり、輸出企業にとっては極めて有利な環境が整った。
トヨタやマツダ、日産といった国内自動車メーカーは、円安によって収益を拡大し、株価も上昇している。特にトヨタは、EV市場での競争力を高めるためにアメリカ市場への投資を加速させており、今回の合意はその戦略と合致している。
しかも、日本の自動車会社の場合、鉄鋼は国産のものが使える。資材の多くを日本で調達できれば、アメリカへの輸出分は15%の関税だけで済む。
それに対して、アメリカの自動車会社は、多くの資材、たとえば50%もの関税がかかった輸入鉄鋼を使わざるを得ないため、コスト面で日本よりかなり不利に陥る。
この合意でトヨタ株が急騰したのは、マーケットがその構造を正確に見抜いているからだろう。
ただし、国内経済全体への波及効果は限定的である。利益を得るのは主にグローバル展開している大企業であり、中小企業や地方経済には直接的な恩恵は少ない。この点において、政策金融による対米投資は「選択的利益供与」の側面を持つ。
中国は外資受け入れに際して、技術移転や合弁義務などを課すことで、投資主導権を握っている。短期的な利益よりも長期的な国益を重視する姿勢は、国家戦略として一貫している。
一方、アメリカは自由市場を前提としつつも、政策金融や税制優遇を通じて、外資を自国経済に取り込む仕組みを巧みに構築している。トランプ氏の発言は、その成果を誇示するものであり、交渉の勝者としての立場を強調する意図がある。
そういう意味では、アメリカの利益の取り方は中国よりはるかに健全といえる。
日本は、政策金融という手段を通じて、外交的譲歩と経済的利益のバランスを取った。80兆円という巨額の対米投資は、単なる資金移転ではなく、戦略的な経済連携の一環である。その成果として得られた関税引き下げと円安容認は、短期的には成功と評価できる。
しかし、長期的には「誰が儲けるのか」「誰が負担するのか」という問いが残る。政策金融による投資は、国民の税金や信用を背景にしている以上、その成果と責任は広く共有されるべきであろう。
日本の金融的利益を長期的には削ぐ可能性も
トランプ氏の「利益の90%」という表現は、単なる数字の誇張ではない。実際には、投資によって生まれる経済的利益の大半がアメリカ側に回る構造を指している。これは、工場建設、用地取得、設備調達、雇用、税収といった要素がすべてアメリカ国内で完結するためである。
一方、日本企業は事業機会を得るが、金融的なリターンは限定的である。政策金融によって資金供給が行われるため、融資元である日本政府系金融機関は利益を追求しない。結果として、アメリカ側が得る利益は、通常の投資よりも大きくなる。
この構造は、国際経済における「見えない利益配分」の典型例である。投資された国が、雇用や税収、技術吸収などの形で利益を得る一方、投資元の国は、表面的な収益以外の部分で利益を失っている可能性がある。
今回の日米交渉は、短期的には成功と評価できる。自動車関税の引き下げ、円安容認、トヨタなどの企業の株価上昇といった成果は明確である。
しかし、長期的には、政策金融による対米投資がどのような形で日本経済に還元されるかが問われる。企業単位では利益が見込まれるが、国家としての収支は不透明である。
特に、政策金融による資金供給は、民間の金融機関とは異なり、利益を度外視しているため、国民の税金や信用が直接的に使われる構造となっている。
この点において、今回の合意は「外交的成功」と「経済的譲歩」の両面を持つ。石破政権は、関税引き下げと円安容認という成果を得たが、その代償として、国家主導の巨額投資をアメリカ経済に流すこととなった。これは、短期的には日本企業の競争力を高めるが、長期的には日本の金融的利益を削ぐ可能性もある。
トランプ大統領が「利益の90%はアメリカが取る」と誇示したのは、まさにこの構造を理解しているからである。彼は、アメリカ国内の雇用創出、税収増加、技術吸収といった“見えない利益”を重視しており、それを外交成果として打ち出している。
これは「アメリカの利益」という実質を取りながら、それを「私は日本の利益の9割分をアメリカにもたらした」と、やや誇張も交えて国内でプロパガンダするという、トランプ大統領一流の交渉術であり、自己アピール術でもある。
一方、日本側は、企業の国際展開を支援するという名目で国家資金を投入している。これはグローバル競争において不可欠な戦略であるが、同時に「誰がその利益を享受するのか」という問いを常に伴う。
「投資の見返り」の再設計と国内格差拡大への対応が課題
アメリカにおいてMAGA(アメリカ第一主義)の動きは今後も続いていくと考えられる。したがって、構造的投資は当面継続されると見ておくべきだろう。
そのような動きに対応するためにも、日本政府や日本企業はより明確な「投資の見返り」を設計し直す必要がある。
たとえば、技術提携、現地での日本人雇用、知的財産の保護、サプライチェーンの再構築など、単なる資金供給にとどまらない戦略的な枠組みが求められる。
また、国内の中小企業や地域経済への波及効果を、対米投資からどう生み出すかも考え直す必要がある。
グローバル企業だけが利益を得る構造では、国内の格差が広がる可能性がある。政策金融を活用する以上、その成果は広く国民に還元されるべきである。
さらに、外交交渉においては、経済的譲歩と政治的成果のバランスを慎重に見極める必要がある。今回のように、関税引き下げと円安容認という成果を得るために、巨額の対米投資を行うという構造は、今後の交渉モデルとして再検討されるべきである。
(評論家、翻訳家、千代田区議会議員 白川 司)

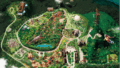

コメント