日本の壁コンセントは、ブタの鼻の2極コンセント
海外のホテルは、世界の旅行者向けに対応するため220V~100Vまで使える特殊なコンセントが多い。でもアメリカの取引先の会議室にあるコンセントは3つ穴が開いた3極タイプだ。またコーヒーショップで一仕事しようと思っても3極タイプ。ヨーロッパも同様で3極タイプのコンセントが多い。
日本と同じように2つ穴の2極タイプは、形や配置こそ違うものの、アジア諸国やヨーロッパでたまに見かけるが、3極タイプに比べると少数派だ。
PC Watch読者なら、国内にいてもコンセントの2極、3極問題に直面することが多々あるだろう。PCやモニターの電源ケーブルだ。
アメリカの壁コンセントは、驚いた顔のような3穴の3極コンセント
インドのコンセントは、丸ピンが3本ある
ベトナムは丸ピンと、日本と同じ平刃が混在しているので変った形になっているが基本3極
トルコでは丸ピンの電源と、3つ目の穴の替わりに上下に出っ張りの付いた3極タイプ
世界は3極が主流なのに日本はなぜ2極が主流なのか?そんな疑問に応えてくれる人を探したが、どこにもいない!コンセントなどの電材で国内第1位、世界第2位のシェアを持つパナソニックに聞いても「分かりかねます」の返答。
いろいろ尋ねてみたところ、ようやく昔々のコンセントから現在までを知り尽くす団体を探し当てた。それが一般社団法人「日本配線システム工業会」だった!
コンセントの始祖は1920(大正9)年にさかのぼる!
「日本配線システム工業会」(以下、JEWAと表記)は、配線システムおよび配線器具に関する調査および研究、情報の収集および提供、普及および啓発、規格の立案および推進などを行なう業界団体だ。
コンセントをはじめ屋内配線機器の啓蒙などを行なっている。1954年(昭和29年)に「日本配線器具工業会」として創立して以来の歴史を持つ
さて街に電線が通るようになったのは1883年(明治15年)。最初はガス燈が電気灯に変っていったが、徐々に会社や家庭にも電灯が普及し電気が個々の建物に届くようになる。
とはいえ1890年(明治23年)頃の電気は電球に明かりを灯すための専用線と言ってもよく、各家庭に引かれた電線には電球ソケットが1個ついているだけだった。1家庭1電球という契約だったのだ。むろんコンセントなどない!
各家庭には1本の電線が引かれ、電灯1個が付けられるようになった。写真はイメージ(松下幸之助記念館)
やがて1915年(大正4年)頃になると、家庭にも扇風機やアイロン、電気あんかなどの家電が入り始める、これらの電源も電球ソケットから取るようになる。大昔のアイロンなどは、電球ソケットに機器から伸びる電線をくるくる回して接続していうたのだ。しかも各家庭に電球ソケットが1個しかなかったので、アイロンをかけたい、扇風機を使いたいという場合は、機器をとっかえひっかえ使うしかなかった。ましてや夜に電灯をつけて扇風機で涼むなんてことができなかったのだ。
コンセント部分に注目。まだコンセントができる前だったので、電球ソケットに差し込んで使っていたアイロン
そんな不便に目をつけたのが現在のパナソニック。当時の松下電器だ。創業者は、今でいう三又ソケットのようなものを開発して売り出した。電球ソケットを2つや3つに分ける、チート(と書いて「便利」と読む)アイテムだ。
1920年(大正9年)「二灯用クラスター」。今で言う二股ソケットで、1つの電球ソケットで2つの家電を同時に使えるようになった
1918年(大正7年)「二灯用差し込みプラグ」。電球ソケットの横に小さい歯が付いた部品を差し込むと、ここから電気が取れるアダプタ。形状は現在のコンセントに近い。これはちょっと工作が必要なのでマニア向けで、後に「二灯用クラスター」が発売された
やがて電球ソケットが使いにくいということで、1920年(大正9年)(と言われている)に今のような差し込み式コンセントが登場する。ただ明確に書面で示されたのは日本電気工藝委員会が制定した「挿込型接續器標準仕様書」に掲載されている「A型10A用」で示されたものとされている。
図面を見ると今と同じ縦型の刃と、横型の刃の2つの差し込みがあり、横型の「C1」は廃止方向との注意書きがある。つまりこの時点では2つのタイプがあったものとも思われる(昭和11年1月発行「照明學會雑誌」より、JEWA提供)
プラグの図面。一般家庭用の10A(1,000W)までがA型。B型 は工場などの業務向けで20A(2,000W)まで対応。平刃が横になったC型も見られる
日本でしか使えない和製英語「コンセント」の由来は、このとき東京電灯(現東京電力)が、工事規定で壁の差し込みを「コンセント」、機器側の差し込みを「プラグ」と言い始めたためだ。海外では「アウトレット」と言わないと通じない。
余談だが、接続部分は金属だか、安全に使うため電気が通らないカバーをしなければならない。当時はプラスチックなどなかったので、コンセントは瀬戸物(陶磁器)でできていた。そこで、愛知県の瀬戸市や常滑市(INAXで有名)、佐賀県の有田(有田焼)などで、電材機器が作られ、今でも地域産業となっている。
【9時20分訂正】記事初出時、常滑はTOTOと記述しておりましたが、正しくはINAXでした。お詫びして訂正します。
昭和初期にアメリカは安全性を考慮した3極式に転換
1930年(昭和5年)には電気冷蔵庫や電気洗濯機、翌年には蓄音機や掃除機、ミシンなども発売される。まだ一般層には普及しない高価な製品だったが、コンセントは家電の普及とともに広がりを見せる。
さてエジソンやテスラといった天才の活躍で電化の進むアメリカは、当初日本と同じ形の2つの平刃式のコンセントを使っていた。しかし1940年(昭和15年)にアメリカの電気工事既定で「アースピン付きコンセント」が義務化される。俗に「3極」や「3P(ピン)」コンセントと呼ばれるものだ。電気工事士でもあまり使わないが、正式名称は「接地極付きコンセント」(電材の発注で見かける程度)。
アメリカは戦前から安全性を考慮して3極のコンセント義務化した
海外製のPCなどでよく見かける3極のコンセント。丸いピンがアースになっている
従来までの2つの平刃は電源用。この2本の電線で発電所からコンセントまで電気が運ばれてくる(送配電)。追加されたもう1本は、平刃ではなく丸いピンとなっていて、家電を感電せず安全に使えるようにする「アース」用だ。英語で書くと「Earth」で地球や大地といった意味で、家電と大地(地中)をつなぐことで、その電線を「アース線」という。
水回りで使う機器には必ず付いているアース線。業務用の冷水器だったがアースはどこにもつながっていなかった(笑)
洗濯機や電子レンジ、冷蔵庫など水回りで使う家電に必ずついている「緑色の電線」、アレがアース線。
日本だと緑の電線とプラグのついた電源コードの2本に分かれているが、アメリカでは緑のアース線がまとめられて3本セットで1本の電線になっている。その先についているプラグが3極プラグというわけ。
これならアースが必要な機器は、丸いピンにアースの電線が接続されているので、コンセントに差し込むだけで電源もアースも接続できる。しかも3本の刃が差さるので接続も安定して抜けにくいという点もある。
ちなみに1999年には台湾でも「アースピン付きコンセント」が義務化されている。実はアース線の接続は、家電を安全に使う上で重要なのだが、日本ではゆるゆるで重要視されていない。そのため特定機器を接続するコンセントのみアース付きの「アースピン付きコンセント」が義務化されておらず、諸外国のように「家じゅうすべてのコンセント」の義務化までは進んでいないのだ。
アメリカと同じ3極式が3年前に義務化!でもネジ止めも併用!?
世界もアメリカに同調しヨーロッパでも「アースピン付きコンセント」が義務化され、コンセントにプラグを差し込むだけでアースの接続もOK。家電の安全対策もバッチリだ。
JEWAの担当によれば、日本でアースピンを備えたコンセントが「義務化」ではなく「勧告」されたのは2000年になってからのことだという。なんと!つい最近ですら、次のいずれかを使って「できるだけアースしてね」というゆるさなのだ。
- アースピン付きコンセント(2つの平刃+アースピン)
- ネジ止め式アース端子の付いたアースピン付きコンセント
- ネジ止め式アース端子の付いた普通のコンセント

1)1つのコンセントに対して1本のアースピンが付いたコンセント
2)1つのコンセントに対して1本のアースピンが付いたコンセント。さらにネジ止め式の従来型アース端子が付いているコンセント
3)アースピンがない従来型コンセント。ただしネジ止め式の従来型アース端子が付いている
より具体的なコンセントの形状が示されたと思いきや、「アースピン付きコンセント」の設置場所は一部限定になる。2005年の規定では、トイレやキッチンなどに「アースピン付きコンセント」にした方がいいよという「勧告」になる。さらに急に「アースピン付きコンセント」にすると、過去に発売されたアース線式の家電が対応できないため、「アースピン付きコンセント(ただし「ネジ止め式アース端子」付きが望ましい)というカッコ書きまで付くもどかしい「勧告」だ。
「義務化」として明文化されたのは、3年前の2022年の改定。先の特定場所のコンセントが「アースピン付きコンセント」(ただし「ネジ止め式アース端子」付きが望ましい)となった。でもやっぱりカッコ書きは取れなかった。
こうして2022年以降の新築物件では、トイレや洗濯機、キッチンまわりの家電のコンセントが3穴の「アースピン付きコンセント」になっている。ただ昔ながらの「ネジ止め式アース端子」付きが望ましいという一文が残っているので、機器側が旧住宅との互換性のために積極的にアースを備えた3極のコンセントプラグを採用していない。相変わらず緑のアース線をネジ止めしているというのが現状だ。
少し進歩が見られたのは、特定場所以外の一般的なコンセントも、「アースピン付きコンセント」をお薦めしますの「推奨」から、ワンランク上の「勧告」になり「アースピン付きコンセント」が良いので将来的に切り替えていきましょう!という感じに切り替わっている。
日本がアースにゆるゆるな意外なワケ
世界の多くは3極のアースピン付きコンセントを採用しているのに、なぜ日本だけ時代遅れの2極式のコンセントを使い続けているの不思議だ。何かの利権か?
その答えをJEWAの担当がズバリ答えてくれたが、日本製の家電が高性能で安全なゆえの意外な原因だった。
理由1:そもそも日本の家電は漏電しにくく安全
アース線の考え方は「もし家電が故障して、家電本体に電気が漏電しても、それに触った人が感電しないようにアースする」というものだ。アース線が未接続だと家電のケースなどに漏電した電気が人の手から足に抜け、地面に流れるので人が感電してしまう。
世界の家電は、PCのようにケースが金属でできている場合が多いが、日本の家電をよく見ると分かる通り、金属が露出している部分はごくわずか。手で触れる大部分は樹脂製になっている。樹脂が電気を流さないため、日本製の家電は人ほとんど感電しない。しかも電線がシッカリ接続され、漏電するすら稀。
高い安全性が担保されているので、アースの重要性が薄まってしまっている。高性能ゆえの問題なのだ。
理由2:家電側が3極プラグを採用すると一般的な2極のコンセントに差し込めない
よくあるのがPC本体やモニターの電源をコンセントに差し込もう思ったら3極のプラグで刺さらない!という経験だ。そのため3極を3極に変換するアダプタを使ったり、テーブルタップの横に差し込んでアースピンをむき出しにして使っているだろう。
2022年に義務化されたばかりのアースピン付きのコンセントなので、電子レンジもエアコンも、冷蔵庫も洗濯機も3極プラグを使うと、かえって顧客が面倒になる。だから家電メーカーは、3極プラグの採用は時期尚早としている。
しかもアースピン付きコンセントには、ネジ止め式アース端子が付いている場合が多く、従来のままの電源コードとアース線に分かれていても何ら問題がない。
理由3:どうしようもない数まで増加して対応しきれない
JEWAは安全のためにすべてのコンセントをアースピン付きコンセントにリプレースしようとがんばっている。しかし経産省の見込みでは「もう無理!」と完全あきらめモード。
既築の住宅数が5千万戸、新築住宅が毎年100万戸と言われており、すべてのコンセントを2極→3極コンセントに置き換えるには、単純計算でも50年かかると試算しているのだ。
戦前に3極コンセントに舵を切ったアメリカだから、現在ほとんどアースピン付きコンセントに切り替わっているのだ。日本はもう手遅れ。
宙ぶらりんのアース線はない?もう一度見直して安全点検
アメリカのコンセントは3穴、日本は世界でも珍しい2穴コンセントを使っている理由がお分かりだろう。日本の製品は、高品質で安全とはいえ、水回りで使う家電は安全のためにアースは必要不可欠。そこでおざなりになりがちのアースについて、専門家にいろいろ質問してみた。
Q:機器が問題なく使えているのでアースは接続していません。接続しないとダメですか?
A:アースは機器に問題が発生したとき、あなたが感電しないように予防するものです。緑のアース線は、必ずアース端子に接続してください。
アースが付いている機器は。必ずアース端子に接続する
Q:「アースは電線を地面に埋めているだけ」と聞きました。それだけで感電事故の防止になるのですか?
A:電気を通さないように思える地面ですが、実は非常に電気を通しやすい物質(特に泥)です。そのため漏電している機器がアースで地中につながっていれば、漏電した電気は地中に流れ、人が感電することはありません。また漏電を検知して、家庭の分電盤にある漏電遮断器が電気を強制的に遮断するので安全です。
アースが接続されていれば、機器に漏電していても人に感電することはない。アースがないと機器に振れた手から足に電気が流れ感電する(出典:パナソニックホームページ)
Q:アースが接続されていれば、漏電している機器に触れても感電しないのですか?
A:落雷の感電から人や機器を守る「避雷針」があります。これは雷が落ちやすくするために、わざと高いところ棒状の金属を空に突き出しています。避雷針の反対側はアースと同じで地面に埋められています。こうすることで、もし避雷針に落雷してもすべての電気が地面に流れるので、建物や家電、住んでいる人に落雷の電気が流れることなく安全になります。
また地面に人が立っていても、人よりも地面の方が断然に電気が流れやすいので、地面から人に向って電気が流れることはありません。つまり近所で漏電していても、地面から感電することはありません。
Q:100Vのコンセントから電源を取っているPCですが、200Vのエアコンについているアース端子に接続しても大丈夫ですか?
A:同一の住宅(分電盤が同じ)なら、100V、200Vどちらのアース端子に接続しても問題ありません。2世帯住宅などで分電盤が分かれている場合は、分電盤をまたぐようなアースの接続はできません。
Q:1つのアース端子に、冷蔵庫と電子レンジと食洗器のように複数機器のアースを接続しても大丈夫ですか?
A:問題ありません。
Q:ホームセンターに「アース棒」が売っていました。これを購入して自分でアース端子を増設できますか?
A:アース工事には、知識と測定、必要に応じた施工が必要なので、電気工事士の資格がなければ工事はできません。
ホームセンターなどでアースを増設する「アース棒」が入手可能。しかし接地に知識が必要で、接地後には測定。測定値を満たしていない場合は施工が必要なので素人工事は禁止
Q:近くにアース端子がなかったので、金属の水道管やガス管に接続しても大丈夫ですか?
A:どちらもダメです。水道管は見えている部分は鉄ですが、地中は電気を通さなない塩化ビニルのパイプです。ガス管は爆発の恐れがあるので、絶対に接続しないでください。
Q:最近建てた住宅なので、アース線をネジ止めする端子がなく、3極のアースピン付きコンセントになってます。アース線は丸いピンの穴に差し込めばいいでしょうか?
A:ホームセンターの電材売り場などで、変換コネクタが入手できます。機器のプラグを変換コネクタに差し込んで、緑のアース線を変換プラグのアースピンにネジ止めします。これで電源コードとアース線が分かれている家電でも、3極のプラグに変換できます。なおこの工事は免許を必要としませんが、慣れない方は電気に詳しい人に相談するといいでしょう。
電源コードとアース線が分かれている機器は、写真のような変換コネクタ(パナソニック製「アースターミナル付変換アダプタ」(WH2881P))などを利用して、アースピンの付いた3極プラグに変換できる
Q:購入したPCとモニターのコンセントが3極のプラグでコンセントに差せません。
A:ホームセンターの電材売り場や家電量販店のパソコンコーナーで、「3P→2P電源変換コネクタ」などを購入して、3極プラグを変換コネクタに差し込んでください。これで普通のコンセントに差し込めます。なお変換プラグはコンセントから外れやすいので、足が引っ掛からないような場所に配線しましょう。
機器が3極電源プラグでコンセントに差さらない場合は、写真のような変換コネクタ(パナソニック製「接地15Aアダプタ」(WH2891P))などを利用して、2極のコンセントをアース線に分離でき
- 日本配線システム工業会のホームページ






















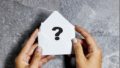
コメント