天孫降臨の神話が伝わる宮崎、鹿児島県境の霧島連山・高千穂峰(1573メートル)の山頂で、祖父、父の3代約100年にわたり、山小屋(現・避難小屋)を管理してきた宮崎県高原町の石橋晴生さん(75)がその役を終え、引退した。管理を引き継いだ町は今春、石橋さんに感謝状を贈った。(木村歩)
高千穂峰山頂で多くの登山客に利用されてきた小屋=宮崎県高原町提供
高千穂峰は神話の主人公でもあるニニギノミコトが降臨したとの伝説があり、山頂に「 天逆鉾あまのさかほこ 」が突き立てられている。ツツジの一種のミヤマキリシマの名所としても知られ、登山がブームだった1969年に年間20万人が訪れるなど、人気を集めてきた。
高千穂峰の地図
町や石橋さんによると、山小屋は24年頃、石橋さんの祖父・国次さんが山頂付近に開設した。当初は宿泊施設として利用され、国次さんが約40年間、石橋さんの父・利幸さんが約30年間にわたって、遭難者らの救助などにあたる山の案内人「 峰守みねもり 」として管理。石橋さんは95年に3代目として引き継いだ。
![image_thumb[5] image_thumb[5]](https://hukiage.com/wp-content/uploads/2025/07/image_thumb5_thumb.png)
大きな荷物を背負い、山頂に向かう石橋さん(2000年頃)=本人提供
食材や灯油といった荷物を背負い、多い日は山頂までを1日3往復した。高原町側の登山道を使うと、上りは約3時間かかった。荷物の重さは40キロ前後になることもあり、「背骨がしなる感じだった」と振り返る。一方、身軽になる下りは「走って1時間30分ほどで下山した。慣れだね」と笑う。道に迷っていた遭難者を見つけ、無事に下山させたこともあった。
2000年頃に宿泊事業を取りやめ、山小屋が登山客が風雨を避ける避難小屋となった後も麓の高原町にある自宅から通い、管理を続けてきた。ただ、年齢を重ね、近年は頻繁な往来は困難に。相談を受けた町が昨年12月から管理を引き継いだ。
感謝状を受けた式典で「峰守」としての思い出などを語る石橋さん(4月、宮崎県高原町で)
峰守としての活動をたたえられ、4月中旬に高妻経信町長から感謝状を受け取った石橋さん。「さみしさはあるが、『やっと荷が下りた』という思いもある。登山者のための小屋として活用してほしい」と述べた。今後は月1回程度、一登山者として現地を訪れ、見守り続けていくという。
町は登山基地として整備している麓のレストハウスに、山小屋で使用されていたランタンや風速計、写真など約40点を展示しており、今後も1世紀にわたる石橋家の歴史を伝えていく。高妻町長は「石橋家の高千穂峰を愛する思いを受け止め、責任を持って引き継ぎます」と語った。

![image_thumb[1] image_thumb[1]](https://hukiage.com/wp-content/uploads/2025/07/image_thumb1_thumb-2.png)
![image_thumb[3] image_thumb[3]](https://hukiage.com/wp-content/uploads/2025/07/image_thumb3_thumb-1.png)
![image_thumb[7] image_thumb[7]](https://hukiage.com/wp-content/uploads/2025/07/image_thumb7_thumb.png)

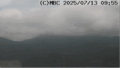
コメント