最新の研究により、地球温暖化は異常気象に明確に影響を与えていることがわかった。元気象庁長官の長谷川氏によると、もはやフェイクかどうかを議論するという次元ではなく、いかにそのリスクを抑えていくかの段階だという。
地球温暖化の影響で日本の雨量は増え、台風の勢いは増し、猛暑日の日数は増えていく。最新の情報と、予測される今後のシナリオを書籍『天気予報はなぜ当たるようになったのか』より一部抜粋・再構成して紹介する。
猛暑は地球温暖化のせいなのか
たとえば、2024年の日本の猛暑は地球温暖化のせいなのでしょうか。災害をもたらす大雨は、地球温暖化のせいなのでしょうか。その大前提として、人間活動による温室効果ガスの増加によって地球が温暖化していることについては、2021年のIPCCの報告により、疑いがないことが科学的に確かめられました。では、2024年の日本の猛暑という個別の出来事についてはどうでしょうか。
毎年の気温は、プラスマイナス1度くらいの幅ででこぼこしていて、地球温暖化のせいだけ、ともいえない感じがします。気象庁は、異常気象があったときに、その要因やメカニズムを分析するため、専門家からなる「異常気象分析検討会」を開いています。
この検討会で分析したところ、2024年の猛暑については、上空のジェット気流が日本付近で、いつもの年より北にずれていたこと、太平洋高気圧が強く、西日本に張り出していたことなどが要因であることがわかりました。つまり、単純に温暖化して暑くなったというのではなく、この年特有の気圧配置が関係していたわけです。
こう書くと、じゃあ地球温暖化は関係ないと言うのか、という声が聞こえてきそうです。少し前まで、この手の質問に答えるのは難しく、地球温暖化の影響の可能性も考えられる、というようなあいまいな答えをするしかありませんでした。
ところが、最近になって、もっと明確な答えができるようになってきたのです。
コンピューターの進歩により、気候のシミュレーションが、このような疑問に答えるための非常に強力な武器になってきました。そのシミュレーション技術を使って分析をしたところ、2024年の夏のような高温は、温暖化した現状であっても10年に1回程度の割合でしか起きないようなまれな現象ではあるけれど、温暖化がなければまずありえないようなものであることが示されました。
このようにシミュレーション技術を使って、ひとつひとつの異常気象などに、どの程度地球温暖化が寄与したかを調べることを「イベント・アトリビューション」とよんでいます。最近、気象研究所をはじめ、多くの研究者がこの研究に取り組んでいます。
雨についても同じように、このイベント・アトリビューションの手法を使って温暖化の影響を明確に示すことができるようになってきました。たとえば、2019年に東日本台風による大雨が日本に大きな被害をもたらしましたが、その雨量は、温暖化によって約1割増えたと考えられています。
2024年の9月には、その年の1月1日に地震の被害があった能登半島で、今度は集中豪雨による災害が発生しました。このときの大雨についてもイベント・アトリビューションで調べてみると、温暖化によって総雨量が約15パーセント増えていたとされています。
台風や集中豪雨は地球温暖化がなくても発生するものですが、その雨量が温暖化によって増えているということです。
地球温暖化やその影響は、もはや将来の懸念ではなく現在の問題であり、本当かフェイクかなどと論じている場合ではないのです。
将来はどうなるのか
そうなると、将来の気候のことがますます心配になります。地球温暖化が進んだときにどのような気候になるのか、気候モデルを使った研究が進められ、その成果がIPCCの評価報告書に順次まとめられています。
最新の第6次評価報告書では、温室効果ガスの排出について5つの典型的なシナリオを設定し、それぞれのシナリオでどのような気候になるのかを予測しています。
それによれば、排出量が中程度以上の場合には今世紀中に地球平均の気温が19世紀末に比べて2度以上高くなる可能性が非常に高く、最も排出量が少なくなる場合であっても、1・5度をいったんは超える可能性があるとしています。
また、温暖化が進むと極端な高温、大雨、干ばつなどの頻度や強度が増すとしています。
最近は、それぞれの地域の気温や雨の降り方などがどうなるかを調べるため、地域気候モデルを使った研究も注目されており、IPCCの第6次評価報告書でも多くのページ数を割いて、地域の気候の予測についてまとめています。
日本の気候については、文部科学省と気象庁が協力して、これまでの気候の変化と合わせて、地域気候モデルを使った気候予測研究の成果をとりまとめた「日本の気候変動2025」を2025年3月に公表しました。2020年に公表された「日本の気候変動2020」の内容をさらに新しくしたものです。
「日本の気候変動2025」に記されている予測の内容をここで詳しく述べることはしませんが、ひと言で言えば、日本においても、温暖化とともに気温が上がり、災害をもたらすような激しい現象の頻度や強度が増し、その程度は、温暖化が進めば進むほど激しくなると予測されています。
たとえば、追加的な温暖化対策が取られず、世界の平均気温が工業化以前より4度高くなるシナリオでは、20世紀末に比べ、日本での平均的な猛暑日の年間日数は約18日増え、1時間に50ミリ以上の大雨の年間発生回数が約3・0倍に増え、海面が約68センチ上昇するなどとしています。また、温暖化とともに、台風の強度も増すと予測されています。

雨水の排水設備や河川の設備などは、何年に1回の大雨に耐えられるように、といった考え方で設計されることが多いです。長期間の雨量のデータを分析すると、たとえば、ある場所で100年に1回しか観測されないような日降水量は何ミリかということがわかるので、それを基準に施設の設計をするのです。
100年に1回という大雨に当たる日降水量は、4度上昇シナリオでは、工業化以前に比べ、全国平均で約32パーセント増えると予測されています。逆に、工業化以前に100年に1回であった極端な大雨(日降水量)は、21世紀末にはもっと頻繁に起こるようになり、100年に約5・3回の発生頻度になると予測されています。排水設備の設計などでは、こうした地球温暖化の影響を考えに入れなければならなくなっているのです。
温暖化をなるべく抑える
このような地球温暖化やその影響から暮らしや産業などを守るため、さまざまな地球温暖化対策が取られています。そのうち、二酸化炭素の排出を減らすなどして、なるべく温暖化が進まないようにする取り組みは緩和策とよばれています。また、温暖化した環境に暮らしや産業を合わせる取り組みは、適応策とよばれていて、どちらも重要な対策であり、相互に関係しています。
地球温暖化の緩和策の実施は容易なことではありません。それは、多くの人々の暮らしに直接影響し、産業の根幹に関わり、しかもお金や負担がかかるからです。
こまめに電気を消すくらいはまだいいのですが、二酸化炭素が出るから車に乗るなと言われると生活が不便になります。だからといって燃費のいいハイブリッド車などに買い替えるとお金がかかります。
企業にとっても、温暖化対策のために効率化や設備投資などを強いられることになります。さらに、二酸化炭素の問題は電力のあり方や価格とも直結していて、家計や産業に大きく影響を及ぼします。
最近では、温暖化を少しでも食い止めなければという人々の意識が共有されるようになり、対策のハードルも下がってきたと思います。また、たとえば車の燃費が良くなればガソリン代が安くなるといった効果もあり、対策を積極的に進める人も多くなりました。
企業にとっても、温暖化対策に後ろ向きでいると、投資家や顧客から背を向けられかねない時代になり、積極的に対策を講じるところが多くなってきています。
脱炭素の動きを好機ととらえた再生可能エネルギーや電気自動車・ハイブリッド車をはじめとするエネルギー効率のいい製品といったビジネスが進み、それらを目指した技術開発も盛んに行われるようになってきました。政府の補助金なども、こうした取り組みを後押ししています。

このように、経済的にも見合い、技術的にも到達可能なレベルまでの緩和策は、今後も進んでいきそうです。しかし、工業化以前に比べて1・5〜2度以内の気温上昇に抑えるという、世界が目指している目標を達成するには、今、各国が見込んでいる対策では不十分です。
写真はすべてイメージです 写真/Shutterstock
天気予報はなぜ当たるようになったのか
長谷川 直之
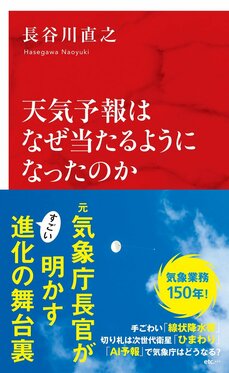
2025年6月6日発売
1,012円(税込)
新書判/256ページ
ISBN: 978-4-7976-8158-1
私たちの生活に欠かせない「天気予報」はどのように作られているのか?
気象の予測技術開発、国際協力業務、「線状降水帯」の情報発表などに取り組んできた
元気象庁長官の著者が、その舞台裏をわかりやすく解説する!
身近だけれど、実は知らないことだらけの「天気予報」のしくみがわかる!
2025年は、日本の気象業務のはじまりから150年の節目の年!
【内容紹介】
○「天気予報」の精度は上がり続けている! そのワケは?
○「降水短時間予報」は、ふたつのいいとこ取りの技術を使っている
○正しく知る「警戒レベル」と「防災気象情報」の意味
○手ごわい「線状降水帯」。予測の切り札は次世代衛星「ひまわり」
○「天気に国境はない」。気象データは無料・無制約で国際交換
○地球温暖化は本当かフェイクかと論じている場合ではない
○「AI予報」で気象庁はどうなる?
など

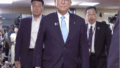
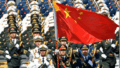
コメント