土地や建物の取引において、必ず必要となる書類の一つが「登記簿謄本」です。しかし、普段あまり馴染みのない言葉のため、登記簿謄本とは何か、どのような時に必要なのか、取得方法はどうすれば良いのかなど、疑問を抱いている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、登記簿謄本に関する疑問を徹底解説します。登記簿謄本とは何か、どのような時に必要なのか、取得方法や費用、登記簿謄本の内容の見方など、基礎知識を分かりやすくまとめました。不動産取引を控えている方、登記簿謄本について詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
登記簿謄本と登記事項証明書は内容は同じ
不動産における登記簿謄本とは、法務局に備え付けられている登記簿の内容を証明した書類のことです。コンピューター処理した場合は登記事項証明書と呼ばれ、不動産の権利関係を確認するために必要な重要な書類です。
登記簿には、所有者や抵当権などの権利関係、土地や建物の面積や形状などの情報が記載されています。登記簿謄本は、これらの情報を証明するもので、不動産取引や相続、裁判など様々な場面で必要となります。
なお、企業の法人情報を登記する登記簿謄本は、土地や建物の登記簿謄本とは異なりますのでご注意ください。
登記簿謄本が必要になるのはどんな時?
登記簿謄本は、土地や建物の権利関係を証明する重要な書類です。様々な場面で必要となる書類ですが、具体的にはどのような時に必要になるのでしょうか?
登記簿謄本が必要となる主な場面には、不動産の売買、不動産の抵当権設定、相続手続き、裁判手続き、行政手続きなどがあります。
上記以外にも、様々な場面で登記簿謄本が必要となります。登記簿謄本は、土地や建物の権利関係を証明する重要な書類ですので、必要となる場面を理解しておくことが大切です。
登記簿謄本には4種類ある
不動産における主な登記簿謄本は、4種類あります。
1. 全部事項証明書: 土地の所有者、建物の種類や所有者、抵当権などの権利関係など、登記されている全ての事項を証明するものです。
2. 現在事項証明書: 現在有効な登記事項のみを証明するものです。過去の不動産所有者や抵当権の記録は記載されていません。
3. 一部事項証明書: 登記簿の記載されている一部の事項のみを証明するものです。分譲マンションの一室だけの登記情報を確認したいときなどに用います。
4. 閉鎖事項証明書: 過去に取り壊された建物の情報や合筆された土地の情報など、閉鎖された登記簿の情報が記載された証明書です。
必要な情報に応じて、4種類のうちいずれかの証明書を取得することができます。
登記簿謄本の取得方法や取得場所、費用について
土地や建物の権利関係を証明する登記簿謄本は、法務局で取得することができます。それ以外にもいくつか取得方法があります。また、閲覧のみの場合は、登記所で登記簿を参照することができます。それぞれの方法や費用について見ていきましょう。
法務局窓口での取得方法
土地・建物の登記簿謄本を取得したい場合、最寄りの登記所にて取得することができます。
身分証や認印などは不要で、手数料が必用です。手数料は1通あたり600円の収入印紙が必要となり、収入印紙は法務局内で購入できます。手数料は、現金で支払う必要があります。枚数が50枚を超えるごとに100円加算されます。
登記事項証明書交付申請書に必要事項を記入し、法務局窓口に提出します。登記簿謄本を請求する土地や建物の地番や家屋番号などが必要になるため、事前に正確に確認しておきましょう。
申請書に不備がなければ、10~15分程度で登記簿謄本を窓口で交付されます。
ただし、法務局によって、営業時間や手数料が異なる場合があるため、事前に確認することをおすすめします。
オンラインでの取得方法
登記簿謄本は、法務局窓口だけでなく、オンラインでも取得することができます。オンラインでの取得方法は、以下の通りです。
1. 申請者情報を登録する
2. 作成した申請書を送信する
3. 手数料を電子納付する
4. 登記簿謄本を法務局の窓口で受け取るか、郵送してもらう
登記・供託オンライン申請システムを利用すると、法務局の窓口で取得するよりも手数料が安く、手数料の納付がインターネットバンキング・モバイルバンキング又は電子納付対応のATMからできることがメリットです。郵送受け取りの場合は500円、窓口まで出向いて受け取る場合は480円です。
また、法務局が遠方で行くことが難しい場合は、オンラインで取得し、郵送してもらうことが可能なので便利です。
郵送での取得方法
不動産の登記簿謄本は郵送で取得することも可能です。その際の手順は、以下の通りです。
記簿謄本の種類や申請する法務局によって収入印紙の金額が異なる場合もあるので注意が必要です。一般的に、郵送での申請は1通あたり600円の収入印紙が必要になります。申請から交付まで時間がかかる可能性があるため、余裕を持って申請するようにしましょう。
閲覧のみの方法

登記簿謄本は、法務局の窓口やオンラインで取得できますが、閲覧のみも可能です。登記簿謄本を閲覧するには、最寄りの法務局の窓口で450円で閲覧するか、民事法務協会が運営する登記情報提供サービスを利用する方法があります。
ただし、登記情報提供サービスからPDFでダウンロードすることは可能ですが、コピーを取っても証明文や公印などがないので公的な書類としては認められません。また、有料なことにご注意ください。全部事項の場合331円です。
閲覧のみの方法が適しているのは、登記簿謄本に記載されている情報を確認するだけで十分な場合です。
登記簿謄本を取得する時の注意点
登記簿謄本は、不動産の権利関係や状況を確認するために必要な書類です。取得する際にはいくつかの注意点がありますので、事前に確認しておきましょう。
登記簿謄本を取得する際には、これらの注意点に気を付けてください。
登記簿謄本の交付申請書の書き方のポイント
登記簿謄本を取得するためには、法務局に交付申請書を提出する必要があります。正式には、「登記事項証明書 登記簿謄本・抄本 交付申請書」と言います。交付申請書は、法務局の窓口に設置してあるため、その場で入手し、記載することが可能です。また、郵送で請求することも可能です。
交付申請書には、以下の項目を記入する必要があります。
交付申請書を記入する際には、登記簿謄本を取得したい不動産の所在地を正確に記入する必要があるため注意しましょう。
交付申請書を記入したら、必要な収入印紙を貼付し、法務局の窓口に提出するか、郵送します。
登記簿謄本の内容の見方
登記簿謄本は、表題部、権利部(甲区)、権利部(乙区)、共同担保目録の4つの部分に分かれています。これらの情報は、不動産取引や相続などの際に必要となる重要な情報です。登記簿謄本を取得して、これらの内容をしっかりと確認しましょう。
表題部の内容
登記簿謄本の表題部は、登記簿謄本の最初に記載されている部分です。表題部には、土地や建物の所在地や面積などの情報が記載されています。たとえば土地の場合は、以下の項目が記載されています。
さらに、建物の場合は、上記に加えて以下の項目が記載されています。
マンションの場合は、マンション全体・土地と専有部分(各部屋)の情報が分かれて記載されます。
登記簿謄本の表題部は、登記簿謄本の内容を理解するための重要な情報が記載されています。登記簿謄本を取得した際には、まず表題部を確認するようにしましょう。
権利部(甲区)の内容
権利部(甲区)には、所有者や抵当権などの権利関係の情報が記載されています。
具体的には、以下の情報が含まれます。
これらの情報は、不動産に関する取引において重要な情報となります。
権利部(乙区)の内容
権利部(乙区)には、使用貸借権や地上権などの制限に関する情報が記載されています。所有権以外の権利の内容について記載された部分です。
具体的には、以下の情報が含まれます。
権利部(乙区)は、所有権以外の抵当権などの権利関係を把握する上で重要な情報源となります。不動産取引を行う際には、必ず確認する必要があります。
共同担保目録の内容
共同担保目録には、複数の土地や建物を担保にした場合の情報が記載されています。一つの抵当権に対して、土地と建物を担保として提供した場合、これらの不動産は共同担保の関係となり、登記簿謄本にその旨が記載されます。
例えば、Aさんが土地と建物を購入した場合、住宅ローンの返済が滞った際に、債権者は土地と建物の両方を差し押さえることができます。
共同担保目録は、複数の不動産が一つの債務に対して同時に担保提供されていることを示す重要な情報です。
まとめ
登記簿謄本とは、不動産の権利関係を証明する公的な書類です。不動産を購入したり、抵当権を設定したりする際には、必ず必要になります。
登記簿謄本には4種類あり、それぞれ用途が異なります。登記簿謄本の取得方法には、以下の4種類があります。
登記簿謄本は不動産に関する取引を行う際に必要な書類のため、取得方法に関する正しい情報をリサーチしておきましょう。

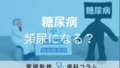

コメント