「バリバリの金融実務家であった私が、わからないことがあれば一番頼りにし、最初に意見を求めたのが山本謙三・元日銀理事です。安倍元総理が、もし彼がブレインに選んでいたら、今の日本経済はバラ色だったに違いない」
元モルガン銀行・日本代表兼東京支店長で伝説のトレーダーと呼ばれる藤巻健史氏が心酔するのが元日銀理事の山本謙三氏。同氏は、「異次元緩和」は激烈な副作用がある金融政策で、その「出口」には途方もない困難と痛みが待ち受けていると警鐘を鳴らす。
黒田日銀は、長期金利をゼロ%程度に抑え込むために、多額の国債買い入れを行った。その結果、日銀の国債保有残高は約590兆円に達し、日銀当座預金残高も、国債買い入れに見合う形で約561兆円に積み上がった(24年3月末時点)。引き継いだ植田日銀は、11年に及んだ異次元緩和を終了し、2024年7月には月間の国債買い入れ額をそれまでの6兆円程度から2026年1〜3月期に3兆円程度に減らす方針も決めた。しかし、計画通りに2年間減額を進めても、日銀がなお500兆円以上を抱えている姿に変わりはなく、市場機能の完全な回復には程遠い。
財政赤字を丸呑みしてきた日銀が市場から徐々に遠ざかれば、長期金利は想定外の上下動を起こすリスクを孕む。はたして、植田日銀は滞りなく、出口戦略を進めることができるのか?
※本記事は山本謙三『異次元緩和の罪と罰』から抜粋・編集したものです。
資本主義システムをめぐるコルナイの主張
計画経済体制を分析し、その構造的欠陥を解明したハンガリーの経済学者コルナイ・ヤーノシュは、著書の中で、資本主義システムと社会主義システムを比較し、次のように述べている(コルナイ・ヤーノシュ『資本主義の本質について──イノベーションと余剰経済』講談社学術文庫)。
「急速な革新(イノベーション)やダイナミズムは、起こるかもしれないし起こらないかもしれないといったランダムな現象ではなく、資本主義というシステム特有の性質に深く根ざしたものである(中略)その反対に、社会主義システムについても同様のことが言える。偉大な革新的な新製品を作りだせないということやその他の局面での技術進歩が後れることは、政策に誤りがあるからではなく、社会主義というシステム特有の性質に深く根ざしたものである」
第3章で紹介したように、シカゴ大学のラジャン教授は「中央銀行による介入は少ない方が、おそらく良好な結果をもたらすだろう」と述べている。これは、政府や中央銀行といった公的当局の市場介入を極力減らし、民間の新陳代謝を通じて経済の活性化を図る資本主義システムに内在する固有の利点を信じてのことだろう。
日本が計画経済のもとにあるわけではないが、ただでさえ一般政府の債務残高対GDP比率が先進国で断トツに高い国だ。中央銀行のバランスシート規模の拡大は、コルナイの主張する資本主義システムのもつダイナミズムを脅かしているように見えてならない。
日銀のバランスシートを見ると、総資産(=負債・純資産計)は、2013年3月末の約165兆円から2024年3月末には約756兆円まで拡大した。じつに4.6倍である。

他の主要な中央銀行との比較でも、その巨大さが際立つ(図表5-1)。中央銀行の総資産の対GDP比率は、米国FRBの35%、欧州ECBの48%に対し、日銀は127%に達する。異次元緩和が始まる前の同比率は30%台だったので、この間の規模拡大がいかに劇的なものだったかが分かる。
長短市場金利の抑え込みが市場機能を低下させた
日銀のバランスシートの膨張は、主として大量の国債買い入れの結果である。当初は巨額の資金供給そのものを狙いとして、2016年以降は長期金利をゼロ%程度に抑え込むことを狙いとして、日銀は国債の大量買い入れを続けた。
もし日銀が市場への関与を控え、金利を市場の自由な形成に任せていれば、長期金利はもっと高い水準で推移していたはずだ。これを力ずくで抑え込むために、大量の国債買い入れが必要だった。
前章で述べたように、FRBは、イールド・カーブ・コントロールのアイデアを棄却した。中央銀行としての独立性が脅かされるリスクを警戒してのことだったが、同時に、中央銀行が自らのモデルや理屈に頼って長期金利の水準を固定すると、「結果的に不適切な金利の上限や目標を設定しかねない」ことも危惧していた。逆に、日銀はデフレ脱却の名のもとに、適正水準からの乖離をみずから積極的につくり出しにいった形である。
では、本来、長期金利はどの程度の水準が適正だったと考えられるだろうか。経済学では、長期金利の水準は、長い目で見ると、物価上昇率の将来見通しと実質自然利子率の和に落ち着くと考えられている。
実質自然利子率とは、「引き締め的にも緩和的にも作用しない中立的な実質金利の水準」と定義される。厄介なのは、実質自然利子率が奈辺の水準にあるかは推計に頼るしかないことだ。予想物価上昇率も、人々の見方を外部から測定するのは容易でない。計算式に当てはめるには、不確実な要素が多い。
そこで、ここでは過去の実績値を計算式に当てはめ、長期金利ゼロ%程度という誘導水準が、どれほど適正水準から乖離したものだったかを探ってみたい。実質自然利子率は一定の仮定の下では潜在成長率に等しいとされることを念頭におき、ここでは、実質自然利子率に代えて実質GDP成長率の実績を、また予想物価上昇率に代えて物価上昇率(GDPデフレーターの上昇率)の実績を代入し、長期金利の水準にあたりをつけてみたい。いうまでもなく、実質GDP成長率とGDPデフレーターの上昇率の和は名目GDP成長率にほぼ等しいので、ここでの議論は、十分に長い期間をとれば、長期金利は名目GDP成長率の水準に収れんするとの見方に立脚していることになる。
異次元緩和が始まった2013年度から2022年度までの10年間の名目GDP成長率は、年率プラス1.31%だった。実質GDP成長率が年率プラス0.67%、GDPデフレーター(GDP統計の作成に利用する物価)の上昇率が年率プラス0.64%である。この式に従えば、2013年時点での10年物国債の長期金利は1%台半ば近くに適正値があったと推定される。この10年は、好景気も、新型コロナの感染拡大に伴う景気停滞期も含むため、その後の期間も、長期金利の適正値は1%台半ば周辺から大きくかけ離れることはなかっただろう。にもかかわらず、日銀は現実の長期金利をゼロ%程度に抑え込み続けた。それだけ強烈な金融緩和であったといえるし、それだけ市場機能を低下させたともいえる。
こうした国債金利の極端な抑え込みは、他の金融市場にも波及した。超低水準の国債金利を眺め、投資家は少しでも高い金利を得ようと社債市場に殺到し、社債金利も大幅に低下した。貸出市場でも、貸出金利が低下した。
社債金利や貸出金利に織り込まれている信用スプレッド(国と企業の信用力の差を表すもの)も、日銀による国債金利抑え込みを眺めた投資の殺到で大幅に縮小した。
こうした影響は金融市場にとどまらず、実体経済に波及し、国や企業、家計の経済活動にも影響した。日銀にすれば需要の拡大を狙った金融緩和の効果浸透であり、市場から見れば、歯止めを失った国債発行や生産性の低い企業の生き残りに象徴される市場機能のゆがみの伝播である。
YCCの修正が意味したもの
ひとつ留意しておきたいのは、日銀が、2024年の異次元緩和解除までの間、イールド・カーブ・コントロール(YCC)における長期金利の変動幅を数次にわたり変更していることである。とくに2022年12月の変動幅拡大は、市場に大きな変動をもたらしたので、そのロジックにも触れておきたい。
日銀が長期金利の変動幅を±0.25%から±0.5%に拡大する直前の年限別イールド・カーブ(利回り曲線)を描くと、10年物金利だけが突出して低水準だったことが分かる(図表5-2の2022年12月19日のカーブ)。日銀が10年物金利に狙いを定めて長期金利のコントロールを続けていた結果である。

一方、それ以外の年限の国債金利は、世界的な物価の上昇を受けたグローバルな金利の上昇にひきずられるかたちで、じわじわと上がっていた。その結果、イールド・カーブに極端なゆがみが生まれた。
このゆがみは、社債市場にも波及し、低金利の社債に買い手がつかなくなり、多くの社債発行が難しくなった。2022年12月に日銀が変動幅拡大に踏み切ったのは、イールド・カーブのゆがみを是正し、社債発行の環境を整えようとするものだった。
ただし、10年物金利が突出して低かったにせよ、イールド・カーブ・コントロールのために行ってきた大量の国債購入は、多かれ少なかれ、すべての年限、すなわちイールド・カーブ全体にゆがみをもたらしていた。22年12月の10年物金利の上限を小幅に引き上げるだけではイールド・カーブのゆがみは解消されなかった。日銀に残された選択肢は、すべての年限を抑え込んで政策の一貫性を保つか、市場の自由な形成にゆだねるかしかなかった。
実際、22年12月の日銀は、10年物金利の変動幅を拡大する一方で、他の年限の金利の上昇を牽制する手段を講じ、市場に介入する姿勢をむしろ強めた。一方、23年4月に発足した植田日銀は、7月、10月と、長期金利の変動幅を2度拡大したあと、24年3月にイールド・カーブ・コントロールを撤廃した。要は、市場機能のゆがみをこれ以上放置できなくなったということである。
それでも、現状は市場機能を完全に回復するに至ったわけではない。長期金利の完全な機能回復とは、日銀が金利の決定を市場に委ね、長期金利の形成に原則として介入しない状態に移るときである。24年7月、日銀は当面2年間の国債買い入れの減額を決めたが、2年後も、事実上中途売却できない長期国債を500兆円以上抱えている姿に変わりはなく、市場機能の完全な回復には程遠い。一方で、長く、強烈な金利抑え込みを続けてきた以上、日銀が市場から完全に遠ざかれば、金利は思わぬ上下動を示しかねない。日銀は慎重なステップを踏まざるをえず、長期金利の完全な機能回復には時間を要する。
*本記事の抜粋元・山本謙三『異次元緩和の罪と罰』(講談社現代新書)では、異次元緩和の成果を分析するとともに、歴史に残る野心的な経済実験の功罪を検証しています。2%の物価目標にこだわるあまり、本来、2年の期間限定だった副作用の強い金融政策を11年も続け、事実上の財政ファイナンスが行われた結果、日本の財政規律は失われ、日本銀行の財務はきわめて脆弱なものになりました。これから植田日銀は途方もない困難と痛みを伴う「出口」に歩みを進めることになります。異次元緩和という長きにわたる「宴」が終わったいま、私たちはどのようなツケを払うことになるのでしょうか。
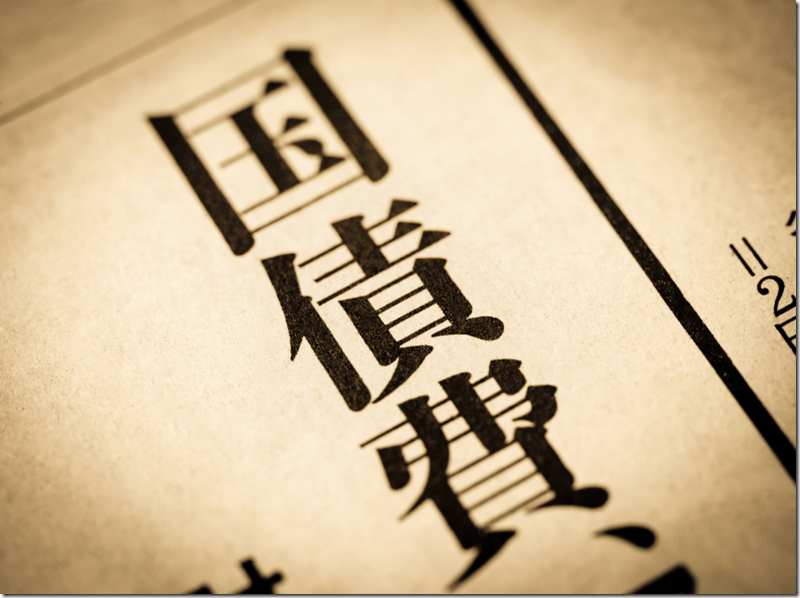



コメント