日銀の金融政策結滞会合後に記者会見する植田総裁。筆者は今回が「3度目の死」だという(写真:ブルームバーグ)
日銀は死んだ。
正確に言えば、日本銀行は再び仮死状態に陥ってしまった。
どういう意味か。日本銀行は、もはやいかなる有効な金融政策も行えなくなってしまったからである。死んだのは、これで3度目だ。
2013年、2014年に続く「3度目の死」の意味とは
最初は、アベノミクスのスタートであり、異次元緩和を始めた2013年4月4日。日銀が根本的、理論的に誤っている自滅政策を始めたときだ。このときに、日銀の死は確定してしまったから、それ以後は、「お前はすでに死んでいる」という状態で異次元緩和を続けてきた。
2度目は「黒田バズーカ第2弾」と呼ばれる、異次元緩和の拡大をした2014年10月末である。すでに異次元の大量の国債買い入れを行っており、債券市場に歪みや副作用が出ていたにもかかわらず、「インフレ期待の低下を防ぐ」という不明瞭な理由で、さらなる国債買い入れ額の増加を行ったときだ。
この状況で、国債買い入れを増加するのであれば、理屈から行けば、過去、現在、未来の金融政策の整合性を図るためには、永遠に金融緩和を拡大し続けなければならなくなった。当時、私は「異次元緩和から永久緩和へ移った」と表現した。
3度目は今回だが、その伏線は2024年8月7日。同年7月末に2度目の利上げをして政策金利が0.25%になった直後に、世界的な株価暴落が起きた。特に8月5日の日経平均株価は、値幅では史上最大の大暴落となった。これに慌てて、日本銀行の内田眞一副総裁は「金融資本市場が不安定な状況で利上げをすることはない」と明言してしまった。これで日銀は死が決定づけられてしまったのである。
1度目は「自殺」、2度目は「復活チャンスの自己破壊」
実は上記の「3回の死」は、それぞれ原因が違う。
1度目の死は、異次元緩和の始まりだが、この時の前代未聞の長期国債の大量買入れの目的、ターゲットは、デフレマインド打破という、世間のムードに流されたものであった。
景気は回復基調にあり、そもそも金融緩和は継続的にすでに相当な程度で行われていた。デフレと言っても、マイナス0.1%あるいは0%という程度のものであった。そして、ロジックもあいまいなものであった。
日銀が「何が何でもインフレ率を2%にする」と宣言し、世の中を驚かせるような実際の手段を取れば期待インフレ率が2%になる、すなわち、「呪文を唱えれば効く」あるいは「夢は願い続ければ叶う」というたぐいのものであった。つまり、日銀は論理を捨て、データに基づく金融政策を捨て、かつ日本銀行の独立性の精神を捨て、政治と世間に迎合する組織に自ら望んで変貌してしまったのだ。自殺である。
2度目の死は、1度目の死を半分取り戻せる、日銀の復活のチャンスを完全に破壊した。景気はいい。デフレでもなくなった。にもかかわらず、異次元緩和を普通の金融緩和に戻すどころか、異次元緩和という4次元緩和を5次元緩和にしてしまった。
デフレマインドの残り火を徹底的に消すために、原油価格の下落に対応して、大規模緩和をさらに拡大したのである。理屈はもちろんない。経済の危機でも金融市場の危機でもない。デフレの気配というのは、原油という完全な日本経済にとっては外部要因、しかも原油価格下落は景気にはプラスの要因であり、サプライサイドの要因であり、金融緩和で影響を与えられる需要喚起というルートと無縁のものであり、緩和を拡大する理由は日本中どこを探しても、経済学のテキストを探してもどこにもなかった。
もちろん、政策決定会合の執行部以外の審議委員の頭の中にもなかった。だから4時間にもわたる議論の後、5対4という前代未聞のボードメンバーの分裂での決定となった。しかも、当時の黒田東彦総裁は、2014年6月23日の経済同友会会員懇談会における講演で、以下のように述べている。少々長くなるが引用しよう。
「日本経済は緩やかな回復を続けており、2%の『物価安定の目標』の実現に向けた道筋を順調にたどっています。もっとも、そうした中で、『人手不足』や『供給制約』といった供給力の問題が議論されることが多くなってきました。その背後にある潜在成長率の低下は、これまでも日本経済の課題として意識されてきたものの、需要が弱かったため、むしろ『余剰人員』や『過剰設備』が目先の問題となっていました。ところが、この1年ほどの間に状況が変わりました。大規模な金融緩和、財政支出、民間活動の活性化によって需要が高まってきた結果、水面下に隠れていた供給力の問題が顕現化してきたのです。こうした状況のもとで、中長期的な観点から供給力を強化することが重要だという認識が広がってきたように思います。このように、実際に問題として顕現化してきた今こそが、課題の克服に向けた取り組みを進めるチャンスです」
つまり、デフレもデフレマインドももはや問題ではなく、日本経済の問題は供給力にある、と当時の黒田総裁は認識していたのだ。では、なぜ、異次元緩和を最初の2年という約束を破って延長しただけでなく、さらに「黒田バズーカ第2弾」と呼ばれるほど、異次元緩和を拡大したのか。謎以外の何物でもないが、理屈はどこにもない。日本銀行の金融政策はどの観点からも、どのような立場の論者からも意味不明となったのである。2度目は自爆テロであった。
「世間から非難されるのは嫌だ」と告白した日銀
3度目の伏線については前出のとおり、2024年8月7日に日銀の内田眞一副総裁が、北海道函館市で開いた金融経済懇談会で「金融資本市場が不安定な状況で利上げをすることはない」と述べたときだ。日銀は7月31日に利上げしたばかりであり、債券市場は落ち着いていた。為替は動いていたが、それならば、金融資本市場とは言わない。金融市場という言葉を使う。要は、株価だ。つまり「金利は株式市場次第」と、自ら株式市場に魂を売ってしまったのである。これは前代未聞の失策だ。
なぜ、こんなミスをしてしまったか、というと、株価が8月5日に暴落して、日銀のせいにされたが、それは違う、俺たちは株価には絶対逆らわない、として、攻撃を回避することに必死だったからである。攻撃とは、株式トレーダーたちでもあったが、本当に逃げたいのは、世間からの攻撃だった。世間から非難されるのは嫌だ、という告白をしてしまったのである。
これは死を決定づけた。プロフェッショナルとして、世間体が最優先、怒られたくない、というのはありえない。しかし、ある日銀OBも、メディアの解説で「利上げはできるかどうか」、という質問に対して「今なら株価も高いし、円安が問題視されているから、少々円高になっても、政治や世間に怒られなくて済むから、可能だ」などと、当たり前のように発言することが何度もある。
つまり、それは日銀のいわば常識となってしまっているのである。政策プロフェッショナルとしての矜持も捨ててしまったのである。2度の死により、すでに地獄の入り口に立っていた日銀は、悪魔に魂を売り渡して、地獄に行くことだけは避けたのである。
さて、2025年5月1日。日銀金融政策決定会合の結果発表の日である。日銀は、物価も経済成長率の見通しも下方修正した。
植田和男総裁の記者会見での質疑での回答を簡潔に解釈すれば、オントラックのトラック(見通し)が下方にシフトしたのである。そして、下方リスクの方が大きいとも述べた。つまり、今後は、インフレ率も上がらないし、景気も悪くなるのであり、日銀もそう見通しているということである。利上げは当面、いや永遠にない、ということだ。
私は、2月28日の「トランプ・ゼレンスキー事件」(アメリカとウクライナの首脳会談)以降、「日銀のターミナルレート(金融引き締めの際の最終到達点)は0.5%だ」、とテレビ、ラジオ、原稿記事で繰り返し主張してきた。残念ながら、この予測は当たってしまいそうだ。
これ以上のインフレにはならない。少なくとも、賃金上昇が見通せるようなインフレにはならない(コストプッシュ、スタグフレーション的なインフレは除く)。これから景気は確実に悪くなる。金融政策として利上げする理由はない。
今後の株価は、乱高下および下落トレンドだろう。株価に支配された日銀の金融政策が、乱高下の中での下落トレンドで、利上げに動けるはずがない。もし利上げをするとすれば、円安に再度の悲鳴が上がり、政治と世間に攻撃されたときに、その攻撃を回避するためでしかない。それは金融政策の利上げではなく、組織自己防衛の利上げだ。
つまり、日本銀行は金融政策の自由度を完全に失ったのである。異次元緩和で、自ら道を踏み外し、そこから道しるべのない荒野に再度の異次元バズーカで自らの身を放り出し、株価と世間に嫌われないように魂を売ってしまった。そこへ、理屈の上でも、現在の金融政策を動かせない経済環境に世界は陥ってしまった。
日本銀行の金融政策は死んでしまったのである。
日銀というよりも、金融政策そのものが死んでしまった
一方的に、日銀を非難してきたが、実は、これは日銀のせいではない。
金融政策そのものが21世紀には死を迎えてしまったからなのである。
日本銀行が死んだのではなく、金融政策そのものが死んでしまったのである。だから、アメリカの中央銀行であるFEDも、2008年のリーマンショックなどの金融危機における救世主としてありがたがられる以外は、金融政策でうまくかじ取りができたことはないのである。
FRB(連邦準備制度理事会)のグリーンスパン議長が、1987年のブラックマンデーという株価危機を救ったことから、グリーンスパンプットという言葉が生まれたが、その後、株式投資家たちは理事長が代わる度に「バーナンキプット」「パウエルプット」、さらに今回は「ベッセントプット」(スコット・ベッセント氏は財務長官だが)とハヤし、中央銀行は株価を上げるためだけに存在するとみなし、臆面もなく中央銀行を執事のように扱っているのである。
しかし、実際そうなのだ。
今後、「東洋経済オンライン」や「会社四季報オンライン」の別の記事で議論する予定だが、21世紀、金融政策の効果、影響は、実体経済ではなく、すべて金融資産市場に吸い取られているのである。実体経済に影響を与えるとすれば、株式市場や為替を通じてだけであり、直接的な効果はまったくなくなってしまったのである。
だから、金融緩和をどんなに行っても、実体経済の価格、つまり物価は上がらず、資産価格だけが上がる、資産インフレだけが起きるのである。物価が上がるのではなく、為替が暴落するのであって、それにより輸入インフレが起きるだけなのである。
世界経済において、実体経済よりも金融資産市場の支配力が圧倒的となってしまった1980年以降、金融政策は力を失い、21世紀には誰の目にもそれが決定的になってしまったのである。
第2に、そもそも需要の過熱によるインフレも、欧米などの成熟経済からは消えてしまった。インフレも消えたのである。残ったのは、コストプッシュの供給制約によるインフレだけである。
なぜなら、ひとことだけ言っておけば、必需品の成熟経済におけるウェ―トが大幅に低下し、ほとんどがぜいたく品、エンターテイメント品になったからである。
もともと価格は、供給制約や供給コストとは無関係に、ブランド力のような企業の市場支配力で決まっており、かつそれは必需品でないから、独占的競争のように、価格が上がってしまえば、ほかのブランドの製品・サービスに消費者はシフトするから、価格を上げるという選択肢はないのである。
だから、景気が過熱しても、物価は上がらず、資産価格だけが上がった。逆に不況になっても、値下げする理由はなく、別の製品を作り、目先を変えて消費者を捉えようとした。だから、物価は下がらなくもなったのである。
そこへ、コロナショック後の供給不足によるショックが起こり、地政学面でも同様なショックも加わり、手薄になっていた必需品が突然不足するようになり、急激なコストプッシュインフレとなったのである。
このような環境では、金融政策の出番はない。利上げなどの引き締めをする理由はほとんどない。仮にインフレになっていても、需要を抑制したところで、ぜいたく品、エンターテイメント品が減るだけだから、こうしたサプライショックによる必需品のインフレは収まらないし、関係がない。
一方、景気が良くてもインフレになりにくいから、金融緩和をやめる大義名分がなくなる。少なくとも、緩和をやめることに拒絶反応をする株式投資家たちを説得する、誰の目にも明快な理由がなくなる。緩和をして株式市場に称賛される以外に、日の目を見ることはないのである。
今後、世界の中央銀行がとるべき金融政策とは?
したがって、日銀も自己嫌悪になる必要はない。日銀が死んだのは、金融政策が死んだだけのことであり、よりこれまでの経緯が、ほかの中央銀行よりも扱いにくい環境を残していっただけのことである。
日銀も、世界の中央銀行も、今後は、インフレでも景気でもなく、資産市場、つまり、債券市場と株式市場の安定性、為替の安定性だけをターゲットに金融政策を行うべきなのである。
景気やインフレのために金融政策を行うようになったのは、1929年の株式大暴落をきっかけとした大恐慌以後のことであり、まだ100年も経っていないのである。
それ以前のグローバル経済においては、為替だけが金融政策の理由だったし、株式市場がよりのさばっただけの違いであり、バブルを作らないために(バブルにならなければ暴落も起きない)、株式市場の安定性、投機の抑制が重要であった、大恐慌以前の本来の姿に戻るだけなのである(本編はここで終了です。この後は競馬好きの筆者が競馬論や週末のレースを予想するコーナーです。あらかじめご了承ください)。
競馬である。
リバティアイランド(5歳牝馬)が死んだ。香港遠征を行い、レース中の怪我で安楽死処分となった。これほど悲しいことがあるだろうか。2023年の3冠牝馬。関係者のみならず、すべての競馬ファンが悲しみに包まれた。
それだけではない。日本競馬のさらなる発展をもたらすはずの日本競馬の至宝を日本競馬界は失ったのである。
日本競馬の課題とは何か
これは、オーナーのせいでも調教師のせいでもない。誰のせいでもない。日本競馬および最近の世界競馬界の価値観がおかしくなってきていたことが原因なのである。
競馬の目的とはなにか。人間のエゴではあるが、サラブレッドとして最も優れた血を見出し、それを残し、発展させ、さらなる優れた競走馬を生産していくことである。それ以外にはない。
ファンを得るのも、馬券を売るのも、そのための資金と生産システムを得るためにある。日本競馬がここまで発展したのは、故・吉田善哉氏をはじめとした、社台グループの馬の生産の実績によるところが大きいが、それを支えたのは、JRA(日本中央競馬会)の競馬広報戦略であり、JRAの圧倒的世界一の馬券売り上げである。一口馬主という一種の発明、イノベーションが支え、「ダービースタリオン」をはじめ、多くのゲームなども日本競馬を支えている。
今の日本競馬に最後に残されている課題は、日本が圧倒的な競走馬生産大国であり、生産馬の質でも圧倒的に世界一であるということを世界の競馬関係者に認めさせることであり、その結果、日本馬の血が、世界に広がり、世界に残り、そこから日本馬の血がさらなる発展をすることである。
そのためには、海外のレースで日本生産馬(本当は調教馬も)が勝ちまくることである。その血を欲しいと思わせることである。これはセレクトセールで馬の生産者が儲かるためではなく、日本馬の血が海外にわたり、世界中でそれを基礎として、さらなる血の発展をすることである。そのためには、圧倒的な種牡馬が必要である。
しかし、牝馬は海外に売る必要はないし、売ってはいけない。繁殖牝馬とは、その現地の血の基礎となるものであり、門外不出の血となるべきものである。
優秀な繁殖牝馬こそ競馬界の至宝、本来のあるべき姿に
だから、牝馬を海外に売ることは必要ないし、その血の世界市場価格を高くする必要もない。つまり、牝馬は海外遠征する必要もないし、さまざまなリスクを考えれば、するべきではないのである。牡馬とまったく逆なのである。
それゆえ、実は3歳のクラシック戦などで能力を示した牝馬は即刻引退すべきなのである。牝馬の古馬のレースが相対的に少ないため、近年一口馬主を中心とする幅広い馬主やファンからの要望で増やしているが、それは実は間違いなのである。
例えば、和田共弘オーナー(シンボリルドルフなどのオーナーブリーダー)が1985年にスイートナディアを2歳(当時は3歳と数えていた)で引退させたのは、そういう考え方に基づく。
また前出の吉田善哉などはシャダイソフィアを5歳(当時は6歳)まで走らせ、同じ1985年、レース中の事故で安楽死させてしまい、一生後悔し続けた(同氏の棺にはシャダイソフィアの鬣が納められたという)。だから、香港競馬のように、生産とは無関係なレースの興行主体は、騙馬の出走を広く認めている。しかし、香港を舞台に長期間無敵を誇ったロマンチックウォリアーがどんなに強くても、騙馬である以上、競走馬の歴史には残らないし、そこまでの価値はない。
優秀な繁殖牝馬こそ、どんな種牡馬よりも重要な競馬界の至宝である。海外遠征だけでなく、牝馬古馬への考え方を、本来のあるべき姿に戻すべきである。
さて、天皇賞(5月4日に京都競馬場で行われる芝コース3200メートルのレース、G1)。うれしいことに牝馬の出走はない。ここは、種牡馬としての価値を最後に高められるかどうか勝負どころの、ジャスティンパレス(7枠13版)とブローザホーン(2枠3番)。ともに血統は申し分ないので、もう1つ、G1の勲章をどちらかに与えたい。
※ 次回の筆者はかんべえ(双日総研チーフエコノミスト・吉崎達彦)さんで、掲載は5月10日(土)の予定です。当記事は「会社四季報オンライン」にも掲載しています。
著者フォローすると、小幡 績さんの最新記事をメールでお知らせします。
小幡 績 慶応義塾大学大学院教授


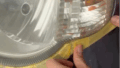
コメント