もう限界かもしれない…日々の生活費、増税、物価上昇、かつて民のために減税を決断した天皇がいたことを知っていますか?
その名は「仁徳天皇」、高台から見下ろした民家の煙が、彼の政策を大きく動かしました。
仁徳天皇の逸話から、現代社会が学ぶべき為政の本質を探っていきます。
民のかまどと、史実に記された減税の決断
![image_thumb[3] image_thumb[3]](https://hukiage.com/wp-content/uploads/2025/07/image_thumb3_thumb.png)
Via|(左)仁徳天皇(右)仁徳天皇陵大仙陵古墳|Wikipedia @wikipedia.org(引用)
仁徳天皇(にんとくてんのう)は日本の第16代天皇で、4世紀末〜5世紀前半に実在したとされる古代の君主です。
彼の最大の功績とされるのが、日本書紀に記された「民のかまど」の逸話です。
即位4年、仁徳天皇は高台から自らの治める領地を見渡したところ、民家のかまどから炊煙が上がっていないのを見て、国民が食事を炊く余裕すらない困窮状態にあることを悟りました。
「我が蔵には食糧が余っているのに、民が飢えているのは政治の失敗だ」として、仁徳天皇は3年間の年貢(租税)と労役を免除するよう全国に布令します。
これは当時の政治としては極めて異例で大胆な政策でした。
当然、国家財政は逼迫、宮殿は雨漏り、屋根の葺き替えすらままならない状態でもありました。
天皇自身も倹約を徹底し、衣服を破れるまで使い、自らも狩猟や農耕で糊口をしのいだと伝えられています。
3年が過ぎても民の暮らしはまだ回復せず、仁徳天皇はさらにもう3年、合計6年間の年貢免除を命じます。
ここまで国民生活を優先し、政治の中断とも言える判断を下した君主は、日本史上ほとんど例がありません。
「減税をした唯一の天皇」という表現はやや強調的にも見えますが、記録上、明確に全国規模で減税・免税政策を行い、その動機や成果が詳細に語られているのは仁徳天皇のみです。
その意味で、彼を唯一と称するのは誇張ではなく、史料に基づいた評価と言えるでしょう。
そして仁徳天皇は、民の暮らしが回復したことを確認した際、こう詠みました。
高き屋に のぼりて見れば 煙立つ
民のかまどは にぎはひにけり
国民の暮らしが戻ったことを、我が事のように喜ぶその姿は、今もなお理想の為政者の象徴として語り継がれています。
為政者は「共に苦しみ、共に喜ぶ」存在であるべき
仁徳天皇の真価は、減税政策そのものだけでなく、自らも倹約と不便を受け入れ、民と苦労を共にした姿勢にあります。
宮殿が朽ちても衣が破れても、民の生活が戻るまでは贅沢を拒み続けました。
やがて国民の暮らしが回復すると、恩返しとして民たち自らが宮殿を修繕したという逸話もあります。
これは「信頼と共感」による政治の力を象徴する話として、多くの人に語り継がれてきました。
この姿勢は、単なるリーダーシップではありません。
政治における信頼の再構築とは、数字や実績ではなく苦楽を共にした実感から生まれるものであるということを、仁徳天皇は行動で示しています。
現代の私たちは、しばしば「政治は遠いもの」「国は信頼できない」と感じがちですが、仁徳天皇の時代には、民の声を見過ごさず、耳を傾け、自ら行動を変えるリーダーの姿があったのです。
減税は未来の国力を育てるための投資である
2025年の今、日本社会では物価上昇、税負担の増加、社会保障費の膨張などが市民生活を圧迫しています。
実質的な手取りが減るなか、「このまま耐え続けられるのか」という不安が社会全体を覆っています。
そうした時代に、仁徳天皇の考え方「民が豊かであれば、我も豊かだ」という思想は、大きなヒントではないでしょうか。
彼の行った減税政策は、短期的には国家財政に大きな痛手を与えました。
しかし結果として、国民が活力を取り戻し、農業が回復し、税の再開がスムーズに行われたと記録されています。
これはまさに、「減税が未来の税収と経済循環を育てたモデル」と捉えることができるのです。
現代でも、減税は単なる人気取りではなく、消費喚起・事業投資・生活再建といった中長期の視点で行われるべき未来投資と考えられます。
もちろん、現在の日本財政がすぐに同様の政策を取れるわけではありません。
しかし、「まず国民の暮らしを立て直すことが最優先である」という哲学こそが、今もっとも求められているリーダーの姿勢ではないでしょうか。
まとめ
仁徳天皇の減税は、単なる財政政策ではなく、「民と共に生きる政治家」としての哲学の象徴でした。
そしてその姿勢は、数字ではなく暮らしの現場に目を向ける政治、支配ではなく共感から始まるリーダーシップを教えてくれます。
今の日本に必要なのは、単なる制度改革や財政均衡ではなく、国民の生活が潤ってこそ国は強くなる、という基本に立ち返ることです。
かつての高台に立った仁徳天皇のように、現代のリーダーたちもまた、煙の立たぬ暮らしに目を向け、声なき声に耳を傾けることから始めるべきではないでしょうか。
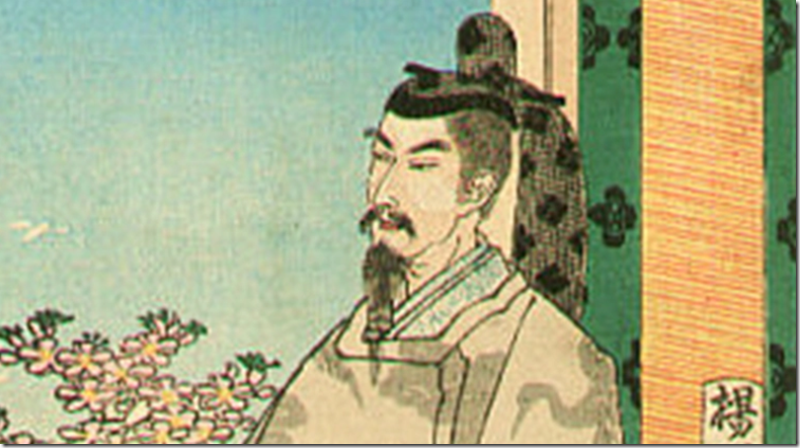


コメント