
京都出身者、あるいは現在、京都に住んでいる人と話している時に「お東さん」「お西さん」という言葉を聞いて、何のことだろうと疑問に思ったことはありませんか。
実はお東さんとは京都駅からほど近い場所にある浄土真宗東本願寺のことで、お西さんとは東本願寺と対極の場所に建っている西本願寺のことを指すのです。
そしてその両方同じ浄土真宗の寺院でも、それぞれお東は真宗大谷派、お西は本願寺派という別の宗派を名乗っているのです。
なぜ同じ本願寺なのに、宗派が別なのでしょうか。
あるいは逆に違う宗派のお寺は軒を並べているのでしょうか。ここではそのような本願寺の秘密について解説します。
浄土真宗とは
そもそも東本願寺、西本願寺の所属する浄土真宗とはどのような仏教なのでしょうか。
日本で1番門徒が多いのが浄土真宗
日本には、仏教の宗派は、主要な分け方で言っても、浄土真宗を始め真言宗などの密教や、曹洞宗などの禅宗などを含めて13宗派あります。
その中でも最も信者の多い宗派が浄土真宗です。
別名を「真宗」とも言い、江戸時代までは「一向宗」と呼んでいました。
浄土真宗は、平安時代の後期に浄土宗で学んだ親鸞(しんらん)が唱え始めました。
浄土真宗の教義は、有名な文言で言うと「善人なおもて往生す、いわんや悪人をや」という言葉に象徴されています。
現代文に解釈を入れながら訳すと「生きている間にのよい行いをした善人でさえ死んだら極楽に行ける。それくらいだから悪人であればなおさら極楽に行ける」ということです。
これを読んで何だか変だと思いませんか。
一般的な常識で言えば、悪人が極楽に行けなくても善人こそ極楽に行けるはずです。
つまり「悪人なおもて往生す、いわんや善人をや」というのが常識的な言い方でしょう。
しかし浄土真宗では、悪人こそ極楽に行ける、ということがその教義の最も根幹的な内容なのです。
この文言における「悪人」とは実はただの悪いことをした人を指すのではありません。
「自分は悪い行いをした」と自覚していて、それでも仏様にすがって極楽に行けるように願っている人のことを指します。
つまり「いわんや悪人をや」の悪人とは仏様に一心にすがっている人のことで、自分は善行をしたから極楽に行けるはずだと思って仏様にすがる気持ちがない善人よりも、そのような悪人の方が極楽に行ける、だから一心に仏様にすがりなさい、という教えなのです。
なかなか人間は善行を行うことはできません。
極論を言えば、魚や肉を食べること自体「殺生」をしているわけで、十分に悪行です。
したがって善人だけが極楽に行ける、悪人は極楽に行けないとなると多くの人が絶望的な気持ちになるのです。
浄土真宗の創始された平安時代はまさに人々はそのように思っていました。
しかし親鸞の唱えた浄土真宗ではそのような悪人こそ、自分の悪行を自覚して、それでも救ってくれるように仏様にすがるので極楽に行けるとしているのです。つまり発想の転換です。
このような教義だからこそ、浄土真宗は身分の上下にかかわらず多くの人に受け入れられ、信者数が日本で1番になったのです。
浄土真宗がお東とお西に分かれた背景
このような浄土真宗は多くの宗派に分かれていますが、その中でも最大のものが東本願寺を本山とする真宗大谷派と西本願寺を本山とする本願寺派です。
なぜこのようによく似た宗派が生まれているのでしょうか。
お東さんとはお西さんとは?本願寺には2つある
浄土真宗には真宗十派と言って、10の宗派に分かれています。
その中でも東本願寺の真宗大谷派と西本願寺の本願寺派が最大のものです。
キリスト教にもカトリックとプロテスタントがあるのと同じです。
本願寺が東と西に分かれている背景
実は本願寺は今から500年前の戦国時代には1つでした。
しかし織田信長が今の大阪城の場所にあった石山本願寺を攻めた石山戦争をきっかけに2つに分かれました。
当時の石山本願寺は、室町時代に浄土真宗を再興した蓮如(れんにょ)によって建立された浄土真宗の一大拠点であり、難攻不落の砦でした。
織田信長は、石山本願寺を10年以上攻め続けましたが、結局石山本願寺を降伏させることはできませんでした。
しかし浄土真宗との戦いに天下統一の足止めされることを嫌った信長は、当時の正親町天皇(おおぎまちてんのう)を間に入れて和睦を求めました。
その時に本願寺内で信長と和睦するか、徹底的に戦うかで議論が分かれ、この2つの考えによって本願寺内が2派に分かれてしまったのです。
これが本願寺が東と西に分かれるきっかけです。
当時の石山本願寺のトップは顕如(けんにょ)でしたが、顕如と三男の准如(じゅんにょ)は和睦を主張し、長男の教如(きょうにょ)は徹底抗戦を主張し、激しく対立しました。
最終的には顕如が和睦を決め、石山本願寺を明け渡して准如と共に和歌山の鷺森別院(さぎのもりべついん)に移転したのです。
これで信長と浄土真宗の争いはひと段落しましたが、争いの火種はまだ残っていました。
信長はその火種を完全に消そうと明智光秀に本願寺の攻撃を命じましたが、光秀は「敵は本願寺にあらず、本能寺にあり」と言って、返って信長を討ってしまいました。これが本能寺の変です。
この結果、浄土真宗は滅亡の危機から逃れることができました。
しかし顕如と教如の間に生まれた溝は埋まることがなく、顕如は浄土真宗のトップの座を長男の教如ではなく三男の准如に譲ったのです。
納得できないのは教如です。時代の支配者は徳川家康に移っていましたが、家康にとっても浄土真宗は目の上のたんこぶでした。
家康はこの勢力を弱めようとして、不満を持っている教如に寺地を寄進して、東本願寺を別に建てさせました。
この結果、本願寺は東と西に完全に分かれ、敵対してしまったのです。
お東とお西は違う?
お経の違いは?
ではお東とお西で唱えるお経などは違うのでしょうか。
浄土真宗で最も重視されるお経は「帰命無量寿如来(きみょうむりょうじゅにょらい)」で始まる正信偈(しょうしんげ)というものです。
これは実は釈迦の唱えたという本来の意味でのお経ではなく、親鸞の書いたものです。
しかしこの正信偈が浄土真宗では最も重要な「お経」であり、これはお東でもお西でも変わりはありません。
ただし、正信偈を読み上げるときの音程などには違いがあります。
仏壇の違いは?一発で違いを見分ける方法
お東とお西は教義もお経も同じですが、しかしすべてが一緒というわけではありません。
特に仏壇や仏具は東西で違いがあります。
まず仏壇ですが、この柱が金箔で加工してあるのがお西の本願寺派で、柱が黒塗りに加工されているのがお東の真宗大谷派です。
さらに仏具である花立、香炉、ロウソク立などは、お西は黒系の色合いの物を使用しますが、お東は金色の物を使用します。
特にお東では灯立というロウソク立ては亀の上に鶴が乗ったデザインのものですが、一方でお西は銅に漆塗りの宣徳製のデザインのものになります。
このように細かな点で見るとお東とお西にはいろいろな違いがあるのです。
「善人なおもて往生す、いわんや悪人をや」という根本の教義は同じですが、その教義を実際に実行し、運用していく上では相違している点が多々あります。
お東とお西の仲は悪かったのは江戸時代まで
徳川家康は当時でも大名以上の日本最大の集団で、結束力も強く、武装もして政権に対する大きな抵抗勢力であった浄土真宗の力をそぎ落とすために、画策をして2つに分断しました。
2つに分かれた本願寺は、徳川幕府に抵抗する以前に、浄土真宗内で争うようになり、お互いの力を減少させていきました。
その点で言えば、家康の目論見は見事に当たったわけです。
したがって、江戸時代の初期にはお東とお西は非常に仲が悪くなっていました。
敵対と言って良いほどです。
しかし江戸時代の後半になってくると、その対立は徐々に弱まり、内容によっては共同歩調をとるようになりました。
たとえば当時は浄土真宗は「一向宗」と呼ばれていましたが、これを正式に「浄土真宗」と名のれるように幕府に要求したり、親鸞を空海などと同じように「大師」と尊称できるように求めたりというようなことです。
ちなみにこの2つを江戸幕府は拒絶し、結局、浄土真宗を名乗り、親鸞が「見真大師」と呼ばれるようになったのは明治に入ってからです。
そして明治になると、江戸初期の確執も随分と薄れてきたこともあって、お東とお西の間では雪解けムードが広がり、第2次世界大戦以降は融和とも言ってよい関係性になりました。
現在ではお東とお西を含む浄土真宗の10派で真宗教団連合というものを組織し、互いに盛んに交流しています。
たとえば真宗大谷派のセミナーで本願寺派の龍谷大学に所属している僧侶が先生として講演したり、また浄土真宗の最も重要な法要報恩講では西の門主、東の門首という双方の宗派のトップがお互いの本山を参拝したりという具合です。
しかし一方では、信者間ではあからさまに敵対はしていませんが、たとえばお東の本願寺派系の高校の生徒は京都に修学旅行をしたときに、本山である東本願寺には参っても、西本願寺には行かない、というような潜在的な対抗心は残っているようです。
そういう意味では公式にはお東とお西の敵対はありませんが、心情的な違和感はまだまだ一般門徒の間には存在していると言えるでしょう。
まとめ
本願寺のお東とお西の違いがお分かりいただけたでしょうか。
浄土真宗が二派に分裂したのは政治上の関係なので、根本的に教義の違いはありません。
ただし、仏壇や仏具などのように、細かい点を見ると違うところもあります。
現在、二派は互いに交流するほどで、関係は良好です。
ただし、新たに浄土真宗のお寺の門徒になる場合は、自分の家は二派の内どちらなのかは把握しておくに越したことはないでしょう。
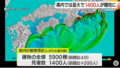

コメント