出典 : kitsune05/Shutterstock.com
焼酎の「甲類」と「乙類」、その違いをわかりやすく解説!蒸溜方法・味わい・原料の違いを詳しく説明し、混和焼酎の魅力にも迫ります。焼酎選びのご参考にどうぞ。
「甲類焼酎」と「乙類焼酎」の違いは、日本の「酒税法」による分類の違い

Milanchikov Sergey/ Shutterstock.com
焼酎は製法の違いで「甲類焼酎」と「乙類焼酎」の2種類に大別されますが、両者の違いを知ることで、たのしみの幅が広がります。今回は、酒税法で規定されている焼酎の製法による分類に着目し、「甲類焼酎」と「乙類焼酎」それぞれの特徴や魅力を深掘りしていきます。
「甲類焼酎」と「乙類焼酎」は日本の酒税法上の分類
焼酎は「もろみ」と呼ばれる発酵液を蒸溜して造られますが、一般に、連続式蒸溜機で造られたものを「甲類焼酎」、単式蒸溜機で造られたものを「乙類焼酎」といいます。「甲類焼酎」と「乙類焼酎」は異なる蒸溜方法に着目した分類方法で、酒類の製造・販売免許や酒税などを定めた法律「酒税法」上の分類でもあります。
なお、2006年の酒税法改正によってそれぞれの正式名称が変更になり、前者を「連続式蒸溜焼酎」、後者を「単式蒸溜焼酎」と呼ぶようになりましたが、ラベルなどの表示には、現在も「甲類焼酎」「乙類焼酎」の表示が認められています。
また、「甲類焼酎」は「焼酎甲類」、「乙類焼酎」は「焼酎乙類」と呼ばれることもあります。
両者の違いをチェックする前に、それぞれの蒸溜方法を見ていきましょう。
連続式蒸溜
「甲類焼酎」は、連続的に蒸溜操作を行う連続式蒸溜で蒸溜された焼酎です。
蒸溜酒の製造に使われる蒸溜機の歴史は紀元前まで遡りますが、連続式蒸溜機の誕生は19世紀と比較的新しく、伝統的な乙類焼酎に対して「新式焼酎」と呼ばれることもあります。
連続式蒸溜という蒸溜方法が英国を経由して日本に伝来したのは、明治の終わりのこと。もともとはウイスキー造りなどに使われていた製造法で、その名のとおり、原料となるもろみを連続して投入しながら繰り返し蒸溜を行います。
以下に紹介する伝統的な蒸溜方法、単式蒸溜に比べて効率的に不純物を取り除き、純度の高いアルコールを効率的に抽出できることから、蒸溜酒の製造以外にもさまざまな用途に使われています。
単式蒸溜
「乙類焼酎」は、昔ながらの蒸溜方法である単式蒸溜で蒸溜された焼酎です。旧式の製法で造られることから、「旧式焼酎」と呼ばれることもあります。
単式蒸溜とは、一度のもろみの投入につき一度だけ蒸溜を行う蒸溜方法。19世紀に連続式蒸溜機が誕生する以前に行われていた蒸溜方法は、すべて単式蒸溜にあたります。
蒸溜は元来、香料の抽出技術や錬金術の発展とともに進化してきたもので、その歴史は紀元前まで遡ります。メソポタミアのテペ・ガウラ遺跡(現在のイラク北西部)では、紀元前3500年ごろの香料用蒸溜機が発見されているというから驚きです。
蒸溜の技術が蒸溜酒の製造に用いられるようになったのは、紀元前750年ごろのこと。以来、改良を重ねながら東から西へと伝播し、日本へと伝わります。
香料用の蒸溜機は8世紀ごろには日本に伝わっていましたが、お酒の製造に使われる蒸溜機が伝来したのは15世紀中ごろといわれています。
江戸時代に使われた陶器製の蒸溜機「らんびき(蘭引)」の名を聞いたことがある人も多いのでは。これはアラビアの錬金術師ジャービル・ブン・ハイヤーンが9世紀に発明し、現在もウイスキーやブランデーの製造に使われている「アランビック」という蒸溜機の名前が転じたものだそう。
「らんびき」で蒸溜酒が造られていた時代から、明治末期に連続式蒸溜という新技術が導入されるまで、「焼酎」は「単式蒸溜焼酎」を指す言葉でした。

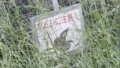

コメント