
(※写真はイメージです/PIXTA)
相続財産の中でも大きな割合を占める不動産ですが、ある民間企業の意識調査では「親から相続したくない」もののランキング1位となっています。背景には、いわゆる「負動産」への拒否反応があるようです。ここでは「負動産」を国が有料で引き取る新しい仕組み「相続土地国庫帰属制度」の最新の運用状況や国庫帰属事例についてみていきます。行政書士/宅地建物取引士の平田康人氏が解説します。
「負動産はいらない」「遺さないで!」という意思表示
終活をする年齢になり自分自身の相続を考えたとき、自分にとって大切な財産や先祖代々と受け継いできた財産などは、身内である子どもや孫などに引き継いでもらいたいと考えます。しかし、当の子どもや孫からすると、「無価値で負担しかない財産は遺さないでほしい」という本音があるようです。
株式会社AlbaLink(本社:東京都江東区)が全国の男女500人(10代~50代以上を含む)を対象に、令和7年1月~2月に実施した「親から相続したくないものに関する意識調査」では、次のようなランキングが公表されています。
【親から相続したくないもの(n=500複数回答)上位5位】
1位 不動産(54.4%)
2位 お墓(20.4%)
3位 借金(17.4%)
4位 骨董品(6.8%)
5位 車(5.6%)
※出所:【親から相続したくないものランキング】男女500人アンケート調査
親から相続したくないものに関する意識調査(株式会社AlbaLink)
(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000199.000055654.html)
意識調査の結果によると、親から相続したくないもの第1位は「不動産」で、全体の半数以上を占めています。主な理由は、
「田畑や山は管理が大変だから。両親ですら把握しきれない土地を私が管理できるとは到底思えない(20代女性)」
「両親が土地を相続して固定資産税に困っているのを見てきたから(30代女性)」
「親所有のマンションが築30年以上経過しているので、資産価値がないため(40代男性)」
などです。つまり「相続したくない不動産」=「所有しているだけで負の財産となる、いわゆる〈負動産〉」であることがわかります。
子どもからすれば、価値がある不動産ならありがたいが、親の実家や田畑、山林など、自ら住むことも、売ったり貸したりもできない〈実用性に乏しい不動産〉はいらない、というのが本音のようです。つまり「〈負動産〉はいらない。遺さないで」という明確な意思表示とも取れます。
「確実に負動産を手放す」という終活
親としては、子どもに「負動産」を相続させて苦労をかけるのなら、生前に負動産の所有権を確実に手放すことも終活のひとつになってきます。
そこで、負動産の引き受け手を探すことになりますが、売買や贈与、寄付の成立が難しい負動産は、民間や国による「有料引取サービス」の利用を検討することになります。
ただ、民間の有料引取サービスには、引取料の搾取だけを目的とする悪徳業者もいるため、お金だけ取って実際は引き取らなかったり、引き取っても管理義務を放置したりすることが懸念されます。運悪くそんな悪徳業者に当たってしまうと、手放したはずの負動産が管理不全により一層荒廃して、管理放置のクレームが、回り回って元所有者に返ってくることもあり得ます。
一方、国の有料引取サービスである相続土地国庫帰属制度では、引取りまでの手続きが煩雑であるうえに費用や時間が掛かりますが、一旦国に帰属されてしまえば、国が国有地として管理することになるため、管理の永続性という面からも安定した管理が期待でき、負動産と完全に縁を切ることができます。
法務省が公開…「相続土地国庫帰属制度の統計」「国庫帰属事例」
不要な土地を国が有料で引き取る「相続土地国庫帰属制度」は、令和5年4月施行から約2年になりますが、国が税金で管理するという安心感から、本制度の施行以降、申請件数は着実に増え続けています。法務省が毎月公表している本制度の運用状況※1では、直近で「申請件数:約3,500件」「帰属件数:約1,500件」、審査中件数や取下げ件数を除いた「帰属承認率:約90%以上」は施行当初より維持しています。
※1 法務省「相続土地国庫帰属制度の統計」(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00579.html)
なお、法務省による運用状況の公表は、令和6年9月度までは3ヵ月に一度のペースでしたが、同年10月度より毎月公表に変更され、申請件数の増加に対応しつつ、本制度の周知にも力を入れているようです。また、法務省が公表している「令和6年度法務省政策評価書※2」では、実際に国庫帰属した土地の事例が写真付きで一部公表されています。たとえば、次のような内容です。
※2 法務省「令和6年度法務省政策評価書」(https://www.moj.go.jp/content/001419858.pdf)
1.宅地の事例
●住宅街にある公道に面した「宅地630m2」
●実地調査で握りこぶしより大きな石が複数確認されたが、管理・処分を阻害する有体物とは認められず承認に至る。
●負担金20万円が納付され国庫に帰属した。
●審査結果が出るまでに要した期間は約5カ月。
*この宅地は、都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている土地ではないため、負担金は「原則:20万円」の適用となっています。
2.農用地の事例
●農用地区域内にある「畑440m2」
●実地調査で背丈より高い草木が存在したが管理・処分を阻害する有体物に当たらない。
●実地調査で、公道に通じるには他人の土地を通行する必要がある土地であることが判明したが、通行が「現に妨げられていない」ものと判断。(道路に接していなくてもOK)
●負担金67.2万円が納付され国庫に帰属した。
●審査結果が出るまでに要した期間は約7ヵ月。
*農用地区域内とは、市町村が今後農業上の利用を図るべきとして定めた区域。
令和6年度法務省政策評価書で公表されている土地帰属事例では、
「実際にどんな土地が申請されたか」
「審査の過程で何が問題になり、その問題を国側がどのように判断して承認に至ったか」
「負担金の額と審査期間は、どのくらいであったか」
など、現地写真を掲載して具体的に公表しており、本制度の利用を実際に検討している人にとっては、承認の見通しがイメージしやすい内容となっています。
相続土地国庫帰属制度は、施行後5年を経過した時点で見直しがされることも予定されています(相続土地国庫帰属法附則2項)。今後、一層使いやすい制度になることを期待したいものです。
平田 康人
行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研 代表
宅地建物取引士
国土交通大臣認定 公認不動産コンサルティングマスター


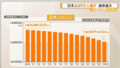
コメント