自動車保険の補償には使っても等級が下がらず、事故あり係数が付かないものもあることをご存じでしょうか。今回は、積極的に使いたい、等級ダウンのない自動車保険を紹介していきます。
文:佐々木 亘/画像:Adobestock(トップ写真=andranik123@Adobestock)
保険を使っても等級が下がらないケースがある

人身傷害保険だけの使用では、過失割合に関わらず事故でケガをしてしまった場合、治療費の請求をしても等級には影響しない(umaruchan4678@Adobestock)
自動車保険で保険金請求をすると等級が1~3下がり、事故あり係数が適用されて3年間保険料が高くなるというのが通例です。しかし、全ての保険金請求で等級が下がるわけではありません。
例えば人身傷害補償保険や搭乗者傷害保険、個人賠償責任保険などの補償は、保険金請求をしても等級はそのまま据え置かれることがあり、翌年以降の保険料も変わらないのです。
人身傷害保険だけの使用では、過失割合に関わらず事故でケガをしてしまった場合、治療費の請求をしても等級には影響しません。また、事故で同乗者が怪我をし、搭乗者傷害保険でだけ補償を受けた場合にも、保険料は上がらずに済みます。
さらに、日常生活で起こりうるさまざまな事故(クルマ関係以外)でも、他人の物を壊したり他人に怪我をさせたりした場合に個人賠償責任保険で補償を受けられます。この際も、ノーカウント事故となるのです。
これらの特約や補償を上手く使うことで、自動車保険をより頼りになる保険へと進化させることができます。等級ダウンの無いノーカウント事故のケースを、是非覚えておいてください。
特約を上手に活用すれば「使っても保険料アップなし」で安心できる

保険会社によっては、事故1回無事故扱い特約と呼ばれる特約を付けることで、一定の条件下では1回目の事故で等級ダウンを回避できる場合もある(umaruchan4678@Adobestock)
自動車保険には、賠償保険や車両保険以外にも、弁護士費用・人身傷害補償・ロードアシスト・ファミリーバイクなどの特約を付けることができます。「特約」とは、保険に追加できる補償のことです。
特約の中には、使っても等級が下がらないものもあり、これを活用することで保険の安心感はさらに高まります。
弁護士費用特約は、事故後の相手とのトラブルで弁護士に相談や交渉を依頼する際に役立ちますが、これを使っても翌年以降の保険料は上がりません。
日常型にすれば自動車事故以外のトラブルにも対応してもらえます。ただし、離婚、セクハラ、名誉棄損などは補償対象外となるため事前の確認が必須です。
また、ロードサービスが付帯されている場合、事故や故障で車が動かなくなったときだけでなく鍵を閉じ込めたり、ガス欠になったりバッテリー上がりになったりした場合に利用しても、等級には影響がないため安心です。
さらに、ファミリーバイク特約は、125㏄以下のミニバイクや50㏄以下の三輪以上の車に付帯できますが、これらの車両が事故を起こし、他人を死亡させるもしくはケガを負わせた際や、他人の物を壊した際に補償を受ける時にも、等級は据え置きとなります。
また保険会社によっては、事故1回無事故扱い特約と呼ばれる特約を付けることで、一定の条件下では1回目の事故で等級ダウンを回避できる場合も。こうした特約は、保険料が少し上乗せになりますが、いざという時に保険を使えず損をするというリスクを減らすことができるのです。
自動車保険を「使わない」のではなく「賢く使う」意識に変える
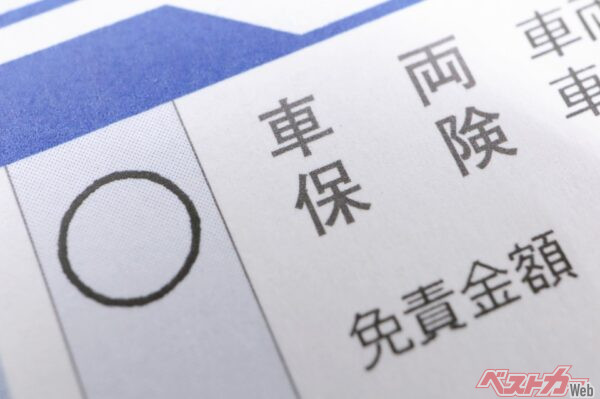
自動車保険を賢く使う意識に変えることで本来の保険の役割を最大限に活かすことができる(umaruchan4678@Adobestock)
何より大切なのは、保険の特約内容や等級が下がらない補償を正しく理解しておくことです。使えるものを使わず結果的に大きな負担を背負うよりも、「自動車保険を賢く使う」意識に変えることで本来の保険の役割を最大限に活かせます。
保険は備えであると同時に、困った時に助けてもらえる心強い存在です。知らないまま使わずにいるのではなく、上手に使うことで安心と経済的な負担の軽減を両立させていきましょう。


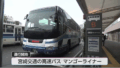
コメント