噴煙5000メートルを上げた直後、ドローンで上空から撮影した新燃岳=3日午後2時ごろ(産業技術総合研究所ホームページより)
霧島連山の新燃岳が7年ぶりに噴火してから22日で1カ月がたった。6月27日から断続的に噴火し、深部の膨張を示す動きも続いている。本格的なマグマ噴火に移行するデータはみられないが、今後の推移は見通せない。専門家は堆積した火山灰による土砂災害の危険性も指摘する。
鹿児島地方気象台によると、新燃岳は22日午後も小さな噴火を繰り返した。6月27日以降、断続的に噴火し、7月3日には噴煙が火口から5000メートルに達した。当初は水蒸気噴火とみられたが、噴出物の分析で初期段階からマグマが関与した噴火だったことが分かった。
この間、火山ガス(二酸化硫黄)の放出量は1日あたり900〜4000トンと多い状態で経過。気象台は火山ガスが急増したとして、噴火警戒レベルを3(入山規制)に引き上げた。火山ガスは15日の調査でも1600トンで「大きな変化はなく多い状態」だった。
九州大学地震火山観測研究センターの松島健教授(固体地球物理学)は「火山ガスが出ているということは、マグマの供給が続いている。地表に出る勢いはなく、地下でガスを放出している」と説明する。
地下深部では膨張が続いており、マグマ噴火に移行するか、このままガス放出で終わるのか、推移は分からないという。「マグマだまりの膨張と、地表に出てくるガスの状況を見ていくことが大事だ」と話した。
降り積もった火山灰が土石流を引き起こす危険もある。15日、上空から調査した鹿児島大の地頭薗隆名誉教授(砂防学)は火口の鹿児島県側で土砂災害の危険があると指摘する。
「これまでに降った灰の影響で不安定な土砂がある。今後、降灰がないと仮定しても、強い雨が降れば、この土砂が動く可能性がある」という。さらに降灰が続いた場合は「浸透能が落ちて、少しの雨でも土砂流出が起きる」とし、下流で土砂災害となる可能性にも言及した。

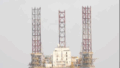

コメント