介護保険料は、40歳から徴収が始まるお金です。40歳〜65歳は「第2号被保険者」として、会社の健康保険料や国民健康保険料とあわせて徴収されます。
65歳になると「第1号被保険者」に切り替わります。第1号被保険者の保険料は、所得金額に応じて区分されるのが特徴です。人によってはこれまでよりも保険料が高くなる可能性があります。
介護保険料がとくに高い自治体・低い自治体はどこなのでしょうか。また、保険料に格差が生まれている理由はなんでしょうか。この記事では、65歳以上の介護保険料の格差について解説します。
1. 介護保険料が高い自治体・低い自治体の上位を紹介
介護保険料が高い自治体・低い自治体を、上位10自治体まで紹介します。
介護保険料が「高い自治体・低い自治体」ランキング
出所:厚生労働省「第9期計画期間における介護保険の第1号保険料について」をもとに筆者作成
1.1 保険料が高い自治体
1.2 保険料が低い自治体
保険料が高い自治体には、大阪府や青森県の自治体が多くランクインしています。一方、北海道の自治体や町村などは、保険料が低いようです。なお、全国基準額は6225円であり、大阪市は全国平均より約3000円高く、小笠原村は全国平均より約3000円低い数字となっています。
介護保険料は自治体によって給付対象者や人口といった事情が異なるため、地域ごとに納める金額が変わります。格差が生まれる具体的な理由を、次章で解説します。
2. 介護保険料に「地域格差」があるのはなぜ?
介護保険料に地域格差が生まれる理由としては、以下の3つが挙げられます。
- 要介護認定を受けている人が多い
- 単身高齢者世帯が増えている
- 地域の所得が低い
介護保険料が最も高い大阪市を例に、それぞれの理由を解説していきます。
2.1 要介護認定を受けている人が多い
介護保険料が高い地域は、要介護認定を受けている人が多い傾向にあると考えられます。
保険料の高い自治体のなかでも唯一9000円台となっている大阪市は、要介護認定を受けている人の割合が全国平均より多くなっています。2025年1月時点での要介護認定を受けている第1号被保険者の割合と、大阪市の要介護認定者の割合を比較してみましょう。
- 全国平均:約19.7%
- 大阪市:約28%
大阪市は全国平均を10%近く上回る認定率です。要介護認定を受ける人が多いと、介護保険給付が増えます。適切な給付をするためには相応の財源が必要になるため、保険料が高くなっているのです。
2.2 単身高齢者世帯が増えている
単身高齢者世帯の増加も、介護保険料が高くなる理由のひとつです。
高齢者でも夫婦で住んでいる人や子供と一緒に住んでいる人であれば、自身が要介護状態になっても、家族の支援を得ながら介護を受けられます。しかし、単身の高齢者世帯は身寄りがない場合もあり、要介護状態となった際は公的支援による介護が必須です。
2020年時点での大阪市の単身高齢者数は21万3260人です。同時期の人口は275万2412人で、人口の約8%が単身の高齢者となっています。
単身の高齢者が多くなると、結果的に要介護認定が増え、介護保険料が上がっていくのです。
2.3 地域の所得が低い
地域経済の冷え込みや低所得者の増加は、結果的に介護保険料の増加を招きます。介護保険料は、所得が多い人ほど金額が高く、低い人ほど金額が安くなります。そのため、安定した介護保険財政を運営するには、地域にどれだけ所得の高い人がいるかが鍵になるのです。
大阪市によれば、2024年度時点で65歳以上の高齢者のうち50%が住民税非課税世帯であるとしています。所得が低い人が多いと、保険料負担の軽減が適用される人が増えます。よって、制度全体を支えるためには標準となる保険料額や、所得が高い層の保険料負担を上げざるを得ないのです。
介護保険料は公的な介護支援をするために必要なお金ですが、徴収額が高いと家計も苦しくなるものです。介護保険料の地域差が家計や生活に与える影響を、次章で解説します。
3. 介護保険料の地域差が家計・生活に与える影響
介護保険料の地域差は、私たちの家計や生活にも影響をおよぼします。
地域差による影響が現れるお金のひとつが「年金」です。65歳以上の介護保険料は、以下の条件を満たした場合に年金から天引きされます。
- 老齢もしくは退職、障害または死亡の事由により年金を受給している
- 年間の受給額が18万円以上ある
そのため、差し引かれる介護保険料によっては、同じ年金受給額でも手取り年金額で損をする可能性があるのです。
年金からは介護保険料のほかに国民健康保険料や所得税、住民税が差し引かれます。最終的な手取り年金額は介護保険料以外の税や社会保険料の金額にもよりますが、介護保険料の金額によっては、ほかの自治体に住む人よりも手取り年金額が減る可能性があるでしょう。
また、介護保険料の地域差は私たちの将来設計にも影響するかもしれません。現在住んでいる自治体の介護保険料が高い場合、将来も住み続けたいと思っても、保険料の負担の高さがネックになることがあります。とくに年金収入や貯蓄が少ない人にとっては、少しでも負担を下げるために移住を検討する人もいるでしょう。
介護保険料の地域差は、老後の生活に少なからず影響を与えるものといえるでしょう。
4. まとめ
65歳以上の介護保険料は、それまでと算定基準が変わるため、グッと高くなったと感じる人もいるでしょう。加えて、地域差があることで不公平さを感じやすくなります。公的な介護支援は重要な行政サービスですが、運営の仕方には課題が残っているといえるでしょう。今後の制度や保険料負担の見直しが期待されます。



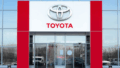
コメント