「食費も仕事で使うクルマのガソリン代も上がり続けて、我が家の家計は火の車です」
こう嘆息するのは千葉県在住の47歳男性だ。2歳と5歳の2女の父親で、建設系の個人事業主として働く一家の大黒柱。42歳の妻は派遣社員として事務仕事をしており、世帯年収は800万円弱だ。借家住まいだが、実の母親が認知症を患って昨年、施設に入り、父親はがんで闘病中のため、将来的には同じ千葉県内にある実家に移り住むことを考えている。
* * *
「親の介護費用や医療費は負担してませんが、それだけに遺産は期待できそうにない。妻も私も会社員として働いた期間が短いので、将来もらえる年金もわずかでしょう。高校の授業料が無償化されるので、下の子が高校を卒業するまでの今後15年は生活費をできるだけ切り詰めて貯金していくつもりですが、数千万円もの老後資金を貯められるかどうか……」
インフレや親の健康状態に悩まされながらも、今、最も不安を抱いているのは自身の老後のお金だという。「娘に私たちの面倒を見させたくない」と話すが、下の娘が成人するのは男性が63歳になる年とあって、その表情は暗い。
「もっと用意しなくては…」
老後に必要な資金は2000万円――。そんな数字がクローズアップされたのは2019年のことだった。金融庁の金融審議会「市場ワーキング・グループ」が、夫65歳以上・妻60歳以上の高齢夫婦無職世帯が95歳まで生活するためには2000万円の蓄えが必要だと試算し、公表したのだ。
その試算方法は単純だ。同世帯の年金受給額と支出額を集計し、平均的な赤字額を12倍(12カ月)したうえで30倍(65歳から95歳までの30年)してはじき出された金額だった。あくまで平均であるため、「わずかな年金しかもらえない平均未満のウチらはもっと用意しなくてはならない」と男性は頭を抱える。
追い打ちをかけるように、昨年は「4000万円問題」へとバージョンアップした。足元で進むインフレの影響を加味すれば、今後必要になる老後資金は2000万円でなく4000万円だ、とメディアが報じるようになったのだ。
「5年で倍に増えたら、これからまだまだ増えるのでは?」
そう不安に駆られる国民が急増したのは間違いない。先の男性も、その報道後に「投資経験ゼロだったけど、新NISAを始めた」と話す。
だが、「4000万円問題」は国民をミスリードしている。第一生命経済研究所の永濱利廣・首席エコノミストは「そもそも2000万円問題も誤った認識だ」と話す。
「2000万円問題は、2017年の家計調査で高齢夫婦無職世帯の月の収支が5万4520円の赤字だったため、それが30年ずっと発生すると2000万円の蓄えが必要になるとして公表されたものです。ところが、その世帯の収支は2020年には月1100円ほどの黒字になり、勝手に2000万円問題は解消されたんです。コロナ禍で支出が減った影響と考えられますが、2023年のデータで見ても月の赤字は3万8000円弱に縮小している。これを30年分にすると1400万円弱になる」
約2030万円
つまり、「老後1400万円問題」へとスケールダウンしているのだ。ただし、インフレを加味すると、必要になる金額は少々変わってくる。
「昨年話題になった『4000万円問題』は、『3.5%のインフレが30年続いたら』という仮定のもと算出した金額です。しかし、日銀は今年1月に物価見通しを若干引き上げましたが、25年度は2.4%で、26年度は2%という予想。つまり、3.5%のインフレが続いたらという仮定は、明らかに過剰なのです。日銀の物価目標に合わせて、安定的に2%のインフレが進むなかで毎月3万8000円の赤字(2023年の高齢夫婦無職世帯の月間赤字額)が発生すると仮定した場合、30年間で必要になるのは約2030万円になります」(永濱氏)
やはり2000万円は必要じゃないか……と思った読者は早まるなかれ。これはあくまで65歳の高齢夫婦も90歳の高齢夫婦も含めた平均的な値。年齢別の支出の傾向を分析すると、さらに必要になる蓄えは小さくなる。
「高齢夫婦世帯のひと月の赤字を細かく見ていくと、60代に比べて85歳以上の世帯は4分の1程度に減っています。人間は年を取るほど支出が減っていくから、赤字が減っていくのです。その年齢層別の支出を勘案し、さらにインフレ率2%を前提に試算してみると、高齢夫婦が30年間生きるために必要な蓄えは1200万円でした。物価の変動に合わせて年金の給付水準が徐々に減少していくことも念頭に入れても、1400万円あれば十分事足りるでしょう」(同)
夫はバリバリ会社員として働き、妻は家庭を守る――そんな“平均的”な家庭であれば、「老後に備えて蓄えておくべき資金は1400万円」が正解となる。一方で、夫婦ともに会社勤めをしてこなかった夫婦は、当然のことながら必要になる蓄えは大きく増える。
自助努力による備えは重要
年金制度を端的に示す際に用いられる夫婦の“モデル年金”は、夫と専業主婦の妻の老齢基礎年金に夫の老齢厚生年金を足したもの。昨年度のモデル年金は約23万円。一方、24年(令和6年)の家計調査結果によると、65歳以上の単身無職世帯(高齢単身無職世帯)の家計収支は2万7817円の赤字だった。
仮に、夫婦ともに基礎年金のみの場合は14万円弱にしかならないためにさらに赤字は大きくなる可能性がある。もらえる年金は人によってまちまちのうえ、インフレも進む中で、自助努力による備えは重要になる。
ファイナンシャルプランナーの岩城みずほ氏は「働き方は多様化しているし、お金の使い方などもさまざまなので、個々に必要な老後資金を試算することが重要」と話す。
「老後2000万円問題は、65歳から95歳までの30年間に必要なお金として示されたものですが、人生100年時代と言われるように、人の寿命は着実に長くなっています。同時に、“現役生活”も長くなっています。フルで働かなくても、パートなどでもいいので、なるべく長く働き、少し収入を得ることで、老後資金不足に対処することもできます。一方で、インフレ傾向が強まり、現金の価値が低下していることにも注意しておくべきでしょう。2%のインフレが続くと、10年で物価は約2割上昇し、30年でお金の価値はほぼ半分になる。このことを踏まえて、リタイアする10~15年前から老後プランを考えていくべきです」
健康寿命を延ばす
永濱氏によると、「シニアの労働参加率が右肩上がりを続けており、直近では60代前半でも7割以上が働いているほか、70代以上で見ても10%以上のシニアが働いている」という。
長く働き、長く収入を得ることが、老後資金問題の一つの解決策と言える。
「国民年金は60歳までしか加入できませんが、再雇用等で条件を満たして働けば、厚生年金は70歳まで加入できます。長く働けば、それだけ受け取れる年金は増えるわけです。加えて、年金は受給開始時期を繰り下げるほどもらえる金額が増える。原則として65歳から支給開始ですが、受給は60歳から75歳まで自由に決めることができます。5年繰り下げて70歳から受給すると42%も年金額が増えて、それが一生続くのです」(岩城氏)
このように、健康寿命を延ばして老後に備えるのと同時に、“資産寿命”を延ばすよう努めるべきだという。当然、活用すべきは新NISAやiDeCoだ。
「早く始めて、長く運用するほど複利効果で資産が増えやすくなります。最もメジャーな“オルカン”と呼ばれる全世界株式指数に1998年7月から毎月1万円ずつ積み立てた場合、25年3月末まで約27年間の投資額321万円は、トランプショックで大きく下落したものの、直近の時価総額で約1600万円へと5倍に増えています。今後も運用を続けながら、老後に必要な分だけを取り崩すようにすると資産寿命を延ばせます。例えば1500万円を65歳から毎月6万円ずつ取り崩していったら20年10カ月で使い切ってしまいますが、オルカンのような投信で、期待リターンは控えめに想定し年率5%、リスク量18%で運用しながら同じように取り崩していけば、市場の状況にもよりますが資産を長持ちさせることができます。上位50%の確率では、95歳時点で200万円ほど資産を残せます」(同)
固定支出を減らす
その運用の鉄則は、長期・分散・低コストだという。
「お子さんのいる家庭の多くは子どもの教育資金を確保するために学資保険に入る傾向にありますが、返戻率が非常に低いのでお金を増やす目的なら不向きです。個人年金保険も同じです。保障と運用の両方にコストがかかる分、資産が増えません。お金を増やす目的なら、新NISAやiDeCoを優先させましょう。途中で引き出さないですむように運用の計画を立てることが必要ですが、新NISAなら資金を一部引き出すことも可能です。また、突発的な支出の備えとして、普通預金に1年分の生活費をプールしておけば、仮に大きな医療費がかかっても高額療養費制度でカバーもできるため、医療保険も不要と考えます。こうした固定支出を減らして、資産運用に回すべきでしょう」(同)
将来受け取れるであろう年金は「ねんきんネット」で誰でも確認できる。自分の年金受給額をチェックしたうえで、老後に必要な資産と体力づくりに励むべし。
(ジャーナリスト・田茂井治)

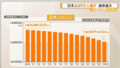

コメント