日本のグローバル競争力ランキングは右肩下がり。その背後にある要因を分析し、直観や主観を重視したイノベーションの重要性に迫る、多摩大学大学院のMBA特別公開講座「イノベーションと直観の科学」。本記事では、同大学院でMBA名誉教授を務める徳岡晃一郎氏が、人口減少が続く日本の現状や、競争力の低下の要因について語ります。
仕事だけがんばると、第二の人生の準備ができない
徳岡晃一郎氏(以下、徳岡):多摩大学大学院の基本コンセプト(である)イノベーターシップに基づいて今日はお話をします。
まず自己紹介させていただきますと、私は今ライフシフトという会社をやっている傍ら、多摩大学大学院の名誉教授として授業も行っております。
私は1980年に日産に入り、その後19年間は日産で人事をやっておりまして。1999年、ちょうどカルロス・ゴーンさんが来られた年なんですけれども、フライシュマン・ヒラード・ジャパンというコミュニケーションのコンサルティング会社に移りました。
ベースはアメリカのPRファームですね。特に人事関係、社内コミュニケーション、企業文化などのコンサルをやっておりました。
途中、兼務というかたちで多摩大学大学院で教え始めて、今も続けております。研究科長の時にイノベーターシップをテーマにカリキュラム全体を刷新し、今のMBAの形に至っています。
2017年、ちょうど還暦の年にコンサルは辞めて、ライフシフトという自分の会社を作りました。
人生100年時代。我々がキャリアをいかに長く保っていくのかは、一人ひとりの大きな課題になっていますので、そのお手伝いをしようというビジネスです。
企業の中で働いていたとしても、その次の第二の人生をいかに早く準備し始めるか。これは大きな問題で、真面目に一生懸命仕事をすればするほど、自分の第二の人生の準備の時間はなくなってしまう。そういう意味で、そこの両立をどうするのかという話をさせていただいております。
私の自己紹介はここまでにして、これからイノベーターシップについて話をして、森(華子)先生に引き継いでいきます。
まず時代認識が非常に大事で、今どういう時代を生きているのか。特にVUCAと言われる変動性、不確実性、複雑性、曖昧性。トランプ大統領になって何が起きるかわからないのも、象徴的な感じですけれど、そういう時代に生きているということですね。
2100年の日本人口は5千万人を割る
徳岡:何が起きるかわからない時に、我々の対応は2つの種類に分かれるんです。大きな波が襲ってくる中で、1つのタイプは「まぁしょうがないよね」「何が起きるかわからないんだから」と様子見をする。
2つめのタイプは、「でも、(わからないと言っても)絶対に起こることはあるでしょう」と、よく時代を認識する人ですね。だからVUCAの時代に騙されないで、今の時代をよく見ましょうということで、私が言ってるのが次の3つです。
人生100年&人口減少、人工知能革命とDX。それからポストコロナになって、今までのマネー資本主義、とにかく短期利益と株価さえ上げればいい時代は過ぎたこと。トランプさんになって、また揺り戻しなんていう話はありますけれども、長期の目線で考えたらこれらは終わらないわけですね。
ということで、まずイノベーションシップに入る前に、この時代認識について少しだけお話をしておきます。
人生100年&人口減少ということで、これはよくある寿命のグラフです。ご覧のように、ずっと男性も女性もひたすら右肩上がりです。コロナで最後ちょっと下がってますけど、また戻っていますよね。
どんどん寿命が長くなって、100歳までいくでしょうというのが最新の知見ということになります。
一方で、同時に起きるのが人口減少ですね。我々、すでに生まれた人たちはどんどん寿命が長くなるんですけれども、若い子たちが生まれてこないという現象です。この戦後、急激に立ち上がった人口のカーブが同じようなタンジェントで下がっていく。
毎年150万人亡くなって、70万人生まれてくるので、70~80万人減っていくんですね。単純に2100年の日本は、(人口が)5,000万人を割る国になる。
これはもう大事を超えてますよね。我々は若手の人数の少なくなる日本の(中でいわば弱者の)高齢者として生きていかないといけないわけです。
1つの時代認識を象徴する、この人口減少については、『未来の年表 人口減少日本でこれから起きること 』(講談社現代新書)という本がありますので、ぜひ読んでいただければと思います。
人口減による影響なので、ほぼ確実に起きるでしょうと。よっぽど技術(革新)が進むか、移民の方たちが入ってきてくれるかというと、そこはなかなか難しい。そうすると、我々は相当ひどい状態に対してレジリエンスを蓄えておかないといけないことがわかると思います。
平成元年の世界の時価総額トップ50社中、 日本企業は32社から1社へ
徳岡:このイメージをグラフにしたんですけれど、これは総人口の減少なんですね。先ほどの本から取ってきたいろいろな事象があって、線が引いてありますけども、2030年にこういうことが起きますとか書いてあるんです。
赤い線が10年刻みなんですけれども、2025年、2035年。ここ(図の中の四角)にみなさまの年齢を入れていただくと(イメージが湧くと思います)。私は67歳なので、(10年〜30年後には)77歳、87歳、97歳なんですけども。30年後にはこういったことが起きてくる。
みなさま方が今40歳だったら50歳、60歳、70歳という時に、まだぴんぴんしてますよね。そういった時に、もうこんなこと(図に記載のあるイベント)になってしまうということであります。
ここに「マイナス7,392」と書いてありますけど、これはこの10年で人が739万人減ると。この次の10年で888万8,000人減る。このインパクトは相当なもんです。次の10年でこれくらいの人数が減ります。その次の10年でこれくらいか、もしくは全部がいなくなる。
だから20年後を認識した時に、我々はどういう生き方をしていくべきでしょうか。あるいはどういうことが起きないと、日本は立ち行かなくなるでしょうか。これから生まれてくる方たちに、いい未来を残していく責任が僕らにはあると思うんですね。
あともう1つの時代認識として欠かせないのが、DX、AIですね。(世界では)こういったこと(技術革新)がどんどん起きていきますが、日本からはぜんぜん出てこない。その中で日本はどれくらい国力を保っていけるでしょうか。
これは有名な表ですけども、平成は失われた30年と言われています。グローバルの時価総額で見た場合、平成元年には50社中32社が日本企業だったんですけども、30年経ったら1社だけになってしまいました。この後どんなイノベーションを起こしていかないといけないか。どんな力があるんだろうか。
これもやっぱり我々が立ち向かわないといけないと思うんですね。このまま坐視しているわけにはいかない。こんな中で、自分たち自身のキャリアをどう作っていくのか。ただ単に老いていくばっかりじゃどうしようもないわけです。
それから次の世代に、どういう社会を残していくのかも考えないといけない。これが大人たちの責任だと思うんですね。ただ、わかっちゃいるけど実行できないのが人の常なので。「日本の職場もスピードを出せ」「イノベーションを起こせ」「ダイバーシティを進めよう」「モチベーションをアップしよう」と言っても、なかなか変わらないのが実態かと。
そこで一人ひとりがどうやって立ち向かうのか。そのスキルをぜひ身につけてほしいと、多摩大学大学院ではイノベーターシップという(コンセプトで)授業をやっているわけです。
日本のイノベーションが小粒になる5つの要因
徳岡:今まで(ものづくりで勝ってきた日本)の強みと裏腹に、「改善オンリーで大きなビジョンが見られない」というのが悪さをしてると思いますし、社内で「内向き型」でがんばるんだけど、なかなか外界志向になれない。「自前型」でアライアンスを組んでダイナミックにやればいいんだけど、なかなか面倒くさくてできない。日本語の壁もありますね。
「竹槍型」はテクノロジー音痴。それから「完璧主義」。なかなか実験して冒険してとならないわけですよね。なので多摩大学大学院としては、いかに大人たちがこういった挑戦に立ち向かうのか、しっかり考えようじゃないかと、そういうイノベーターシップの観点でMBAをやっているわけです。
こういう志や問題意識を持つ人が、続々と来ていただいているわけです。そうなると、ただでさえ忙しいわけですよね。我々は特に短期的成果を求められますから、一体いつそんなことを考えるのかという話になります。
でも本当は、こちら側(長期的な視点で業務や人のこと)をしっかり考えないと、未来がない。これは自明の理ですよね。最近は両利きの経営だと言いますけども、もう当たり前ですよね。ただそれが普通にできないのが問題なわけです。
実際に、自分たちがどれくらい時間を使っているかというと、ここ(短期的な視点で日々の問題解決)に80パーセントぐらい使っているんですね。こちら(工数確保)が10パーセントもいけばいいほうだと思います。
特にライフシフトの時代で、第二の人生まで考えないといけないとなると、ここ(人の成長)が重要なんですけども、もう本当に自分のことが後回しになっている。
こちら側(業務改革や人の成長)を考えるためには、やっぱりその時代をちゃんと認識して、この先に一体何が起きるのか。自分はどうありたいのかをしっかり考えていかないといけない。これはロジカルにはなかなか出てこなくて、自分の思いや夢がすごく重要になるわけです。これは2040年とは限りません。自分なりの時間軸を設定すればいいと思うんですよね。
「自分の子どもが大学を卒業した年に、何か考えてみよう」あるいは「役職定年になってまで(会社に)いる必要はないよね」という時期を考えてみようとか。いずれにしても、将来に何かの節目が来るとわかっていたら、そこをトリガーにする手があると思うんですよね。
いずれにしても、どこかで自分の節目を考えてバックキャストする。それをしないで、単年度の成果主義の評価に汲々としていたら、何も変わらないですね。その積み重ねで10年〜20年、あっという間に過ぎてしまいます。
みなさんも10年前と今の生活と、あんまり変わってないんじゃないかと思うんですね。それじゃあ、やっぱり未来は開けないでしょうということです。
関連タグ:
この記事のスピーカー

徳岡晃一郎
多摩大学大学院MBA名誉教授


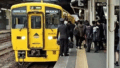
コメント