腎性骨症の概要
腎性骨症は、腎臓機能の低下により骨に含まれるカルシウムが減少して、骨や関節に影響が生じる疾患です。
慢性腎臓病との関連性が高く「透析骨症」や「腎性骨異栄養症」などとも呼ばれます。
腎性骨症の主な症状には、骨や関節の痛み、変形、腱の断裂などが挙げられます。
また、骨がもろくなりちょっとした動作で骨折しやすくなるのも特徴の一つです。
腎性骨症の代表的な原因は、腎臓機能の低下により引き起こされるミネラルの代謝異常、ビタミンDの不足、副甲状腺ホルモンの過剰分泌です。
とくに副甲状腺ホルモンの過剰分泌は血管の石灰化を招き、大動脈解離や心筋梗塞などの疾患を発症するリスクが高まるため、早い段階で治療する必要があります。
腎性骨症の治療には、食事療法や薬物療法などの内科的治療や副甲状腺の切除をおこなう外科的治療、腎臓機能を維持するための透析治療などが挙げられます。
発症を予防するためには、腎臓機能を保ち慢性腎臓病を悪化させないことが有効です。
生活習慣の見直しに取り組み、規則正しい生活を心がけましょう。

腎性骨症の原因
腎性骨症の原因には、腎臓疾患によるカルシウムやリンなどのミネラルの代謝異常や、ビタミンDの不足、副甲状腺ホルモンの代謝異常などが挙げられます。
腎臓には、体内の水分やミネラルの濃度を一定に保つ作用や、ビタミンDを活性化させる作用などがあります。
慢性腎臓病などの発症により腎臓機能が低下すると、ミネラルの代謝異常が起こり、リンが体外へ排泄されにくくなる高リン血症(血液中のリンの濃度が高い状態)が生じることがあります。
また、活性化ビタミンDが不足して、腸からカルシウムを吸収する量が減少し、低カルシウム血症(血液中のカルシウム濃度が低い状態)を発症しやすくなります。
さらに、リンは副甲状腺ホルモンの分泌と相互的に関与しているため、高リン血症によって副甲状腺ホルモンが過剰に分泌される(副甲状腺機能亢進症)ことがあります。
これらが骨や血管に影響して、さまざまな症状や合併症が見られるようになります。
腎性骨症の前兆や初期症状について
腎性骨症状の前兆として、腎臓機能の低下による身体のだるさやむくみ、尿量の変化、食欲不振などが挙げられます。
進行すると低カルシウム血症によって、骨や関節の痛み、骨の変形、腱の断裂などがみられ、骨がもろくなって骨折のリスクが高まります。
また、副甲状腺機能亢進症や高リン血症によって、血液中にリンが多く排出されると、血管の壁に付着して石灰化を引き起こし、大動脈解離や心筋梗塞などの心血管疾患のリスクが高まります。
腎性骨症の検査・診断
腎性骨症の検査では、血液検査や画像検査(レントゲン検査、超音波検査、CT検査など)、尿検査、骨密度検査などがおこなわれます。
血液検査ではカルシウムやリン、副甲状腺ホルモン、血清クレアチニンなどの値を測定します。
副甲状腺ホルモンの値が異常な場合には、超音波検査やCT検査などの画像検査によって、副甲状腺の状態を観察します。画像検査では、副甲状腺機能亢進症によって副甲状腺が大きくなっていないか確認します。
腎臓機能をさらに詳しく確かめるために、尿検査を行うこともあります。
また、骨の強度や骨密度の状態を観察するために骨密度検査やレントゲン検査が実施されるケースもあります。
腎性骨症の治療
腎性骨症の治療法は、内科的治療と外科的治療に大別されます。
内科的治療では、ミネラルの代謝異常や活性化ビタミンDの欠乏、副甲状腺ホルモンの過剰分泌を解消させるために、食事療法や薬物療法などがおこなわれます。
食事療法では主にタンパク質の摂取を制限して、リンの摂取をできる限り抑えます。
薬物療法では、ミネラルの代謝を正常に戻すために活性化ビタミンD製剤や、副甲状腺ホルモンの分泌を抑制する薬剤などが使用されます。
外科的治療は、内科的治療の効果が十分に得られない場合などで検討され、副甲状腺機能亢進症を解消する目的で副甲状腺の切除が実施されます。
透析治療をしている場合では、副甲状腺機能亢進症を再発するケースも少なくないため、副甲状腺の全摘出術が選択されるケースもあります。
腎性骨症になりやすい人・予防の方法
腎性骨症は、慢性腎臓病を患っている人に起こりやすい疾患です。
腎臓機能が低下するほど、腎性骨症の発症リスクが高まるとされています。
そのため、腎臓機能を悪化させないことが腎性骨症の予防につながります。
腎臓機能の維持には、生活習慣の見直しが効果的です。
食生活で減塩を意識したり、適切な水分量をこまめに摂取したりすることで、腎臓の負担軽減につながります。
慢性腎臓病は、糖尿病や高血圧症などの生活習慣病との関連性も指摘されているため、これらの治療や病状のコントロールも、慢性腎臓病の悪化予防に役立ちます。
また、重度の慢性腎臓病では透析治療によって腎性骨症のリスクを減らすことも必要です。
すでに透析治療を受けている場合は、腎性骨症の発症・進行予防のために定期的な血液検査を受けることも望ましいとされています。
関連する病気

監修医師:
本多 洋介(Myクリニック本多内科医院)
群馬大学医学部卒業。その後、伊勢崎市民病院、群馬県立心臓血管センター、済生会横浜市東部病院で循環器内科医として経験を積む。現在は「Myクリニック本多内科医院」院長。日本内科学会総合内科専門医、日本循環
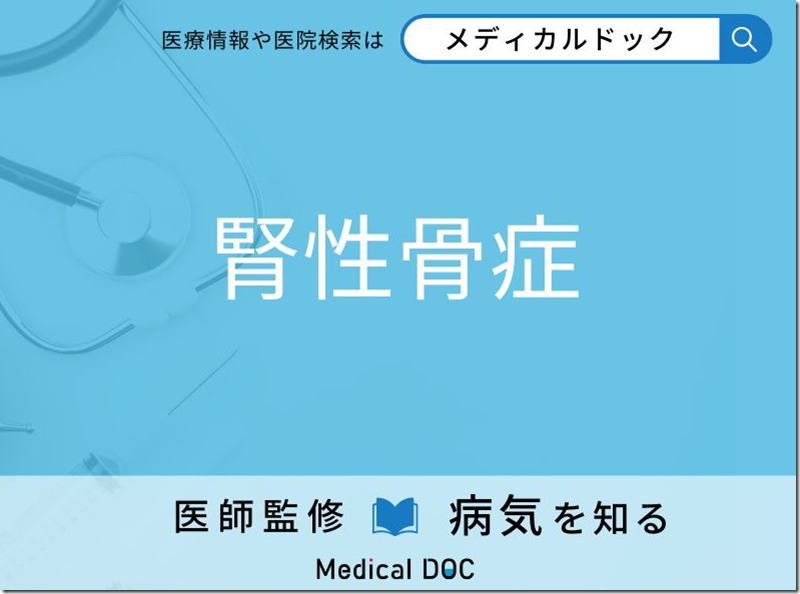


コメント