高血圧はよくある生活習慣病のひとつですが、実は命に関わる病気へとつながる静かなリスクでもあります。塩分がなぜ高血圧につながるのか、血管にかかる負担とはどれほどのものか。放置してはいけない理由と、正しい対処の考え方について、「小泉クリニック」の小泉先生に伺いました。
![]() 編集部
編集部
すでに高血圧の場合、とにかく塩分を控えるように注意されますよね?
![]() 小泉先生
小泉先生
この点については、様々な研究がなされているものの、「塩分の濃いところに水が集まる」のは事実なので、やはり塩分を控えるべきでしょう。血中の塩分濃度が高いと、血管内に水分を引き込むことで、高血圧の原因になります。血管内の血液量全体が増えると考えてください。
![]() 編集部
編集部
つまり高血圧は、血液量過多と言い換えられるのでしょうか?
![]() 小泉先生
小泉先生
「血液量全体が増えるケース」と、末端の動脈硬化によって「高い圧を加えないと流れにくくなっているケース」に分かれます。もっとも、血液量全体が増えたことによって、末端の動脈硬化を起こすことも考えられますよね。高血圧に対しては、血液量と末端抵抗の「二軸」で考慮していく必要があります。
![]() 編集部
編集部
ところで、高血圧のなにがいけないのでしょうか?
![]() 小泉先生
小泉先生
血管、とくに動脈へのダメージが問題ですね。動脈は、心臓の鼓動に合わせて拡張と収縮を繰り返します。みなさんご存じの「脈」は、このことによって生じているわけです。ところが、血液のハイプレッシャーが続くと、血管のしなやかさを失わせます。この状態が「動脈硬化」です。
![]() 編集部
編集部
心臓からの血液を、しなやかに受け止めきれなくなると?
![]() 小泉先生
小泉先生
そう考えていいと思います。また、毛細血管の“詰まり”も起こり得ますよね。脂質異常症などを併発していると、なおさらのことです。この詰まりが、心臓や脳といった重要な器官の血管で起こると、死に至ることもあります。
![]() 編集部
編集部
高血圧と診断される血圧の値は?
![]() 小泉先生
小泉先生
高い値と低い値の双方で診断し、「高い値で140以上、低い値で90以上」の状態が恒常的に続いた場合、高血圧とみなします。ただし、「白衣高血圧症」といって、医師や看護師の前だと緊張し、血圧が上がる人も少なくありません。できれば落ち着いた家庭内で計測し、上記から5を引いた、「高い値で135以上、低い値で85以上」を目安としてみてください。
※この記事はメディカルドックにて【高血圧の人は必見! 医師が食事面での注意点を解説「味付けよりも食べ方に注目して」】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。

監修医師:
小泉 信達(小泉クリニック)


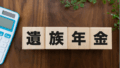
コメント