「地方移住」と聞くと、心惹かれる人も少なくないのでは。都市部の喧騒から離れ、自然に囲まれた環境のなかで、自給自足に近い暮らしをする――老後の生き方として、そんな選択肢に目を向ける人も珍しくないでしょう。しかし都会人にとって、田舎の暮らしは想定外の連続でした。
(※写真はイメージです/PIXTA)
東京から長野へ…憧れの田舎暮らしの現実
60歳で定年を迎えた片山亮さん(仮名)は、都内の中堅メーカーで長年勤めてきたサラリーマンでした。退職金として手にしたのは、1,800万円。さらに年金の繰り上げを選択し、月々12万円を手にするようになりました。65歳から年金を受け取っていれば月18万円ほどを手にできましたが、減額されても年金受給にこだわったのは2歳下の妻との「田舎暮らし」。定年後のセカンドライフをどう生きるか――何度も話し合った末、若いころから憧れていた地方移住を決意したのです。
「収入がゼロになることは不安で、地方移住は諦めていたかもしれない。60歳から年金がもらえるから、安心して移住ができたんです」
結婚して以来、賃貸マンション暮らし。「遊び盛りの子どもたちを育てるなら、持ち家のほうが楽だったかもしれない」と笑う片山さん。しかし、年を重ねても東京で暮らし続けるイメージがわかず、マイホーム購入に踏み切れなかったといいます。
「振り返ると、頭の片隅には常に田舎暮らしへの憧れがあったんだと思います」
移住先に選んだのは、長野県の山間部。価格は何と200万円。もちろん広大な土地付きです。購入のポイントは、居間中央にある囲炉裏でした。手続きやリノベーションに合計1,000万円を費やしましたが、「東京でマイホームを実現することを考えたら。広い土地があり、自給自足に近い生活ができるなら安いもんです」と興奮気味に話してくれました。
【60代の移住希望先ランキング】
1位「静岡県」9.5%
2位「群馬県」7.3%
3位「長野県」6.1%
4位「栃木県」5.5%
5位「千葉県」5.1%
出所:認定NPO法人ふるさと回帰支援センター『2024年 移住希望地ランキング 1位:群馬県 2位:静岡県 3位:栃木県』
地方移住を決めたときから、家庭菜園に関する本を何十冊も読みあさったり、移住フェアに参加したりと、積極的に準備を進めてきた片山さん夫婦。長野に引っ越してきてからは、夫婦で協力して畑を耕し、ニワトリを飼い始めました。「採れたての卵でつくる卵かけご飯。初めて食べたときの衝撃が忘れられません」
しかし野菜づくりは簡単ではありません。農業経験のない片山さん夫妻は、土地の性質や季節ごとの管理に戸惑い、種をまいても芽が出ず、雑草の管理も追いつかない日々。さらにイノシシに種を植えたばかりの畑を荒らされ絶望。「育てれば食べられる」という甘い見通しはすぐに崩れ、スーパーで食材を買う日々が続きました。
「自給自足なんて、無理な話なのかな――」
東京にはない「田舎だからの出費」の想定外
さらに見通しが甘かったと気づいたのは、冬を迎えたときのこと。山間部の古民家は隙間風が吹き込み、暖房代が予想以上にかかりました。灯油代は月に2万円弱、電気代も月2万円を超えるように。都会生まれ、都会育ちの片山さん夫婦には色々な意味で冬は厳しい季節でした。
「田舎であれば安く暮らせると思っていましたが、意外とお金がかかるんですよ」
またしかし地方では買い物に行くにも車が必須。ガソリン代や車検費用もかさみます。東京で暮らしていたときにはなかった出費です。さらに維持費が高いことがわかりました。「10年は乗る」として、中古で車を買いましたが、山道での運転で消耗が激しく、「10年なんて乗っていられない」と実感。さらに雪のない地域と違って、冬タイヤは必須。それらを加味すると、かなりの金額です。
「確かに住居費や食費は、東京と比べてかなり安い。でもすべてが安いわけではない。結局、トントンというイメージですね」
東京で暮らすよりも生活費が安い――どこか期待していたところですが、現実は厳しいものでした。
さらに片山さん夫婦は「地域の人との温かい交流」を期待していましたが、現実はそう甘くありませんでした。その地域には古くからの集落特有の慣習や人間関係があり、外部から来た新参者にとっては、なかなか溶け込むことが難しいものでした。地域の寄り合いや行事に参加しても、すでにできあがっているコミュニティに入っていくのは簡単なことではありません。移住者が珍しい存在ではない地域であれば、すんなりと溶け込むこともできるでしょう。しかし片山さん夫婦が選んだ地域は移住者は珍しく、いつまで経っても「よそ者」と扱われている感じがしたといいます。
東京で暮らしていたときのように気軽に立ち寄れる友人や知人が近くにいないため、相談相手もなく、夫婦二人きりで問題を抱え込むことになりました。さらに夫婦喧嘩も多くなったといいます。新しい生活に馴染めないストレスや想定外の連続に、「あなたの計画が甘かったのよ」」「すべて任せておいて、そんな言い方はないだろう」と、お互いを責めることが多くなりました。孤独感と閉塞感が、夫婦を蝕んでいったのです。
内閣府『令和6年版 高齢社会白書』によると、住み替えの意向を持つようになった理由として、「自然」への憧れを口にしている人の割合が1割いました。また住み替え先として、片山さん夫婦のように大都市から小都市・町村と、地方への移住を3.6%。さらに現在の居住地よりも規模の小さな都市への住み替えを希望している人は、14%弱いました。地方への憧れを口にしている人は、少数派ながらも珍しくはないのです。
【住み替えの意向を持つようになった理由】
1位「健康・体力面で不安を感じるようになったから」24.8%
2位「自身の住宅が住みづらいと感じるようになったから」18.9%
3位「自然豊かな環境で暮らしたいと思ったから」10.3%
4位「買い物が不便になったから」10.2%
5位「交通の便が悪くなったから」9.8%
「正直、地獄のような日々でした」
片山さんは、当時の心境をそう表現しました。理想と現実のあまりの乖離に打ちのめされ、結局、2年目の冬を迎える前に再び東京に戻った片山さん夫婦。「なんだかんだいって、ここ(東京)が私たちの故郷だったんだと実感しました」理想を追いかけて実現した田舎暮らし。しかし夢の生活は、想像以上に過酷なものだったようです。
[参考資料]
出所:認定NPO法人ふるさと回帰支援センター『2024年 移住希望地ランキング』
内閣府『令和6年版 高齢社会白書』

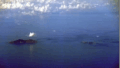

コメント