配偶者や家族が亡くなったときに受け取れることがある遺族年金は、亡くなった本人の状況や家族の人数など条件によって金額が変わります。もし母親の遺族年金が少なく感じるときは、平均額との比較をする前に、金額の決まり方を知っておいた方がよいかもしれません。
今回は、遺族年金の金額の決まり方や、受け取っている方の平均額などについてご紹介します。
遺族年金の金額の決まり方
遺族年金は「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があります。それぞれ受給要件が異なるため、遺族厚生年金を受け取れても遺族基礎年金は受け取れないケースもあります。まずは、それぞれの受給要件と金額の決まり方を比較しましょう。
遺族基礎年金
日本年金機構によると、遺族基礎年金は、子どもがいる配偶者か子どもが受け取れる年金を指すようです。なお、ここでいう子どもは「18歳になった年度の3月31日までにある方」とされており、子どもが障害年金での障害等級1級か2級状態の場合は20歳未満までが対象になるとされています。
子どものいる配偶者が受け取れる金額は、配偶者の誕生日が昭和31年4月2日以降なら「年83万1700円+子どもの加算額」、昭和31年4月1日以前なら「年82万9300円+子どもの加算額」です。また、子どもの加算額は1人目と2人目が23万9300円、3人目以降は7万9800円になるとされています。
遺族基礎年金を申請する際は、年金請求書を年金事務所や年金相談センターに提出しましょう。年金請求書には戸籍謄本や住民票の写し、亡くなった本人の住民票の除票などの添付書類が必要とされています。準備に時間がかかる可能性もあるので、できるだけ早く書類の準備に取り掛かるとよいでしょう。
遺族厚生年金
遺族厚生年金は、自身が優先順位で最も高い位置づけの場合に受け取れる年金とされています。
1位:子どものいる配偶者
2位:子ども
3位:子どものいない配偶者
4位:55歳以上の両親
5位:孫
6位:55歳以上の祖父母
なお、子どもや孫の条件は老齢基礎年金の子どもの条件と同じです。
日本年金機構によると、遺族厚生年金の金額は、亡くなった夫の「老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3」とされています。ただし、厚生年金の加入月数が300ヶ月に満たないときは、計算では300ヶ月加入していたとみなされます。加入時期が平成15年4月以降であれば、報酬比例部分は「平均標準報酬額×0.005481×加入月数」です。
例えば、平均標準報酬額が26万円で厚生年金に250ヶ月加入していた方が亡くなったとしましょう。加入期間は300ヶ月となり、亡くなった本人の報酬比例部分は「26万円×0.005481×300ヶ月」で42万7518円です。遺族年金は「42万7518円×4分の3」なので、年間約32万639円、月約2万6720円を受け取れる計算になります。
なお、申請方法は遺族基礎年金と同様とされています。
遺族年金は平均いくら受け取っている?
厚生労働省の「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、令和5年時点で遺族基礎年金・遺族厚生年金を受け取っている方の平均額は月8万2569円でした。
そのため、今回のケースの月8万円弱は、平均より下回るものの、ほぼ平均と同程度の額といえるでしょう。
まとめ
遺族年金は、条件を満たした子どもがいる場合に受け取れる遺族基礎年金と、優先順位の最高位であれば受け取れる遺族厚生年金があります。
特に遺族厚生年金は、亡くなった本人の収入や厚生年金加入期間によって、支給額が大きく変わります。遺族基礎年金・遺族厚生年金を受け取っている方の平均額は月に8万円程度という結果だったため、今回のケースの月8万円弱は、平均とほぼ同程度といえるでしょう。
遺族年金額が想定よりも少なかったときは、生活費の支援などを検討してみるのもよいでしょう。
出典
日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)
日本年金機構 遺族基礎年金を受けられるとき
日本年金機構 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)
日本年金機構 は行 報酬比例部分
日本年金機構 遺族厚生年金を受けられるとき
厚生労働省年金局 令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
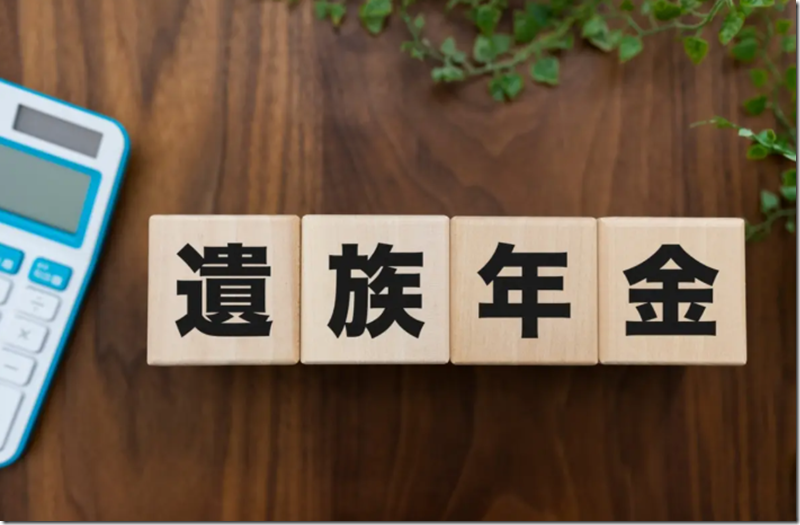
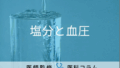

コメント