トランプ政権が発足して、はや100日が経過した。相次ぐ同政権の「無茶ぶり」に振り回されている各国だが、日本もその例外ではない。中でも今後、日本の頭を悩ませそうなのが、防衛費の負担増額だ。緊張感を増す東アジア情勢などにより、国防のための増額はやむを得ないとの雰囲気もある中、増額は果たして防衛力の「最大化」に最善の策と言えるのだろうか。限られた予算の中でも確固たる防衛力を担保する手法について、台湾のユースケースをもとに元プレジデント編集長の小倉健一氏が考える。
トランプ政権下で見込まれる「負担増」
「防衛力の抜本的強化」を目的として、日本の国防予算はここ数年で大幅に増額された。それでも足りないと見えるのか、トランプ政権において、米国防総省の国防次官(政策担当)エルブリッジ・コルビー氏は「日本は非常に裕福だ。なぜ彼らは脅威に見合ったレベルの支出をしないのか」と日本の防衛費の水準が低いと怒りをあらわにしている。

コルビー氏は日本がより防衛費を増額するべきだという考えを示している
(写真:The New York Times/Redux/アフロ)
こうした米国の要求は、単に同盟国への負担増を求めるものと見るべきではない。特にトランプ大統領は、一貫して掲げる「自国ファースト」の理念により、明らかに他国の紛争への積極的関与を避ける方向へと舵を切った。これは、日本自身の防衛努力が一層問われることを意味し、とりわけ台湾海峡を巡る緊張が高まる今日において、台湾有事がより現実的な脅威として迫っていることの裏返しとも言える。
日本の防衛費の増額については、米国からの圧力もあるものの、「安全保障」と名の付く分野では莫大(ばくだい)な支出が許容される土壌が日本にはあるように感じる。無駄があったり効率の悪さがあっても、それには目をつぶり、生命と財産を守る最後の砦なのだから仕方がないと考えてしまうのだろう。
増額は仕方ない?それは「大間違い」と言えるワケ
しかし、実際にはこれは間違った考え方と言えそうだ。先日筆者が訪れた台湾・台北にて意見交換をした、同国立法委員(日本の国会議員に当たる)の陳冠廷氏は、筆者に対して、こう述べた。
「このドローンのように、安くて、大量に作れる、効果的なドローンなどの攻撃能力が必要です」
陳氏が言うこのドローンとは、9万円程度で製造できる滑空式の攻撃型ドローンである。これで何十億円とする戦車を破壊できたら大きな戦果と言えよう。陳氏の発言を受け、筆者は、以下のような見解を伝えた。
「米国のトランプ大統領が防衛費を積み増せと、日本にも台湾にも言っている。しかし、防衛力を上げるためには、金額を積み増していくという発想よりも、支出できる予算の枠内でいかに最大限の抑止力や効果を発揮させるという考えに立たないと危うい」
陳氏は「その通りです。軍事予算に回すことで、国民の生活に回すべきお金がなくなってしまいます」と答えた。
陳氏の指摘は、台湾のみならず日本にとっても極めて重要な示唆を含んでいると言える。中国の公表国防費は日本の4倍以上とも言われ、実際の支出はさらに巨額であると見られている。このような圧倒的な物量の差を前にして、日本がいくら防衛予算を積み増したところで、正面から対抗しようとすれば焼け石に水だ。
もちろん、現場の部隊から「ミサイルを10発欲しい」「最新鋭の戦闘機がもっと必要だ」といった、より高性能な武器を求める要望が次々と出てくるのは当然のことである。しかし、そうした個々の要求に応え続けていったとしても、全体的な戦力差という根本的な課題が埋まるわけではない。
日本もまた、台湾と同様に、限られたリソースの中で最大限の効果を追求するべく、徹頭徹尾、防衛力の在り方を効率性の観点から見直さなければならない。日本や台湾を中国が攻撃すると大変な目に合うと信じてもらうこと、これが抑止力であり、限られた予算の中でそれをどう最大化するのかという点が重要だろう。
増額より行うべき「ある改革」
では、そのためにはどうするべきか。
具体的な方策の1つとして挙がるのが、軍事機能の一部を「民営化」するという方法だ。
米国、欧州連合(EU)では、政府がすべての安全保障や海上保安を管理するのではなく、民間の会社がその役目を担うことが試みられている。コストの削減(税金のムダ遣い削減)と最新装備への切り替え(安全保障の質の向上)を両立できるのは、「安全保障の民営化」である。日本も、すべてを政府が行うのではなく、民間企業を活用することで、無駄を減らし、安全保障の力を強くできるはずである。
そんな中、最近、面白い動きをしているのが台湾と台湾の民間企業だ。
台湾では、安全保障分野において民間企業の役割が大きい。背景には、中国からの圧力により、台湾政府が外国政府との武器取引が制約される中、民間企業を活用して安全保障能力を高める必要性があったという状況が存在する。台湾ではこの状況下、民間のテクノロジーを組み合わせることで安全保障機能を強化しようとしているのだ。民間企業であれば、政府の軍事機関とは異なる柔軟性と効率性を持ち、監視や防衛活動を担うようになる。
民間企業の最大の強みは、機動的な改造、改善、修繕とコストの最適化にある。政府が新たな装備を導入する際には、計画策定、予算確保、入札、調達、人員育成といった多段階のプロセスが必要となる。この間に技術革新が進み、購入時点ですでに陳腐化する可能性もある。さらに、一度導入した装備は長期間使用せざるを得ず、更新の柔軟性に欠ける。装備を自由に改造することも容易ではない。
なぜ台湾の「防衛体制」を見習うべきなのか
一方、民間企業はリース契約なども活用して、常に最新技術を導入できる。たとえば、台湾の安捷航空(Apex Aviation)は、海洋監視、海上風力発電所への医療ヘリ搬送、航空機のパイロットの訓練などを業務としている。同社の防衛・安全事業の責任者である洪曉榮(Honor Hung)氏は、以下のように述べる。
「台湾政府は、沿岸警備隊が空中監視システムを導入する計画を立てましたが、そのコストは500億台湾ドル(約2,500億円)に達しました。一方、民間企業が同等の監視機能を提供する場合、年間8億台湾ドル(約40億円)で済みます。政府の調達と比較して、圧倒的なコスト削減が可能です。政府の防衛機材の更新期間は原則7年ですが、イノベーションを続ける安全保障関連の機器は陳腐化が激しいです。民間企業であれば、さまざまな契約形態によって柔軟な対応ができます」
同社では、最新の監視技術・SAR(合成開口レーダー)を積極的に導入し、政府機関の能力を補完している。この技術は、雲や悪天候を透過して地形や物体を高解像度で検出する能力を持つ。これにより、台風や地震後の地形変化を即座に把握し、迅速な災害対応が可能となっている。ほかにも、同社ではパイロットの適性診断や訓練を行っているが、これらも航空会社だけでなく、自衛隊が外部へ委託しても良い分野であろう。
前述したように、米国や欧州では、民間軍事企業の活用は一般的である。密輸対策、テロリスク管理、海上監視、後方支援など、多くの分野で政府機関と協力し、安全保障を担っている。特に米国では、国防総省が多くの業務を民間企業に委託し、効率化を図っている。ウクライナ戦争でも、民間企業が提供するドローンや監視技術が大きな役割を果たしている。これらの事例を考えれば、日本が同様のアプローチを取ることは十分に合理的であると言えるだろう。
電通総研 経済安全保障研究センター主席研究員の部谷直亮氏は、「現代戦では絶え間ない改修が前提となっており、ウクライナでは両軍が毎月、新しい兵器を投入しており、兵器の改修も日単位です。技術的優位性は1カ月程度と言われており、英軍では現代戦を“1日限りのアイディアの戦争”と表現しています。こうした速度には従来の防衛産業も軍隊も追随は難しいものです。が、安捷航空の取り組みはこの問題に対する有効な回答の1つだと思われます。運用や日々の改修まで含めて委託するやり方は見習うべきですし、彼らに日本法人を設置させての委託も検討すべきでしょう」と語る。
日本の防衛意識は「もはや時代遅れ」?
台湾の事例から、日本が学ぶべき点は多い。政府の軍事部門は戦争遂行能力を高める役割を持ち、装備の調達・運用を行う。しかし、監視、災害対応、医療搬送といった分野では、民間企業のほうが迅速かつ安価に対応できる可能性がある。政府がすべてを抱え込むのではなく、適材適所で民間企業を活用すれば、全体の効率が向上し、限られた予算と人員でより大きな効果を生み出すことが期待できる。
防衛白書によると、装備の高度化や複雑化により、装備全体のコストが増加傾向にある。計画通りに装備を取得し、適切な経費で運用するには、装備のライフサイクル全体を考えた管理が不可欠とされている。そのため、防衛装備庁が重要な装備を選定し、長期間にわたる管理を行う体制を整えている。
しかし、調達には多くの問題が残る。電子作戦機の導入計画では、新型機が求められているものの、コストが9,051億円に達し、既存機の改修で対応する方針が示されている。だが、この対応では古い装備の陳腐化リスクを完全に防げない。無人機の導入計画も、不確定要素が多く、コストすら明確になっていないケースも散見される。これらは、硬直的な調達システムと、変化への対応の遅さを示唆している。
日本では、民間軍事企業の存在自体が少なく、政府機関がすべてを担おうとする傾向が依然として強い。しかし、この考え方は、国際的な潮流や技術革新のスピードを鑑みれば、すでに時代遅れとなりつつある。民営化も視野に入れた自衛隊や海上保安庁の非効率の是正や、戦略的に民間企業を活用する仕組みの構築を実現し、真の抑止力向上と国民の安全確保を両立させる必要があるだろう。
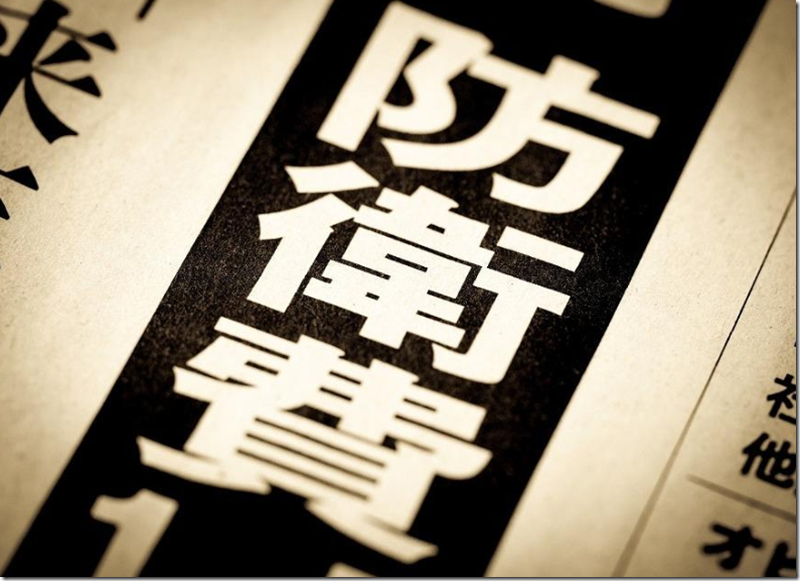


コメント