トランプ政権の発足から、はや3カ月。
日米同盟に「不公平」と不満漏らすトランプ。
アメリカに「従属」続ける日本が、「代償」として支払うものとは……。
『従属の代償 日米軍事一体化の真実』の著者であるジャーナリスト・布施祐仁氏と、『永続敗戦論 戦後日本の核心』の著者である政治学者・白井聡氏が、「トランプ2.0」下のアメリカ、そして日本のこれからについて語ります。
【対談】トランプ政権と対米従属 #7
※本記事は、2025年1月31日にジュンク堂書店池袋本店様にて開催されましたトークイベント「「日本は対米従属から脱却できるのか?!―トランプ米大統領就任から考える『日本のこれから』」の一部を抜粋・編集したものです。
▶︎▶︎▶︎まだお読みでない方は、「米国を「恐怖の底」へ突き落とした中国!米国が日本を「犠牲」にしても守りたいものとは一体…」もぜひお読みください。
長期政権の意外な「共通点」
布施 白井さんの『国体論』(集英社新書、2018年)の中では、「国体」というものが国民の政治的主体化の阻害要因になっていると書かれていますが、そのあたり少しご解説いただいてもよいでしょうか。
白井 そうですね。なぜ国体が阻害要因になっているのか。要するに天皇制の代わりに、代わりにというかモデルチェンジするような形で、アメリカが天皇のポジションについた。それが日本の戦後対米従属のあり方なんですが、これは世界でも類を見ないですね。これが戦後日米関係の本質であるならば、日米同盟のために、そしてアメリカの覇権を維持するために、いざ台湾有事が起こったならば日本が最前線でもって奮闘するというのは、ロジカルに考えれば、ある意味当然といえば当然。
だって、大日本帝国においては、「天皇陛下のために死ぬ」というのは当然の義務として認識されていたわけですよね。その天皇陛下が戦後、アメリカに入れ替わったんだとするならば、「アメリカ様のために喜んで命を差し出す」「アメリカの繁栄のためであれば、自己犠牲は日本人の当然の義務であり、むしろ喜びではないか」という精神を持たなければならない。この問題が今、問われているわけですよね。
対米従属を長年にわたって続けて、ゆがみきった精神になってしまっている状況がある。そこで、戦後日本人が独立的な主体たりたり得ないのは、なぜかということが気になるわけです。布施さんはどのようにお考えですか。
布施 やはり日本の本質というものは、戦前と戦後で変わってないのだと僕はずっと感じていて。結局、権威主義なんです。戦前の日本の統治は、戦争遂行も含めて、天皇の絶対的な権威の下でおこなわれました。アメリカは、その天皇の権威を利用するのが、日本の占領支配を成功させるベストな方法だと考えた。そこで昭和天皇の戦争責任を問わずに、天皇制も残した。昭和天皇も共産主義を非常に恐れていたので、自分や日本をアメリカに守ってもらおうとしました。
マッカーサーは昭和天皇に「征夷大将軍」に任命されて、日本の統治を任せられたのだという白井さんの指摘は、非常に的確な表現だと思いました。日本を支配するアメリカの権威は、戦前の絶対的な権威だった昭和天皇によってお墨付きが与えられ、日本国民もそれを受け入れた。そういう中で日本は対米従属の中に入っていったのだと思います。
もちろん、それだけではない。アメリカの側につくことによって、アメリカの巨大な市場へのアクセスを認められ、工業製品を輸出して経済成長するという、大きな「うまみ」も確かにあったわけです。
ただ、1970年ころに日本の経済力がドイツを抜いて世界第2位になると、アメリカは日本の経済成長を抑えにかかってきますよね。繊維に始まり、やがて半導体に及びます。今は、日本の輸出に占めるアメリカの割合は低下し、中国とほぼ並んでいます。こうした現実を直視するならば、アメリカに従属して中国と対立するのは日本の利益にならないはずなのに、思考停止してアメリカにひたすら追随しています。
なぜ、こうした非合理的な状況が続いているかというと、結局、ものすごく権威主義的な社会だからだと思います。
僕が物心ついてからの日本の長期安定政権といえば、1980年代の中曽根政権、2000年代の小泉政権、2010年代の安倍政権です。この3つの政権に共通するのは、アメリカから求められた軍事協力の拡大に忠実に応え、アメリカ大統領と良好な関係を築いたことです。日本国民の中に、日本の首相がアメリカの大統領に高く評価され、良好な関係を築いていると、頼りがいのあるように感じてしまう心理があるように思います。根っこにあるのは、「長い物には巻かれろ」という権威主義です。
そのあたりに、対米従属から逃れられない理由があるように思います。
白井 はい、そのような権威依存人間だから、自分の中に物事を判断する基準というのがないんですよね。政治家や役人もそうですし、学者のほとんどもそうだと思います。
「ヤクザの抗争」と化した覇権争い
白井 ただ、これからは、それでは「きつい」んですよ。どうきついかというと、たとえば、ポスト冷戦秩序がいよいよぐちゃぐちゃになって崩れてきて、新帝国主義の時代に入りつつあるんだという分析をする人もいます。確かに、そういう新しい状況も生まれてきているだろうと思います。
一体それは何が変化してきたということなのかを考えてみると、一つには、先ほどお話したような、アメリカを中心とする先進国のG7体制が世界を支配できなくなってきて、グローバルサウスが台頭し、それがドル覇権を揺るがすということがある。
それからもう一つ。長年アメリカは懸命に、自由と民主主義こそが大事であって、これは当然世界中に普遍的に広がっていくべきものであって、そのスタンダードを明らかに無視している中国なんかはおかしいんだというスタンスをとってきました。しかし、トランプは明らかにその点で、バイデン政権とは違いますよね。そんなことはどうでもいい、それよりもアメリカ人をどうやって食わせるかの方が大事だという、ある意味現実的なものの見方をしている。ロシアに対する姿勢もそれに近い。
ついでに付け加えると、日本の外交もその辺は修正をしてきています。自由や民主主義や法の支配といった「優れた価値観」を共有する国とは親密にして、そうでない国とはちょっと距離を置きましょうという「価値観外交」、これは早い話が、中国を敵としておいて、アメリカとの関係をべったりと続けるための理屈なんですが、日本は実は岸田政権のときから、この価値観外交を密かに引っ込めております。国連などの国際舞台での演説の文言を注意深く読むと、価値観外交が実は放棄されている。つまり今、イデオロギーはゼロの状態になっている。イデオロギーの時代が終わったんですよ。
そうなると、ときに紛争という形で現れ、ときに圧力の掛け合いという形でこの世界に現れるさまざまなコンフリクト、これが一体何に似てくるかといえば、ヤクザの縄張り争い、ヤクザの抗争なんですよね。
ヤクザの抗争って、イデオロギーは別にないじゃないですか。あれは要するに「勢力圏争い」ですよね。それぞれが持っている勢力圏があって、いろいろな事情――勢力を広げたいだとか、それは許さんだとか――によりドンパチが起こる。
しばらくガチャガチャとやっていると、互いの損傷が激しくなったところで「ちょっといい加減にした方がいいんじゃないか」と第三者、たとえば別の地域の親分なんかが出てきて、「あんたたちそろそろ手打ちしなさい」とか言って、和解の盃とかを酌み交わさせるわけですよ。一度和解をしたら、抗争を簡単に再開するわけにはいきません。それは、あいだを取り持った親分の顔を潰すことになりますからね。
そのようなヤクザの抗争のような「ゲームのルール」でもってコンフリクトが起こり、またコンフリクトが解消される。新しいようで実は古い政治のダイナミズムに戻っていくわけです。
▶︎▶︎対談を前回から読みなおしたい方は#6「自衛隊と米軍「ズブズブの関係」に「シラを切る」日本政府…既視感の正体「まるで関東軍」」へ
▶︎▶︎▶︎議論の内容をさらに詳しく知りたい方は、「台湾有事」衝撃の結果予測!唐突すぎる「方針転換」に相次ぐ怒りの声「聞いてない」もお読みください。
本記事の著者・布施祐仁氏は、新刊『従属の代償 日米軍事一体化の真実』(講談社現代新書)で、米国への従属の道を歩んできた日本の歴史を振り返りながら、現代を「新しい戦前」にしないために「日本に必要なこと」を解説しています。ぜひ、お手に取ってみてください。
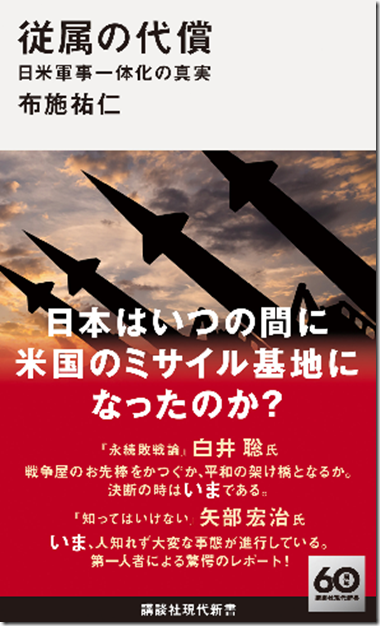
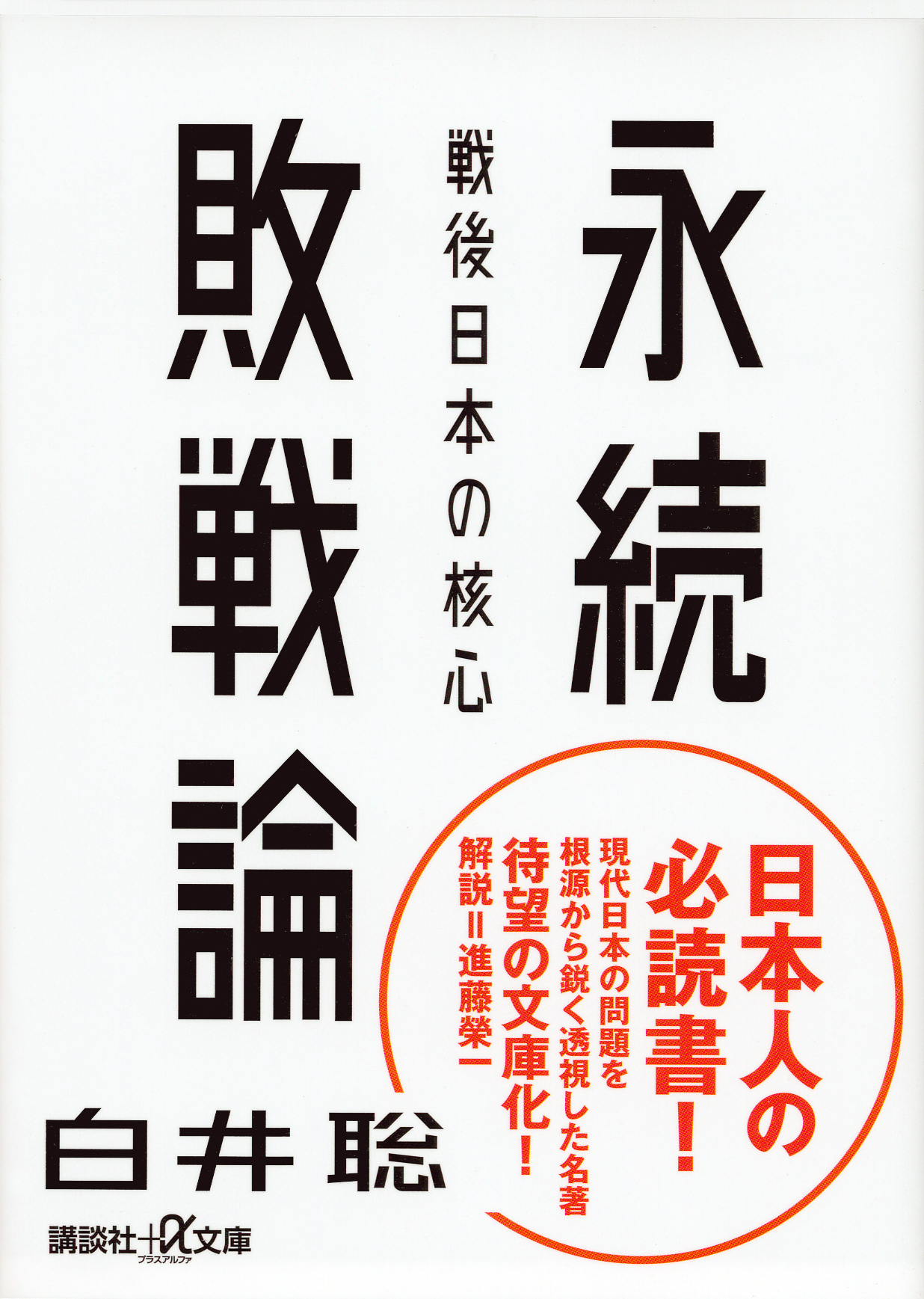
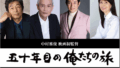

コメント