親の死後、生命保険金を受け取ったとき、「このお金って税金がかかるのかな?」と不安に思う方も多いでしょう。
特に金額が大きい場合や、複数の相続人が関わる場合は、相続税の申告が必要なのか迷うこともあります。
本記事では、死亡保険金に相続税がかかる条件、非課税枠の考え方、課税される場合の注意点などを、相続手続きを初めて経験する方でも分かりやすく解説します。
死亡保険金に相続税はかかる?
生命保険金は「受取人固有の財産」として、通常の遺産とはやや扱いが異なりますが、相続税の対象になるケースがあります。
具体的には、亡くなった方(被相続人)が保険料を負担していた場合、生命保険金は「みなし相続財産」として、相続税の課税対象になるのです。
ただし、すべての保険金が課税対象になるとは限りません。一定の条件を満たせば、「非課税枠」が適用されます。
非課税になる条件とは? 金額と相続人の人数に注目
死亡保険金の非課税枠は、以下の式で計算されます。
500万円 × 法定相続人の数
たとえば、受取人が配偶者と子ども2人の3人であれば、非課税枠は500万円 × 3人 = 1500万円です。この枠内であれば、保険金に相続税はかかりません。
したがって、1000万円を受け取ったとしても、法定相続人が2人以上いれば、非課税枠内に収まるため、申告も納税も不要です。
ただし、受取人が法定相続人以外(例:親族以外、孫、内縁の配偶者など)の場合、非課税枠は適用されないため、注意しましょう。
【PR】「相続の手続き何にからやれば…」それならプロにおまかせ!年間7万件突破まずは無料診断
相続税がかかるケースと申告の注意点
保険金の受取額が非課税枠を超えた場合、その超えた分と他の遺産(不動産・預金など)を合わせた合計額が、相続税の基礎控除を超えると相続税がかかります。
相続税の基礎控除は、以下の式で計算されます。
3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
たとえば、法定相続人が3人なら、基礎控除額は 4800万円 になります。遺産総額がこの金額以下であれば、相続税の申告は不要です。
逆に、超えている場合は、死亡から10ヶ月以内に相続税の申告・納税をする必要があります。
また、相続人が未成年・障害者・海外在住者など特殊なケースに該当する場合、追加の控除や注意点もあるため、専門家に相談すると安心です。
まとめ:制度を理解して正しく対応しよう
生命保険金1000万円を受け取った場合でも、法定相続人が2人以上いれば相続税はかかりません。
ただし、非課税枠が適用されるには、「被保険者かつ保険料負担者=亡くなった方」「受取人=法定相続人」という関係性が必要です。
相続税がかかるかどうかは、保険金の金額だけでなく、遺産全体の合計や相続人の人数にも左右されます。不安がある場合は、早めに税理士や専門の窓口に相談し、期限内に正しい手続きを進めることが大切です。制度を正しく理解すれば、慌てず安心して相続に対応することができます。
出典
国税庁 No.1750 死亡保険金を受け取ったとき
国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
国税庁 No.4152 相続税の計算
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

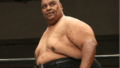
コメント