落花生を収穫、脱穀する生産者=鹿屋市東原町
おつまみなどに人気の落花生を鹿児島県内で最も多く生産しているのが鹿屋市だ。ただ、全国的には「千葉産」が圧倒的なシェアを占めているのが実情。知名度向上や、さらなる収量増が課題となる中、「塩ゆで」推しで打開を図ろうとする生産者もいる。
農林水産省の統計によると、都道府県別の落花生の生産量(2024年)は千葉県が1万2800トンで、全国の86%を占めてトップ。以下、茨城1180トン、神奈川231トン、鹿児島175トン、山梨37トン。また、県によると、県内市町村別(23年産)では鹿屋市が最多の55トン。以下、西之表市、肝付町、霧島市、錦江町と続く。
千葉や茨城に水をあけられているとはいえ、鹿児島の落花生栽培が盛んな要因について、鹿屋市の担当者は、水はけの良いシラス土壌が多いことを挙げる。また、在来の落花生を研究する鹿児島大学教育学部技術専門職員の中野八伯(はつのり)さん(45)は「やせた土地での栽培に適している」と話す。
ただ、鹿屋市で生産している三和物産(同市)の和田彰常務は、「鹿屋産」や「鹿児島産」の知名度不足を自覚している。「千葉のイメージ、生産体制が強すぎる」という。
■ □ ■
8月中旬、同社が所有する東原町の畑を訪ねると、炎天下で収穫の真っ最中だった。従業員が機械で茎ごと土から抜き、落花生の実を脱穀機にかけていた。その後は工場に運んで洗浄し、塩ゆで用、いり豆用、原材料用など用途別に加工する流れとなっている。
県内では8月から10月にかけて落花生の収穫シーズンを迎える。近年は猛暑と重なるため、屋外での作業は働き手の負担が増すばかりだ。
さらに、栽培初期に他の作物と比べて手間がかかりすぎることもネックとなっている。
地温の調整や雑草抑制のために土壌を黒いカバーで覆う「マルチ」は、需要が高くないため専用のものがまだない。鹿屋市の場合、おおむね3月後半~4月前半ごろに種をまくが、生産者は落花生を成長させるための穴を一つ一つ加工したり、特注したりしている状況だ。
このほか、病気にかかりやすくなるため連作できないことも収穫量の増加を阻む要因となっている。
■ □ ■
それでも同社は地元の落花生の存在感を高めようと、約20年前から生産を続け、PRも工夫してきた。今、力を入れるのは、県内では比較的見られる「塩ゆで」の食べ方を県外に発信することだ。
適した品種を求めて、大きなシェアを誇る「千葉半立(はんだち)」ではなく、大粒で皮が白いのが特徴の「郷(さと)の香(か)」を採用。現在はこちらが大隅地域の主流になっているという。
和田常務は「ビールに枝豆みたいに、焼酎に落花生というセットでのイメージができれば、より知名度が上がるのではないか。さらなる需要につなげ、県外の人にも関心を持ってもらえたら」と期待する。
■鹿児島県の落花生は琉球経由で伝来か 垂水に説明版
鹿児島、大隅の落花生はどこから伝わってきたのか-。大隅地域の歴史や文化の継承に取り組む郷土史家らでつくる「大隅史談会」には、この疑問に答える資料が残っている。まとめた上園正人さん(故人)の結論は「琉球経由のルート」だ。
上園さんの資料によると、日本で落花生の本格的な栽培が始まったのは明治時代。ただ、それ以前に琉球へも流入し、それが薩摩半島の山川(指宿市)に伝わり、「琉球豆」「南京豆」などと呼ばれていた。
大隅地域に落花生を伝えたのは、垂水の「田中良八」という人物とされる。山川に行った際に落花生を持ち帰り、試しに植えてみたところ、うまく収穫できた。上園さんは、これが県本土初の落花生栽培だと説いている。
このほか、田中が増産を進めるために近隣の町や村を回って栽培を勧め、このうち特に現在の鹿屋市花岡地区が産地になったと書いている。こうした内容は、垂水市新城の国道220号沿いにある「落花生の伝来地」の説明板にも記されている。


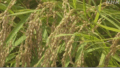

コメント